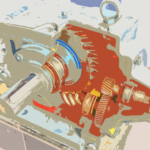六畳一間の私の家のクローゼットの扉を開けるとその向こうには理想の世界がある。そこはやわらかい砂浜と静かな海が広がっており空はいつでも夕暮れのような淡い色をしている。海の沖では優しく唄うクジラたちが暮らしており彼らが大きく宙へ跳ねるときらきら光る白い波が砂浜まで届く。またある時にはネオンのように発光するフラミンゴの群れが頭上に飛来し空をピンクに染める。海に背を向ければ街路樹のように等間隔で並べられた無数の全身鏡を見つけることができる。全身鏡には望んだ通りの洋服を着て望んだ通りの化粧を施し望んだ通りの髪型になった自分の姿が映る。鏡の列に沿って歩くと白く塗られた小屋に到着する。小屋の中には痩せた壮年の男がひとりで暮らしており私は彼を『パパ』と呼んでいる。
幼い頃の私は父のことを優しいひとなのだと思っていた。私の行為を厳しく咎めたり私の不出来に声を荒げる用なことが一切なかったからだ。いつも家に居てのんびりとしており私にとっては怖れる必要のない安全な大人だった。そういうふうな父の姿勢が優しさゆえのものではないと気付いたのはいつ頃だっただろうか。例えば砂糖を舐め続ける子どもを見て身体に悪いからやめるよう注意する大人と黙ってニコニコ眺めている大人とではどちらが優しいだろう。何より父は私が怪我や病気をした時にも普段通りにのんびりしているだけで助けてくれなかった。私がそれまで父の優しさだと感じていたものは実際のところただの無関心でしかなく路肩で見かけた鳩に対してパンくずを投げるような態度でしかなかったのだと分かった。
一方で母のことは幼い頃からいつも怖れてきた。私に対して怒声や罵声をたびたび浴びせたからだ。もちろん私を思いやっての叱咤もあっただろうが単に苛立ちをぶつけていただけの場面も同じくあっただろう。そして私はそれらふたつを区別できるような賢い子どもではなかった。だから母が語気を強めるたびにごめんなさいと私は口にしたがそれはほとんど反省によるものではなく降り注ぐ怒りをやり過ごすための避難措置でしかなかった。そんな母だが父に対しては異様に甘かった。昼夜を問わず働き詰めてたったひとりで家計を支えていたが終日家に居るだけの父には微温い言葉を掛けるばかりでそういう面にも私は怖れを覚えた。
理想の世界の白い小屋では痩せた男がひとりで暮らしており私は彼を『パパ』と呼んでいる。『パパ』は私の父とは違いきちんと仕事をしている。私が部屋を訪ねる時には決まってパソコンの画面を見つめながらキーボードを叩いている。お金をたくさん持っているので買えないものもない。パソコンで以て注文をしたならどんなものでも三分以内にダンボールに入って小屋の前まで届く。『パパ』はこれまで私の望むものをなんでも買ってくれた。洋服に美容師に仔猫に化粧品、高級な車やプール付きの豪邸やいくらたべても太らないケーキを貰ったこともあったし、海を泳ぐクジラや空を飛び交うフラミンゴだって私が『パパ』におねだりをして買ってもらったものだ。ここは理想の世界だ。私が『パパ』に伝えた理想がそっくりそのまま実現される世界だ。
十八歳になり働き始めた私は六畳一間のアパートを借りて一人暮らしを始めた。金銭的にはかなり厳しくクローゼットとベッドの他には家具らしい家具も買えない状況で始まった新生活だったがそれでも両親のもとから離れることを躊躇はしなかった。冷蔵庫とか炊飯器もなく食事はもっぱらコンビニで買って済ます他なかったがそれでも後悔することはなかった。当時の私は両親に対してそれほどまでにうんざりしていたのだ。家を出る意思を伝えた時のことははっきり覚えている。父はいつものようにのほほんとして何も言わず母は火のように怒って反対した。引越しの当日は逃げるようだった。
クローゼットの奥には理想の世界がある。私の願いを『パパ』がそのまま実現することで築かれた世界だ。そしてこの『パパ』自体もまた私の中の理想を編み上げる形で生み出された男だ。父とは違う理想の父親として作り出した男だ。娘に対して関心がなく配偶者には依存する怠け者の父とは正反対の男性として創造したのが『パパ』だ。だからこそ私はここを訪ねると毎回疑問に思う。ベッドの上で一糸纏わず私を組み敷く『パパ』を見上げながらどうしてこんなことになってしまったのだと思いを巡らせ虚ろな気持ちになる。私は考える。おそらく理想というものにはふたつの種類がある。自分が幸せになるために必要なものを望んでいる理想とそうではない理想だ。前者を抱いてそれが叶えばひとは幸せになれるが後者はどれだけ叶えたところで虚しくなるばかりだ。私がここで叶えた理想はいずれも後者だった。前者の理想を抱くためには自分が幸せになるために何が必要かを知っていないといけない。私はそれを知らない。ならどうすればそれを知れるだろう。私は考える。理想の世界で理想の男に汚されながらあれもこれもが足りない頭で私は考え続ける。
目を覚ますと六畳一間の自宅のベッドの上に居たが酷い寒気があり全身の関節がキシキシと痛んで身体を起こせなかった。頭の方もぼうっとしていたが自分が高熱を出しているであろうことはなんとか理解できた。キッチンの方からは匂いと音がした。首を動かしてキッチンに目をやると誰かがそこで料理をしておりそれは母だった。手に握られたスマートフォンには私自身が母に発信した履歴が残っていた。私が目を開けていることに気づくと母はこちらを向き「そんなに痩せていつも何食べてるの。冷蔵庫ぐらい買ったげるから栄養取りなさい」と厳しい口調で言った。

あとがき
欲しいものを手に入れるというのは勿論むずかしいけど、その前段階で、必要なものを欲しがるというのもきっと難しい。追いかけては間違えに気付いて、次を追いかけて……。その繰り返しを幾度もやる中で、必要なものに少しずつ近づいていくのでしょう。
2019/09/18/辺川銀