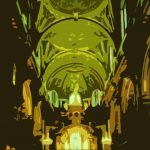アルバートは廃墟になり錆びついた工場で過ごすことを好んだ。アルバートは美しい男だった。髪が長く、時々少女に見間違えられることもあった。比較的口数は少なかったが、角砂糖を砕いたような声で喋りミルクのような表情で笑った。アルバートが笑顔を見せたのは廃墟になり錆びついた工場の煙突の上に登って空を見上げた時だ。空の様子はいつも変わらないからとても安心するのだと言った。アルバートは十五歳から十九歳ぐらいに見えた。しかし誰もアルバートの本当の年齢を知らなかった。アルバートは機械の身体を持っていたからだ。機械の身体を持ったアルバートはずっと長い時間を、死ぬことも老いることもなく生き続けることが出来た。
アルバートの見た目は普通の人間とまったく見分けがつかない。普通の人間よりずっと美しいが、だからといってその身体が機械で出来ているなどということは誰も想像がつかない。アルバートは普通の人間と同じように食事をとり、睡眠をとる。比較的口数は少なかったが、泣くことも笑うことも出来たし恋人を作ることも出来た。三十六度五分の体温があり恋人と抱き合っても機械の身体だと気付かれることはなかった。アルバートの見た目は普通の人間とまったく見分けがつかない。ある日の出来事だった。アルバートはいつものように煙突の上にひとりで座って夕日を眺めていた。ふと空に手を伸ばそうとするとアルバートは自分の右腕が錆びついて動かなくなっていることに気付いた。アルバートは煙突から降りて廃墟になった工場の地下にある秘密の研究所に向かった。彼はそこで壊れた右腕を外して、あらかじめ作っておいた傷一つない右腕を新たに装着した。交換は慣れた手つきで素早く行われた。機械の身体を持ったアルバートはこうして部品を交換することによって、ずっと長い時間を、死ぬことも老いることもなく生き続けることが出来た。
あるところで、女がひとり死んだ。ちょうど七十年間生きた。三十歳の時に結婚してふたりの子どもをもうけた。ふたりの子どもはそれぞれ大人になって彼女に合計四人の孫を与えた。女は裕福ではなかったが貧しくもなかった。物静かだったがよく微笑む女だった。女の葬式は良く晴れた日の教会で営まれ百人ほどの知人がそこに参列した。人間というのはアルバートと違って古い部品を交換することが出来ないのでほとんどは生まれてから百年も経たずに死んでしまう。死んだ女はかつてアルバートの恋人だった女だ。人間というのは不便だなとアルバートは思った。知った人間が死ぬたびにアルバートはそう思った。その晩アルバートは煙突の上で月を見ながら泣いた。アルバートはずっと長い時間を死ぬことも老いることもなく生き続けることが出来た。今までに一体自分が何度泣いたか、アルバートは思い出すことが出来ない。
アルバートはその日も廃墟になった工場の地下にある秘密の研究所に向かった。小型カメラになっている右目を一度外してから、眼窩の奥に埋め込まれている青い小さなチップを取り出す。そして新品の青いチップを新たに装着してから、恥した右目を再び眼下に埋めた。チップの交換は慣れた手つきで素早く行われた。交換された青いチップは彼の記憶装置だ。アルバートは古くなった腕や脚や内臓を定期的に交換することでずっと生き続けることができた。交換が必要なのは心臓や記憶もまた例外ではなかった。記憶の交換を終えるとアルバートは静かに横たわり意識をシャットダウンして深い眠りについた。翌朝再起動された時には、生きていくうえで最低限必要なことだけを除きすべてを忘れている。なので今までに一体自分が何度泣いたか、アルバートは思い出すことが出来ない。
廃墟になり錆びついた工場でアルバートはドクターに出会った。ドクターは白髪の老人で科学者をしているのだといった。ドクターはひと目でアルバートが生身の人間ではないということに気付いた。アルバートは驚愕した。ずいぶんと長い間生き続けてきたがアルバートが機械だということを言い当てた人間はこれまで、少なくともアルバートの覚えている範囲内では、ただのひとりも居なかったからだった。アルバートはドクターに自分の身体と地下にある研究所について紹介した。その後ドクターは何度か繰り返しアルバートのもとを訪れ、アルバートの身体や研究所の施設を研究した。アルバートはもともと口数の少ない男だったが、ドクターと話す時には普段よりも多く喋りそしてたくさん笑った。
アルバートは機械の身体をしていた。機械の身体を持ったアルバートは古くなった部品を交換することによって、ずっと長い時間を、死ぬことも老いることもなく生き続けることができた。交換が必要なのは記憶も例外ではなかった。なのでアルバートは自分が、誰によって作られ、何のためにこんなにも長い時間を生きているのかについてまったく知らなかった。ただ、この身体には部品を交換し生き続けるというプログラムが本能のような形でインプットされているということだけが分かった。心臓が古くなってきたので交換作業をした。心臓の交換は胸板を外して行う。アルバートの心臓にはモーターがふたつ入っているので、そのひとつづつを外して新しいものに換えるという動作を二回繰り返した。これもまた記憶とは別の部分にプログラムされている非常に手慣れた動作だ。作業を終えたアルバートは左胸に手を当てモーターの音を聞いた。今後数十年にわたって自分を動かし続けるだろう新しい心臓について思った。
ドクターが死んだ。ちょうど七十年間生きた。家族に看取られ穏やかな死だったのだという。ドクターは優秀な科学者だったので多くのひとが彼の最期を惜しんだ。アルバートは美しい男だった。髪が長く、時々少女に見間違えられることもあった。アルバートはドクターの死を知り、かつて近しかった人間でちょうど七十年で死んだ人間が他にも居たような気がしたが思い出すことが出来なかった。ドクターはアルバートの身体が機械で出来ていることを見抜いた、アルバートが覚えている範囲内では、ただひとりの人間だった。その晩アルバートは煙突の上で月を見ながら泣いた。身体中が錆びついてしまいそうなほど泣いた。今までに一体自分が何度泣いたか、アルバートは思い出すことが出来ない。だが泣き続けるうちにアルバートは、こんなに深く激しく泣いたのは生まれてはじめてだということが分かった。はっきりと分かった。
アルバートは廃墟になり錆びついた工場で過ごすことを好んだ。アルバートは、煙突の上に登り空を眺めることを好んだ。空を眺めることでアルバートは安心することができた。アルバートはずいぶん長い時間を生きたが、彼がどんなに長く生きても空というのはずっと変わることがなかった。ある晩空を眺めながら、アルバートは自分の記憶が古くなり交換が必要な状態にあるということを察した。古くなった記憶は古くなった腕や脚や心臓と同様に交換することが必要だった。むしろ記憶こそが、アルバートを構成するすべての部品の中で最も、定期的な交換を必要不可欠とする部品だった。夜空を眺めながら、アルバートはいつだったかドクターが生前言っていたことを思い出した。アルバートの身体には部品を交換し生き続けるというプログラムが本能のような形でインプットされているが、そのプログラムは、古くなりすぎた記憶をそのまま放っておくことによって書き換えられ正常に機能しなくなる場合があるのだということをあの時ドクターはアルバートに伝えていたのだった。アルバートは美しい男だった。髪が長く、時々少女に見間違えられることもあった。アルバートは空を眺めながらミルクのような表情で笑った。