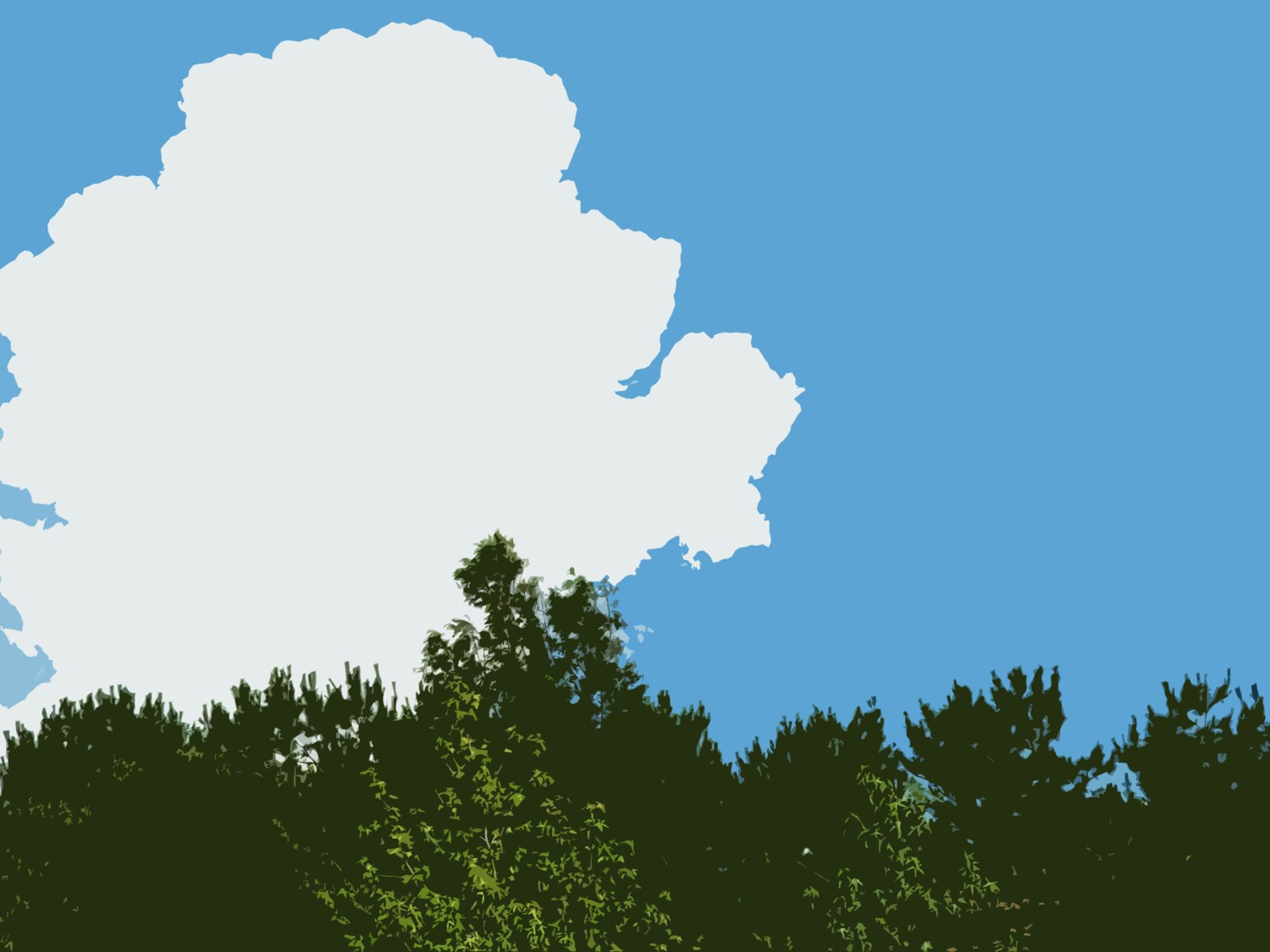母の墓参りをするために五歳の娘を連れて霊園を訪ねた。平日の午前中で日差しが酷く強いこともあり霊園には私たちの他に誰も見当たらない。聞こえてくるのは蝉の鳴き声だけだ。今は晴れているが遠くには大きな入道雲が見えるので数時間後には雨が降るかもしれない。
私が母の墓石に水を掛けていると、どこかで捕まえてきたシオカラトンボを右手に持った娘が、それを得意げに見せびらかしながらこちらに笑いかけた。私はその様子をスマートフォンで撮り、今は会社で仕事をしている夫に送信した。娘の手から離れて飛び立ったトンボは、ものの数秒でどこかに飛び去って行った。
買ってきた花を華瓶に挿してから、線香をあげた。空に登っていく線香の煙を眺めながら、娘がふと、私にこう尋ねた。「ねえママ。あたしのおばあちゃんはどんなひとだったの?」
幼い頃。私も母に、同じ疑問を向けたことがあった。私にとっての祖母。娘にとっての曾祖母。母にとっての母に当たるひとはどんなひとだったのかと。
「酷い親だった」と、母はその時答えた。「ほとんど家にも居ない親だった。家族がどんなに寂しがっても省みなかった。だからあなたにはそんな思いを決してさせないわ」と続けて、まだ小さかった私の身体をきつく抱きしめた。
その言葉通り母は私を手厚く扱った。運動会や授業参観には欠かさず来てくれたし、私が宿題をする時は終わるまでずっと隣に居てくれた。着る洋服や読む本や目にするテレビ番組もぜんぶ選んでくれた。夜は必ず手を繋いで寝かしつけてくれた。
中でもよく覚えているのが、毎朝、投稿前に私の髪を結ってくれたことだ。「あなたの髪は本当に綺麗だね」と口癖のように言い、温かい手でポニーテールや三つ編みに結い上げてくれた。母が結ってくれた髪は同級生や先生たちからもすこぶる評判で、私はそれがとても嬉しかった。
中学生になっても母の調子は相変わらずだった。入部する部活動は母が決めた。綺麗になるためには運動をした方が良いけど日焼けをするのは良くないという理由で、活動のほとんどを室内で行う体操部に入ることになった。三年生の時に受験する高校を選んだのも母だった。そんな私たち親子の関係を「変わっているね」と珍しがるひとは少なくなかったが、私はすっかり慣れていたので、この時点では特に違和感を覚えることはなかった。
私がはじめて母の意に反したのは高校生の時だ。ある日の放課後、私は母に黙って美容室に行き、髪を短く切った。この頃もまだ、母は私の髪の毛を宝物のように扱い、毎朝丁寧に結い上げてくれていたのだけど、それでも髪を切った。なぜなら当時、私は同じクラスの男の子に恋をしていたからだ。その男の子について「どうやら彼は短い髪の女子が好きらしい」という噂を小耳に挟んだからだ。
背中のあたりまであった髪を、耳が出るほど短くして帰ってきた私の姿を見て、母は狂乱した。食器だとか、花瓶だとか、家の中にある色々なものが一夜のうちに壊れた。金切り声や怒鳴り声は朝まで止むことがなかった。
以降、母はよりいっそう、私に強く干渉するようになった。それまでは高校まで自転車で通っていたのだけど、車で校門の傍まで送り迎えをされるようになった。結う髪がなくなった代わりに、毎晩お風呂場に入ってきて、高いシャンプーで私の髪を洗った。
そんな日々が続くうちに、私は体調を崩した。母の作る食べ物が一切喉を通らなくなって、無理やり流し込んでも全部吐き戻してしまうようになった。体重がみるみる減り、うまく学校に通えない日も増えた。見かねた担任に付き添われて病院を受信すると、入院することが決まり、それからの数ヶ月は母から引き離されての生活を送った。
高校をなんとか卒業すると私は就職した。母の元を離れてひとりで暮らし始めた。母は当然猛反発したけど、当時の担任や主治医が後押ししてくれた。
ひとり暮らしでは苦労することがとても多かった。例えばその日に来ていく洋服とか、夕飯の献立、コンビニで買う雑誌、休日に観る映画なども自分で選んで決めなければならず、そういうことが当時の私には非常に難しかった。
この時になって、私はようやく、母が自分をどういうふうに育ててきたのかはっきり理解した。母はきっと私に、いつまでも小さく弱く何も出来ないまま、何も自分で決められないままで居てほしかったのだ。ずっと母の手を必要とする子どものままで居てほしかったのだ。
ひとり暮らしを始めてから、母は頻繁に私のアパートを尋ねてきた。仕事から帰ると、合鍵で家に入ってきた母が夕飯の支度をして待っていたこともあった。一日に五回も十回も電話が掛かってくることは珍しくなかった。実家に戻ってくるよういわれたことも数え切れないほどだ。ある時は電話口で泣き、ある時は怒鳴り、私を自分のもとに連れ戻そうとしていた。
それが嫌で、実家を出てから少し経った頃、私はもう一度引っ越しをした。今度は母に住所を知られないようにだ。携帯電話の番号も変えた。そこまでやってようやく、母の干渉が一切ない日々を私は手に入れた。
数年後。区役所から掛かってきた電話で母が死んだことを知った。ずいぶん進んだ状態の癌が数ヶ月前に発見され、それからはもう、あっという間に死んでしまったそうだ。急なことだったので、葬儀のことはぼんやりとしか記憶に残っていない。参列者の数はとても少なかった。
母が死んだ翌年、勤め先の上司だった男性と私は結婚した。その二年後に娘が誕生して、私も親になった。母親になる際、自分も母と同じ違えを犯すのではないかという心配も少しあったのだが、部下たちに対して面倒見よく接する夫の働きぶりをずっと眺めていたら、少なくともこの人は良い父親になってくれるだろうと思えたので、不安はだいぶ薄れた。
「ねえママ。あたしの髪の毛結ってよ」と娘が言ってきたのはつい数週間前だ。通っている幼稚園で三つ編みが流行っていて、自分も同じようにしてほしいという。娘を鏡台の前に座らせた時。私は自分の指が固くなるのが分かった。髪を結う、という行為に関連付け、母のことを思い出さずに居ることができなかったからだ。けれどいざ、娘の柔らかい髪に指を通ていると、不穏な思いはすぐに解けて、どこかに流れていった。娘の繊細な温度とか匂いは、思いもよらず私を穏やかな気分にした。
母の墓に供えた線香から、煙がまっすぐ登る。気温が高いせいで、私の額には汗が滲んでいる。視線を落とすと足元には娘が居て、大きな瞳で私を見詰めてくる。
ねえお母さん、と、墓石を前にして私は考える。私にとってあなたは全然、良い親ではなかった。今の私はあなたのことをあまり好きではないし、もっと長生きしてくれれば良かったとも思うことができない。けれどあなたが私のことを愛していたことだけは、たったそれだけなら理解することが出来る。望ましい形の愛ではなかったけど、愛されていたことだけは、それは分かってあげる。だから私はたった一回だけ、自分の娘に嘘を吐こうと思う。決してあなたのためだけではないけど。
「ねえママ。あたしのおばあちゃんはどんなひとだったの?」と尋ねてきた五歳の娘に向けて、私はひとつ息を吐いてから、優しい人だったよ、と短い言葉で答えた。すると娘はパッと顔を輝かせて「会ってみたかったなぁ」と白い歯を見せた。
正午が近づくにつれ日差しがいっそう強くなってきた。その一方で風は少し強く、入道雲も徐々に近くに来ている。ポケットの中でスマートフォンが震える。雨が降り出す前にお家に帰りましょうと、私は娘の手を引き、墓石に背中を向けた。

あとがき
タイトルはOASISの”Don’t Look Back In Anger”より。モデルになってくださった方から「あの曲のような読後感で書いて欲しい」とリクエストを貰って、書かせていただきました。
2018/11/12/辺川 銀