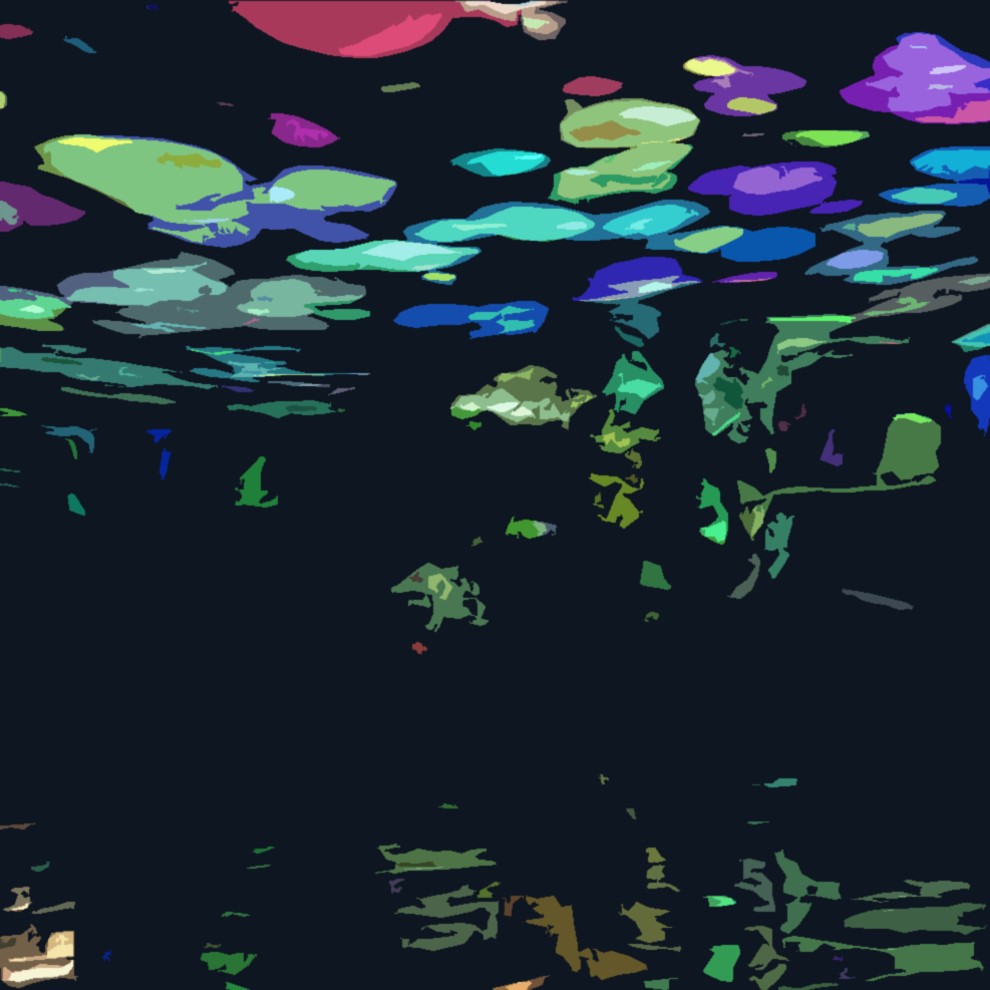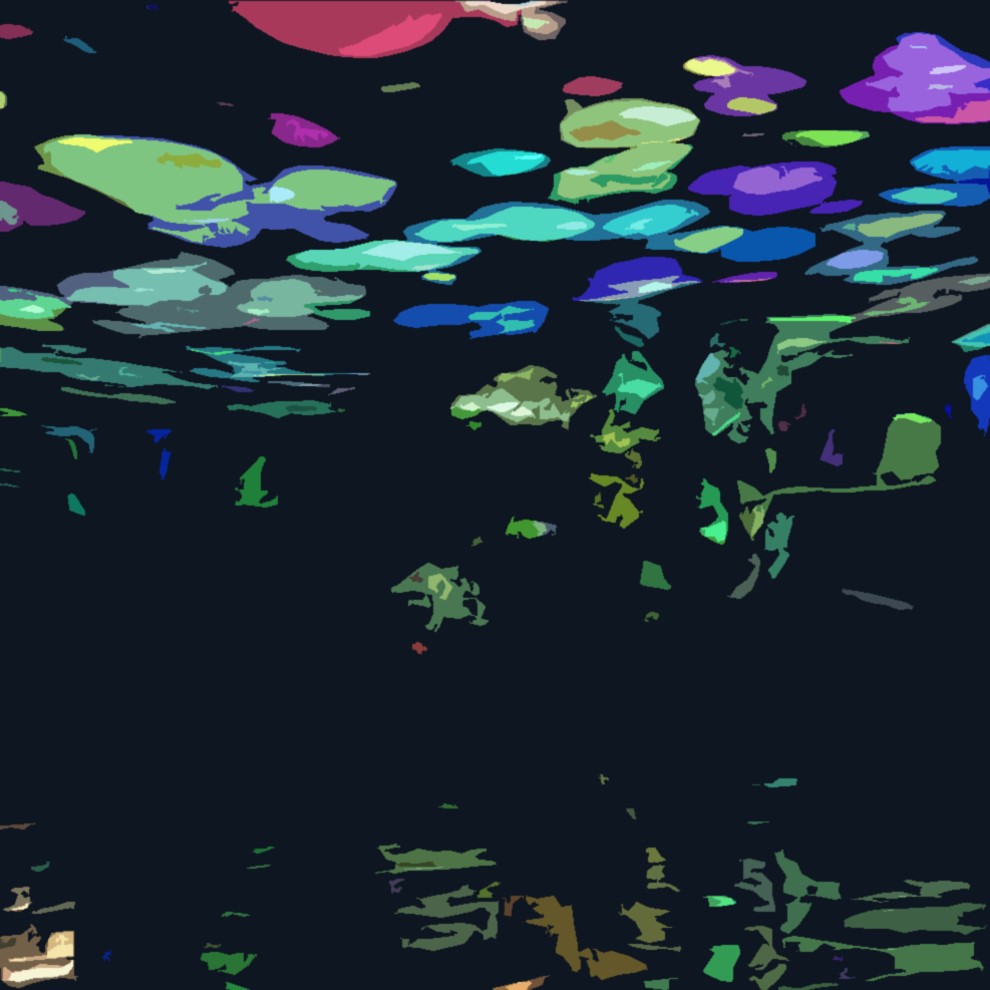
高校時代の文理選択で文系を選んでからというもの理系の勉強なんて全くやった覚えのないわたしの目から見ても科学の進歩は目まぐるしく見える。五年前とか十年前と比較しても世の中はたいへん便利になりひとが自殺をするのもずいぶん簡単になった。数年前に発売されて”ラムネ菓子”という通称で呼ばれているその薬は就寝前に一錠を服薬することで幸福感を伴う穏やかな眠気と共に一切の痛みや苦しさを感じさせることなく心臓を止めてくれるし、そのあと四時間半ほどの時間を掛けて残った遺体をさらさらの砂に変えてくれるから腐乱などによって醜い姿をこの世に残す心配さえも要らない。一昔前の自殺志願者というのは先ず最初に死のうと心に決め、次にはどのような死に方をするのがいちばん苦痛が少ないだろうかということに頭を悩ませたものだが、現在では少なくとも苦痛の少ない死に方を求めて彼らが死に方を模索するということはすっかりなくなった。”ラムネ菓子”は今や全国のドラッグストアの棚に陳列されておりバファリンや正露丸を買うのと同じぐらい簡単に手に入れることが出来る。
先日行った同窓会で十五年振りに再開したトヨダ君は学生の頃わたしに対して恋をしていたのだと酒を飲みながら語った。そしてそれは彼にとっての初恋だったそうだ。三十二歳の誕生日を来月に控えたわたしの容貌に対してトヨダ君は「自分はこれまで学生時代の初恋をずいぶん美化していたのではないかという疑問が今日ここに来るまではあったのだけど今のあなたは僕の記憶にある姿よりもいっそう綺麗に見える」のだと評した。「それはこの店の照明が薄暗いせいだと思うわ」と答えながらわたしは当時のトヨダ君がどんな姿かたちをしていたのか思い出そうと試みたが上手くいかなかった。誰もが名前を知っている自動車メーカーに勤めているのだというトヨダ君は平均的な三十二歳の男性と比較して髪の生え際が高い位置にあったが、左手の薬指には指輪が光っており赤ん坊を抱く女性の写真をスマートフォンの待ち受け画面にしていた。にもかかわらず「今日の同窓会に来たいちばんの理由はあなたの顔をひと目でも良いから見たかったからなんだよ」とトヨダ君は言った。
トヨダ君の初恋の対象になっていたのだという十代後半の頃の私は死にたがりの高校生だった。自分はいつどのように死ぬべきかということを毎日のように考えては妄想にふけるような少女だった。家族との仲は良く友人も居たし日々の生活に何か不満があったわけではなかった。ずいぶん昔のことなので正確に覚えているわけではないのだけど当時のわたしが抱いていた死にたいという気持ちは恐らく悲観から来ていたものではなく、あの年頃の少年少女にありがちな、例えば卒業後は地元を出て東京に行きたいとか日本では見つけることの出来ない自分を探すために海外留学をしたいだとか誰か好きな相手がいるわけではないが試しに処女を捨ててみたいだとか好奇心から煙草を吸ってみたいだとかいう感情と同じような、自分の日常の少し遠くにあるものに対する漠然とした憧れの一種だったような気がする。当時好んで見聴きした小説や音楽や絵画の作者はみんな自殺した人物だったし彼らの生き方を美しいと感じていた。
同窓会から帰る電車は空いておりわたしは狭いボックスシートにトヨダ君と向かい合って座った。がたんがたんと電車が揺れるせいで互いの膝が何度か軽く当たった。「あのさトヨダ君」月は出ておらず車窓から見える景色といえば遠くの方に民家の灯りがかすかに見えるだけで酷く暗かった。「もしもわたしがこの後トヨダ君と寝ても構わないって言ったとしたらどうする?」その一秒後にトヨダ君はぽかんと小さく口を開いたが更に二秒後には「そんなつもりはないくせに」と言って不敵にニヤけたのでわたしもつられて笑った。スピーカーから流れるアナウンスが次に停車する駅の名前を告げた。これはこの数時間を一緒に過ごす中で発見したことだがトヨダ君という人物はびっくりするほどわたしについて詳しい。わたしは未だに高校時代のトヨダ君がどんな顔をしていたのかを思い出せないというのに。次の駅が近づき電車は徐々に速度を落としていく。「当時のあなたに恋をしていた気持ちは今でもすごく鮮明に思い出すことが出来るし、それを思い出すと今の自分があの頃からどれくらい遠くに来たのかをいつでも確かめられる。だからこれから先も、例えば家族のことが愛おしくて仕方がない時なんかに、あなたのことを思い出すことがきっとあると思う。今日は会えて良かった」電車は停車してトヨダ君は立ち上がった。扉が開くと少し冷たい外の空気が車内に流れ込んだ。わたしも会えて良かったなと思う。電車を降りたトヨダ君はその場で一度だけ振り返って軽く手を振ったが、ドアが閉まるより先に改札の方へと歩き出していった。それからドアが閉まった。
終着駅で駅員に声を掛けられて目を覚ました。促されるままにホームに降りてから自分が居眠りしていたことを認識した。それほど多く飲んだつもりはなかったが軽い頭痛があるので自覚している以上にアルコールが回っているのかもしれない。改札を出るとすぐ目の前にはドラッグストアの黄色い看板が煌々と光っていた。わたしはまるで蛍光灯に引き寄せられる夏の虫のように自動ドアをくぐった。頭痛薬や整腸剤といった薬が並べられている棚の端っこには”ラムネ菓子”のパッケージも陳列されており、わたしは先程のトヨダ君との会話を思い返しながらそれを手に取った。十代の頃のわたしは死にたがりだったが最後に死にたいと考えていたのはいつ頃だっただろうか。正確な時期を思い出すことは出来ないが恐らくこの”ラムネ菓子”が世の中に出回った時期よりは前だったのだと思う。それをきちんと、きちんと確かめてから、”ラムネ菓子”のパッケージを陳列棚の元あった場所に戻すと、その横にある冷蔵ショーケースの中から二日酔い対策のドリンク剤をひとつだけ掴んで、レジの方へと向かった。