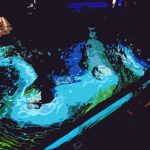午後三時。あたしは電車に乗った。電車の中は冷房が効いていた。ひんやりと涼しかった。向かいの窓から強い日差しが差した。シートに腰掛けると、赤いランドセルから虫の図鑑を出した。小学校の図書室から借りてきた図鑑だ。あたしは虫が好きなのだ。蝶々も蛾も同じように好きだ。テントウ虫やゴガネ虫も好きだ。カミキリ虫とかハサミ虫も好きだ。セミやトンボも好きだ。虫の身体は綺麗だ。ゼンマイ仕掛けの玩具みたいに、理屈に適った動きをするのが素敵だ。
そろそろ夏が来る。小学校に入学する前は夏が好きだった。何故なら夏は、一年の中でいちばん虫が多い季節だからだ。パパと一緒に車に乗って、ホタルを見に行ったり、カブト虫を取りに行くことが、すごく楽しみだった。だけど今では、夏が来るたびに悲しい気分になる。何故なら夏は、パパが死んだことを思い出す季節だからだ。あたしのパパは、あたしが小学校に入学した年の夏に、電車に轢かれて死んだ。仕事が忙しくて、くたびれていたので、駅のホームでうっかり転んで、線路の上に落ちてしまったらしい。
電車が進むにしたがって、車両の中は徐々に混んできた。窓の外には背の高いビルがすらりと並んでいる。乗り込んでからに十分ほどが過ぎると、あたしの家の最寄りの駅で、電車は停車した。ドアがプシュゥと音を立てて開いた。何人かの乗客が電車を降りて行った。だけどあたしはシートを立たなかった。ホームのスピーカーから音楽が流れて、それが鳴りやむと、ドアはプシュゥと音を立てて閉まった。電車はあたしを乗せたまま、再び走り出した。
あたしのママはとても厳しいひとだ。パパが死んでからいっそう厳しくなった。毎日の門限は四時と決まっている。だからあたしは他の子みたいに、放課後の時間を、遊んですごせない。五時から六時までの一時間は、通信教育の問題集を解かなければいけない。それとは別に週に二日は塾に行かなければいけない。見たいテレビ番組はテストで良い点を取った時にしか見せてもらえない。甘いお菓子は週に一度しか食べることが出来ない。クラスメートと比べても、自分は割と不自由な子どもなんだと感じる。中でもいちばん辛いのは、虫取りに行くのを禁止されていることだ。女の子が虫を好んだりするのは変なことなのだと、ママはあたしに、ことあるごとに言うのだ。
だけどあたしは、昨日まで一度も、ママからの言いつけを破ったことはなかった。何故ならママの口にすることを全て正しいと信じていたからだ。大人は子どもより正しいことを言うと、あたしはこれまで、疑いもせずに信じてきたからだ。
家の最寄りの駅を過ぎると、電車は橋を通り、大きな川を渡った。川を渡った先では、背の高い建物が急に少なくなり、その代わりに、木々や畑が多く目についた。カブト虫が取れそうな雑木林があった。水を張った田んぼにはアメンボだって住んでいるだろう。空は綺麗に見えた。遠くの方に入道雲があった。あたしは昆虫図鑑を閉じてランドセルの中に仕舞った。
安全のためにと持たされている、子ども用の携帯電話を取り出し、時間を確かめた。門限の四時を既に過ぎている。門限を破るのは生まれてはじめてだから、あたしの胸は酷くそわそわした。あたしは携帯電話の電源をオフにすると、それもランドセルに仕舞った。
あたしがママを疑うことなどなかった。何故ならあたしは幼い子どもだからだ。ママはあたしの何倍も長く生きている大人のひとだからだ。大人は子どもよりも正しいことを言うと、昨日までのあたしは、そう考えていたのだ。だけど実際には、そんなことはなかった。
昨日の夕方。いつものようにあたしが帰宅すると、そこにはママだけではなく、見たことのない男のひとが居た。男のひとはあたしのママとずいぶん親しげだった。あたしのママはその男のひとを、あたしにとって新しい父親になるひとだと、笑顔で紹介した。あたしはそれをすごく嫌だと思った。間違えていると思った。ママは正しくないことを言っていると思った。死んでしまったパパのことを可哀想だと思った。
終点の駅に辿り着いた。聞いたことのない名前の駅だった。電車のドアがプシュゥと音を立てて開いた。乗客たちは電車を降りて改札口へと向かった。だけどあたしはそうすることが出来ない。あたしの持っている定期券では、ここから外に出ることは出来ない。お金もそんなに多くは持っていない。
仕方がないので車両から出てホームのベンチに座った。ホームの時計は五時半を示していた。空はまだ明るくて綺麗に晴れていた。死期の迫ったセミたちの鳴く声が聞こえた。向こう側には青い海が見えた。太陽の光を映してきらきら光っていた。
乗って来た電車はホームに停まったままだ。行先を示す方向幕の表示が変っていた。この電車は二十分後に再び発射する。来た方向へと戻る。あたしはそれに乗って、家に帰るだろう。あたしは子どもだから、これ以上遠くまで逃げていくことは出来ない。あたしはベンチを立った。
ママがどんなに正しくないひとでも、あたしは家に帰らなければいけない。あたしが門限を守らなかったので、ママは恐らくあたしを叱るだろう。だけどあたしはママに向かって、謝りもせず、何食わぬ顔でただいまと言うのだ。あたしに出来ることなんて、せいぜいそれくらいだ。