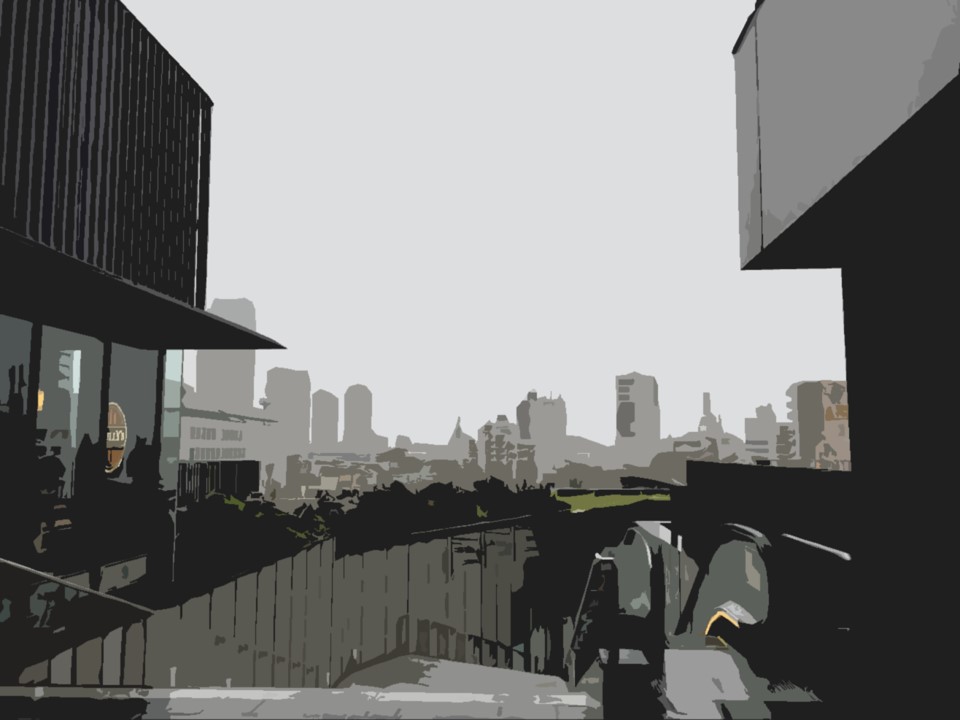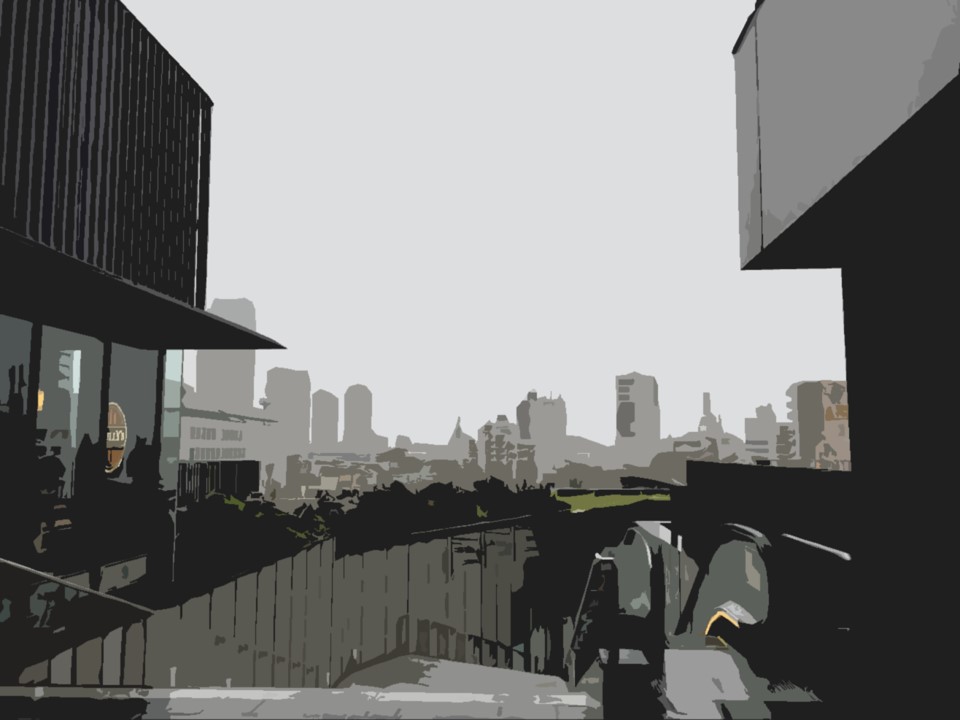煮付けにした鰈のお腹には細かな卵がぎっしり詰まっていた。煮付けになった鰈の身体をわたしが器に盛り付けていると、その最中に夫は帰宅した。出来上がった夕飯をテーブルの上にふたりで並べるとわたしたちはふたりで向かい合って座り、両手を合わせていただきますと言った。
—
父はわたしを男手ひとつで育てた。母は居なかった。母が居ない理由についてわたしは父から聞かされたことがなかった。父は恐ろしかった。わたしがお風呂に長く浸かっていたり休日だからといって遅くまで眠っていたりすれば火のように怒った。通知表に悪いことが書かれていた時には頬に張り手をもらった。
中でもとりわけわたしが怯えたのは食事の時間だった。父に言わせるとわたしは箸の使い方があまり上手ではなかった。正しくない箸の使い方で食べ物を口に運ぶことは許されておらず、作法を少しでも違えればわたしの箸は父の手によってはたき落とされた。同じ間違えを何度も繰り返した末に「今日の食事は抜きだ」と言い渡されたことも一度や二度ではなかった。
中学校の卒業式を済ませた日にの夜にわたしは家出をした。当事交際していた大人の男の部屋に転がり込んで暮らした。その男は、父の厳しさにうんざりしていたわたしの目にとても優しく映った。長く入浴しても、たくさん眠っても、男はわたしを怒鳴りはしなかった。食事の時に細心の注意をはらう必要もなかった。
男の部屋はいつも散らかっていた。雑誌や服や、作りかけのプラモデルや、誰かからもらった贈り物の包装紙が、フローリングの床の上にいつも散乱しており、男やわたしはいつもそれらを踏みつけながら部屋の中を歩いた。いま思い返すとあの男は、自分の持ち物を大切にすることが出来ないひとだった。男はある時わたしにこう言った。「別の女がここに来るから出ていって欲しい」と。
それでもわたしは家に帰らなかった。父のもとには戻りたくなかったので様々な男の家を転々として過ごした。そんな生活はやがてわたしが仕事に就き、自分だけの部屋を借りるまで続いた。
わたしと父は病室で再会した。家出をしてから七年経っていた。七年ぶりに会った父はもう喋ることができなくなっていた。身体のあちこちにチューブや電極を繋がれ、機械によって命だけを保たせていた。枯れ木のように身体は痩せて肌がくすんでいた。再会を果たしてから、わたしは週末ごとに父を見舞ったが、父はいちども目覚めることはなかった。わたしが長く眠りすぎた日、このひとは、わたしが泣いて謝るまで、怒鳴り散らしたというのに。機械のスイッチをこの手で止めてやろうか。そんな衝動にわたしは何度も駆られた。
父は死んだ。再会してからひとつも言葉を交わさないまま死んだ。遺産はすこしあったが、遺言などはなかった。わたしは悲しまなかった。涙も出なかった。だからといって嬉しいわけでもなかった。どのような感情を抱くのが適切なのかよく分からなかった。父の葬式は雨の日に行われた。参列者の数は少なくはなかった。
「君のお父さんは、会う度に君の話ばかりしていた」
「あなたについての自慢話を、何度も聞かされた。自分に似ず賢い、自慢の娘だと」
あのひとは自分の娘を深く愛していたと、参列者たちは口を揃えて言った。
だけどそれを聞いても、わたしは父から褒められたり、優しくされた時のことなど、ひとつも思い出すことができなかった。
—
夫と出会ったのは父が死んでから数年経ってからだ。とても美しく箸を扱うひとだなというのが、夫に対する最初の印象だった。そして夫の方も、わたしの箸使いを見て、綺麗だと褒めてくれた。わたしの箸の使い方を褒めてくれたひとは、父も含めて、夫がはじめてだった。わたしは今でも父のことが嫌いだ。けれど父から教えられたこの箸使いを、褒めてくれるひとの伴侶になれたことは、良かった、と思う。
煮付けにした鰈のお腹には細かな卵がぎっしり詰まっていた。わたしはそれを箸で口に運び、丁寧に噛み潰した。無数の卵は口の中で、何かを訴えかけるようにぷちぷちと弾けた。わたしの向かい側で同じものを食べている夫は、「おいしい」と静かに言い、わたしに笑いかけた。わたしも笑い返した。