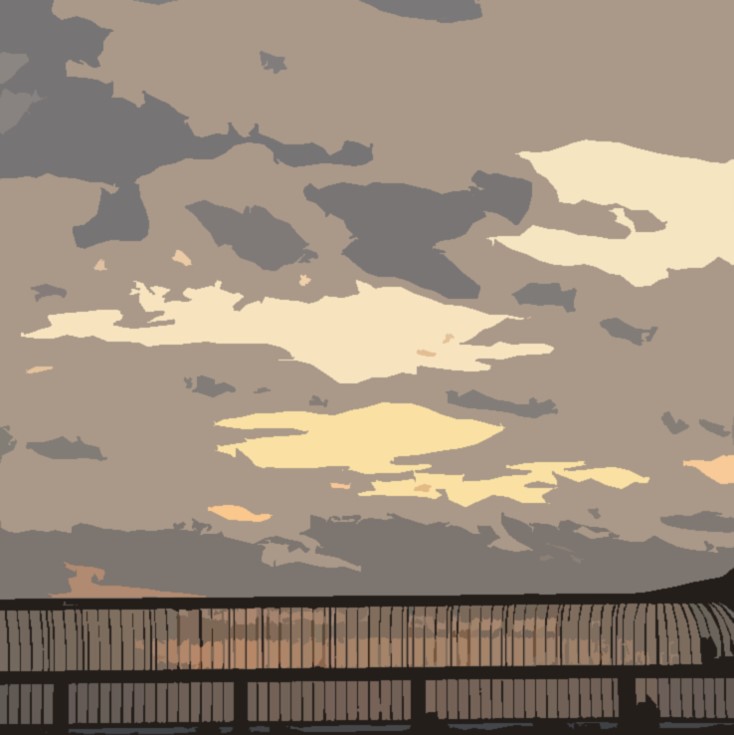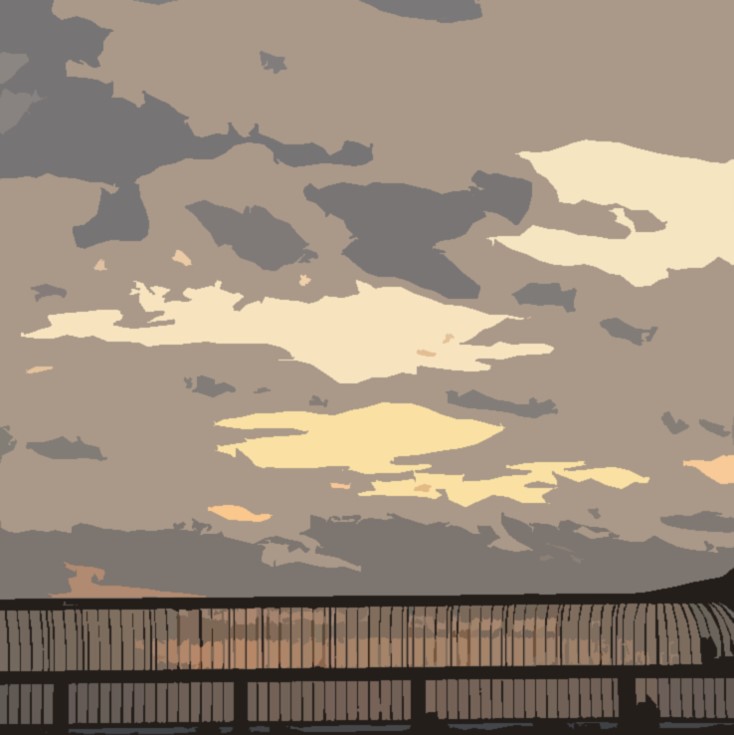鼻の先に、雨の粒がぶつかる、冷たい感触で、わたしは目を覚ました。身体を起こして、辺りを見回すと、自分がまったく、見知らぬ場所に居るということに気付いた。ちょうど小学校のグラウンドと、同じぐらいの広さで、地面は赤茶色の、カーボンのような素材で舗装されている。所々にへこんだ箇所があるのか、小さな水溜りが幾つも出来ていた。四方には、十メートルはあろうかという、巨大な塀に囲まれており、扉や門は、どこにも見当たらない。あたしの腰には、ずっしりと重たいポーチが巻かれていたが、やはりこれも、はじめて見るものだ。ファスナーを開けると、中には四角いチョコレートが、ぎっしりと詰まっていた。
中心部には、まるで水銀の滴を、そのまま巨大にしたような、三メートルほどの物体が、ひとつ置かれていた。しばらく眺めていると、それがどうやら、生き物らしいことに気付いた。少しずつ動いている。スライム状の身体を、ぬらりぬらりと伸縮させながら、分速一メートル程度の、非常にゆっくりとした速度で、こちらに迫って来るのだ。どうして自分がこんなところにいるのか、さっぱり分からない。しかしあの水銀のような生物に触れることが、非常に危険だというのは、すぐに理解した。おそらく少し触っただけでも、あっという間に死んでしまうだろう。
とにかく何とかして、ここから脱出しなければいけない。四方を囲んでいる高い塀に沿って歩きながら、出口を探し始めた。塀をよじ登るのは無理そうだが、きっとどこかに出口があるはずだ。途中でお腹が減ったので、ポーチの中からチョコレートをひとつ取り出して齧った。水銀生物はゆっくり迫って来る。明かにわたしを追って来ているけど、動きは非常に遅いから、距離をきちんと取っている分には、捕まることはないし、捕まらなければ別に危険はない。じっくりと冷静に探して、出口を見つけ出せれば、きっと無事に外に出られる筈だ。しかしどんなに探しても、この場所からの出口が、見つかることはなかった。
わたしがこの場所に来てから、一週間が過ぎた。この一週間、雨はほんの僅かな時間も降り止むことがなく、今日も降っている。あまり眠っていないので、わたしはなんだか、頭がぼうっとする。水銀生物は、今日も変わらず、わたしを追ってくる。水銀生物は、分速一メートル程度の、非常にゆっくりとした速度でしか移動できないので、起きている分には容易に逃げられるが、わたしが眠っている時や、休んでいる時でも、同じ速度で追いかけ続けてくるので、とても恐ろしい。この場所は、ちょうど小学校のグラウンドほどの広さだけしかない。充分な距離を取ってから、瞼を閉じたとしても、三時間眠れば、百八十メートルも距離を詰められる。今のところはまだ逃げ延びているけど、もしも気を抜いて、寝過ぎてしまったら、それがわたしの最期の時だろう。
ポーチの中から、チョコレートをひとつ取り出して、三分の一だけ齧って、ポーチの中に戻した。このチョコレートが、わたしにとって唯一の食糧だ。しかしそれも、既に残りが少ない。諦めてしまうことをわたしは考え始めた。ここから脱出することは、どうやら不可能みたいだし、だったらいつかは必ず、あの水銀生物に捕まり、死んでしまうのだ。いつかは必ず捕まるんだったら、こうして逃げ続けることに、一体何の意味があるんだろうか。今日を生き長らえたって、明日もどうせ、寝不足で、お腹を空かせて、あの水銀から逃げまどうだけの時間が、待っているだけだ。
十日目。目を覚ますと、水銀生物がすぐ目の前に居た。どうやら少し、長く寝過ぎたようだ。今日もいつも通りに、振り続いている雨は、水銀生物の身体の表面にもぶつかり、小さな波紋を無数に描いていた。逃げなければと、わたしは考えたが、身体が動かなかった。すごく眠いので、もういちど、このまま目を閉じ、眠ってしまおうと思った。おそらく二度と、目覚めることはないだろうけど、大したことではない。逃げ回る時間が、ほんのちょっぴり、短くなるだけだ。瞼がすとんと落ちる。
けれど次の瞬間、わたしは再び目を開けて、空を見上げていた。この十日間、途切れることなく降り続けていた雨が、突然止んだからだ。雲が途切れて、そのあいだから、白金色に光る太陽が、ほんの数秒覗いだ。わたしの視界は涙でじんわり滲んだ。久しぶりに見る太陽は、わたしがこれまで目にした、他のどんなものより、優しく美しかった。すぐにまた、空は雲に覆われ、雨が降り出した。わたしは立ち上がり、一目散に走って、水銀生物から、なんとか距離を置いた。
十五日目。今日もやっぱり雨が降っている。ポーチの中のチョコレートもあと数日で、いよいよ底をつく。チョコレートがなくなったら、そこから先は一切何も食べずに、水銀生物から逃げる生活を続けなければいけない。果たして何日、生き延びられるだろうか。分かっているのは、最後には間違いなく、あいつに捕まって死んでしまうという、たったひとつのことだ。しかしそんなことは、もうどうだって構わないと、わたしは考えて、雲に覆われた灰色の空を見上げた。死ぬ前に、あの美しい太陽を、あと一度でも良いから見てやると、わたしは決めている。いつかは死ぬと分かっているけれど、太陽を見るまで、わたしは逃げ続けたい。