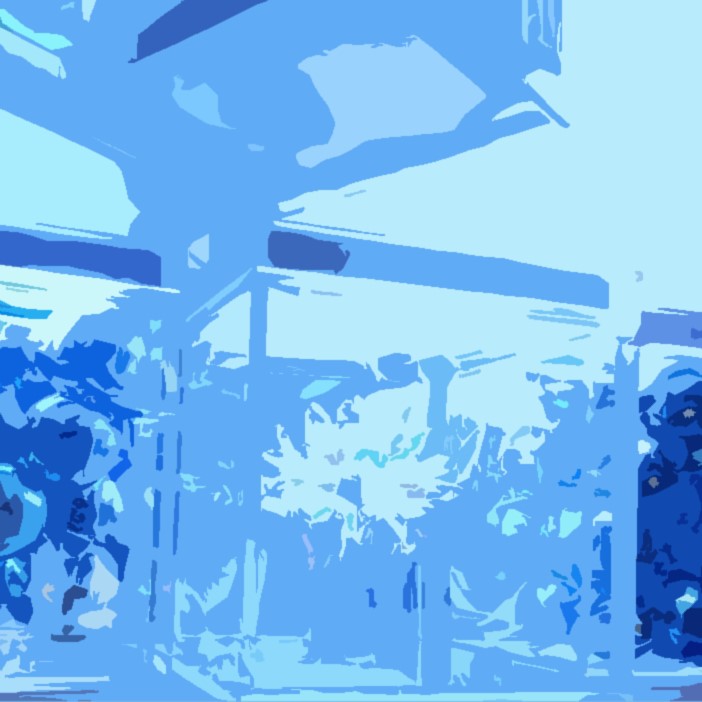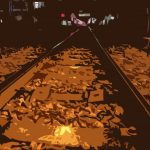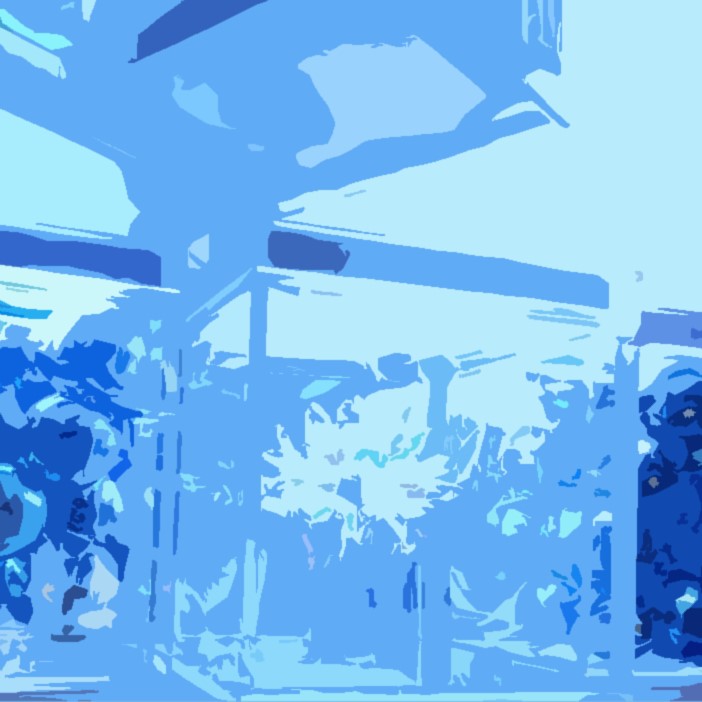
ラクダに乗ってやって来た赤毛の行商人が、空のように青い葉をした小さい鉢植えの植物を買わないかと勧めてきたので、ひとつ購入した。なんでも北西の遠い国にだけ生える珍しい植物なのだという。だが購入してから一週間もしないうちに植物は元気を失い弱り始めてしまった。指よりも細い幹は乾いてヒビが割れ空色の葉っぱも曇ったように色がくすんでしまった。疑問に思い調べてみると、この植物はどうやら熱さと乾燥にとても弱いらしい。私はあの赤毛の行商人の顔を頭に思い浮かべ、そんな植物をこの砂漠の真ん中で売るなどどういうつもりだろうと憤ったのだけれども、今更腹を立てたところで既に後の祭りだ。冷凍箱の中から氷を五つ取り出し、植物の根元に転がすように置いた。砂漠の中で氷は貴重なものだし、数時間もすれば溶けてしまうだろうが、こうして毎日氷をくれてやればこの植物も少しは元気を取り戻してくれるかもしれない。
私の身体はもう朽ち始めている。まだ若く妻も存命でこの辺りにも町があって医者が暮らしていた頃、私は左腕を失ってアルミの義手を付けたが、義手は長い年月を経て数年前からついに錆びはじめたのだ。錆は義手から骨へ筋肉へと伝わり今ではもう私の身体全体に広がってしまった。もう数年も持たないだろうしその辺で転びでもすればきっと簡単に崩れてしまうだろう。一緒に暮らしている一人娘は慎ましい性格をしているので献身的に私の身の回りの世話をしてくれるし、錆の成分が皮膚に浮き上がれば錆取りを染み込ませた布を使い綺麗に拭き取ってくれるのだが、きっと本音では疲れているのだろう。親の欲目だが器量も悪くないし、もしも私の身体がこんなふうでさえなければ、さっさと都会に出て良い旦那など見つけて幸せに暮らすことだって出来るはずなのだ。
植物は日に日に弱り続けていき、空色だった葉の数もだんだん減っていったのだが、私は毎朝欠かすことなく氷を与え続けた。ある朝起きると右手の感覚がなくなりほとんど動かなくなってしまったのだけど、それでも義手の左手を使い、力加減に気を付けながら氷を掴んで植物の根元に与えた。起き上がるのも億劫なほど暑かったり、私の体調そのものがあまり良くない時などもあったが、氷箱から氷を取り出し植物に与える作業だけは決して娘に任せることなく、自分の手で続けた。今の私は娘に生かされているのだ。この枯れかけた植物ひとつ生かしてやることが出来ずに、娘に生かされる資格などないように思えたのだ。
ある時、娘は私の前に跪き啜り泣き始めた。どうしたのかと尋ねると、娘は、この砂漠を出て都会で暮らしたいと答えた。若い時間をこの砂漠の中で終えてしまうのは辛いと、消え入るような力のない声でこぼした。構わない。と、私は娘に言った。私は自分のために娘が人生の一部をふいにすることなど望んでいないからだ。娘は三日三晩悩んだ後、荷物をまとめて出ていく支度を始めた。最後の日に、娘は私の身体を、錆取りを染み込ませた布を使いこれでまででいちばん丁寧に念入りに拭って、綺麗にしてくれた。幸せになりなさいと、私は、口に出さずに思った。
娘が出て行き数週間が過ぎると、私は間もなく自分の身体が崩れて朽ち果てるだろうということが分かった。もう暑さも感じることはないし、膝も腰も、思うように動かすことがすっかり出来なくなってしまった。悲鳴を上げる身体を、唯一動く左手の義手で支えて、氷箱の中から氷を取り出すと、私は床を這うようにして植物の鉢植えの方へ向かった。そうして氷を植物の根元に、転がすようにして与えた。植物に氷を与えることができるのも、たぶん、今日が最後だろう。見ると、植物は花を咲かせていた。花はまるで夕焼けのような真っ赤な色をしていた。私の身体はもう、少しも動かなかったが、良かったと思った。おそらく明日にはすべてが終わるだろう。これでさようならだ。