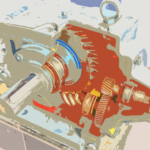その駅で電車を降りたのは私だけだった。重たく熱い八月の外気に晒されると全身の皮膚はあっという間に湿り気を帯びて私を不快にした。汗で濡れた自分の前髪が額に鬱陶しくまとわりつくのも嫌だ。改札を出てもひとの気配はなく強い陽射しと無数の蝉の鳴き声ばかりが周囲を満たしており遠くを見れば恐竜の背骨を思わせるぎざぎざした稜線が山々の緑色と空の青色とを別けて隔てている。駅舎の影のベンチに腰を下ろそうとすると足もとに落ちている蝉の躰を見つけた。屈み込んでよく見てみるとその蝉にはまだ息があり六本の細い脚を力なく動かそうとしていた。突然鳴いて暴れることもあるので瀕死の蝉を嫌うひとは多いが私は特に虫に対する苦手意識はない。数日前には「夏休みの自由研究は蝉の観察をやりたい」という小学二年の息子とふたりで公園に行き蝉の抜け殻を幾つも集めて歩いた。
私が彼女と知り合ったのは中学生の頃だ。彼女は私が過去に出会った誰よりも美しい造形をしていた。小さな頭やすらりとした身体つきは同じ人間のそれとは思えずより上等な生きものであるかのようだったし完璧といえるほどに整ったその顔を眺めれば同姓ながらに胸が高鳴った。にもかかわらず彼女はいつも自分自身を粗末に扱った。地元でいちばん大きな工場の経営者を父に持ち金銭的には困るはずなどないのにその美しい躰を幾度となく大人たちに売った。売った相手は男もいれば女もおり父親の工場の従業員だとか学校の関係者も複数いたのだという。耳や舌には常に幾つかのピアスが着いていたが装飾ではなく自分の躰に穴を開けること自体を目的にしている様子だった。白い肌には火傷やあざや切り傷などが絶えることなくあった。そんな彼女をよく思わず「頭がおかしい」というひとも少なくなかったが私はそれでも彼女が好きだった。なぜなら彼女が美しかったからだ。
ひとの気配がない駅舎の影で私はひとり屈みながら地面に落ちた瀕死の蝉を見つめた。六本の脚はまだ微かに動いているが鳴いたり飛んだりしだす気配はない。地上に出てから一週間しか生きることのない蝉は短命で儚い生きものの代名詞のように言われることが多いが実際にはその逆だと私は思っている。土の中で六年も生きている時点で昆虫としては長寿の部類に入るし、加えて一生のうちの最も良い時期をいちばん最後の一週間にまで取っておけるのだから人生の大半を緩やかな衰えに苛まれて過ごす人間と比べてもある意味では素晴らしい生き様なのではないか。鞄の中でスマートフォンが振動する音が聞こえたので取り出して確認すると家にいる夫から「今日は夕飯どうする?」とメッセージが届いていた。私は食べて帰るので息子とふたりで済ませておいてほしいと返信をしてからスマートフォンを鞄の中に戻し再び地面に視線を落とすと蝉はもう少しも動くことがなかった。
私と彼女は中学から高校までを同じ学校に通った。この六年間で私は彼女に対しもっと自分を大切にしてほしいだとか自分に粗末にするような真似をしないでほしいなどといったことを何度も何度も伝えた。だけれど彼女は私の言葉を聞き入れることはなかった。それどころか私の心配をあざ笑うかのように自ら傷つき続けた。目の周りに昔の漫画のような青あざを作ったこともあったしどういうものを摂取したのか分からないがろれつの回らない状態で学校に来て授業中に突然倒れたことあった。何らかの理由で左耳の鼓膜が破れ何週間か聞こえない時期もあった。美しい彼女は歳を重ねるにつれおかしくなっていった。精巧に形造られた高級店のケーキがフォークの先で崩されていくみたいに。私は彼女のことが大好きだったのに。大好きだから傷ついてなどほしくはなかったのに。
蝉は死んだ。手を伸ばして動かなくなった蝉の身体に指先で触れてみたが何の反応もなかった。近づいてくるエンジンの音に気づき私は顔を上げた。やってきた銀色の乗用車は駅舎の前に停まった。運転席の窓を開けて姿を見せた彼女は私の記憶にある姿よりもさらに痩せており長い首には包帯が捲かれていた。「ひさしぶり」と笑顔で発するその声も空気が抜ける音のようでほとんどちからがなかった。喉を壊して上手く喋れないということは会う約束をした時点で伝えられていたから私は驚かなかった。彼女の半袖から伸びる腕や手の甲は相も変わらず傷だらけだったし促されて助手席に乗り込むと煙草の匂いがした。自分を大事にするつもりなど未だにないのだろう。しかしそれでもこうして再会できたことが私はとても嬉しい。大好きだから傷ついてほしくないとあの頃の私は思っていたのだが、どれだけ傷ついても大好きなことに変わりはないのだなと今の私は思う。
彼女が車のハンドルを握ると私は死んだ蝉のことを思った。帰りにここを通る時まであの亡骸は残っているだろうか。あるいは蟻とか鳥につつかれ跡形もなく壊れているだろうか。

あとがき
そりゃあもちろん大切なひとには健康で幸せな道を行ってほしいのだけれど、それでも彼ら自身が選んで歩む道と、僕らが彼らに望んでしまう道というのはやっぱり、大なり小なり違っているわけです。
2019/08/22/辺川銀