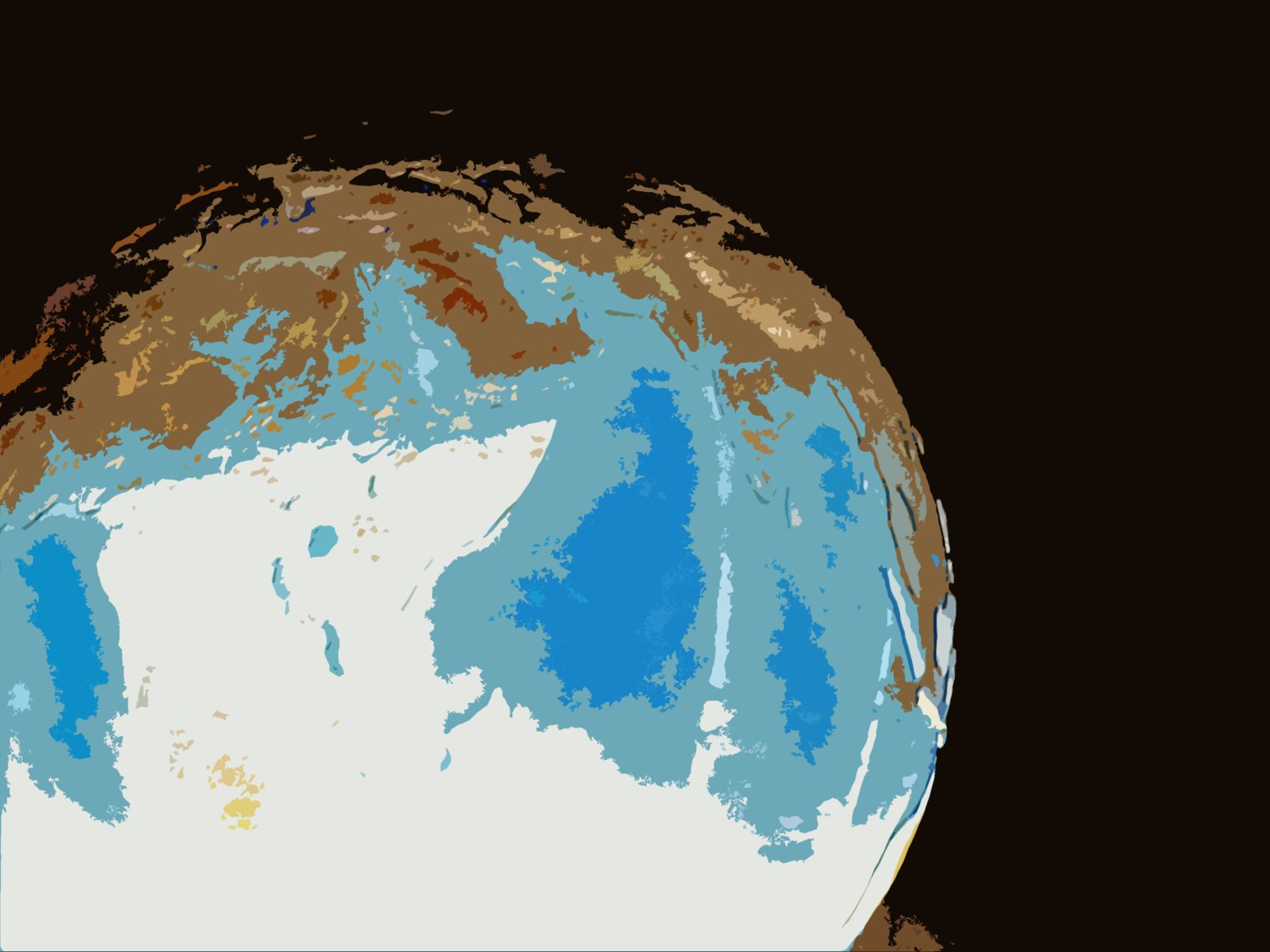開け放した窓の外から鈴虫の鳴く声が聞こえる。自宅のリビングで夫とわたしはテレビを眺めながらお酒を飲み交わす。結婚してから今年で十年経つが子どもはいないしおそらく今後も産まないだろうと思う。ニュース番組のアナウンサーは宇宙の彼方に地球そっくりの青い星が見つかったと話す。光の速度で移動できてもたどり着くまでには数千年かかるほど遠くの星ではあるが水も空気も存在しており今の時点で生き物が住んでいる可能性さえあるということだった。近所の商店街で買ってきたからあげを食べながら夫はぽつりという。「おれ実は子どもの頃、宇宙飛行士になりたかったんだよ」
わたしが生まれ育った山奥の土地には素晴らしく美しい空があり夜になれば無数の星々がまるで大都会の摩天楼から見下ろす夜景のようにきらきらと瞬いてみえたが一方の地上には書店や飲食店はおろかコンビニさえなかったのでわたしにとってはただただ狭くて退屈な場所でしかなかった。おもてを歩けば姿を見るのは噂話と陰口が大好きな年寄ばかりで地域にひとつしかなかった自動販売機がいつの間にか撤去されていたときにはああこの土地に未来はないんだろうなと確信したものだ。中学校はわたしが通っていた三年のあいだに全校生徒の人数が五人を超えた時期がいちどもなくその中に自分以外の女の子がいたこともなかった。
そんなどうしようもない土地に彼がやってきたのはわたしが中学二年生だった年の夏のこと。わたしと同い年だという彼は「家庭の事情」により夏休みのあいだだけ自宅のあるトーキョウを離れて親戚である寺の住職のもとで過ごした。その期間中わたしと彼は毎日のように顔を合わせていた。彼は会うたびにトーキョウの話をわたしに聞かせてくれた。甘くカラフルなスイーツのお店が何軒もずらりと立ち並ぶ通り。星々のすべてを空から剥がして地上に散りばめたかのような明るい夜。ありとあらゆる書物が集まる巨大な図書館。県外にさえ出たことのなかったわたしには彼の口から語られる何もかもが魅力的に感じられた。
当時わたしと同じ中学に通っていた三人の男子たちは彼に対して「都会ぶっていて気に入らない」「女みたいなやつ」「俺たちのこと田舎者だって馬鹿にしてやがる」などと言いあまり良くは思っていない様子だった。確かに彼はあの土地で育った男子たちとは違い肌の色は白く身体つきもほっそりとしていたし常に柔らかい物腰で喋ったがそういった部分がわたしの目には弱々しさではなく上品で洗練されたものとして映った。何より二次性徴を経て丸みを帯びつつあったわたしの外見に対して好奇の目を向けたり馬鹿にしたり不自然に遠ざけたりしないところが良かった。
わたしたちは決まって彼が滞在する寺の境内で会った。彼が語るトーキョウの話はいつも良いところで終わった。ちょうど明日も聞きたいと思わせるようなところで「今日はここまで。続きはまた明日」と切り上げるのだった。そんな彼にわたしはいちどだけ文句を口にした。わたしはもっとたくさん聞きたいのにどうしてそんなに小出しに話すのだと。すると彼は「僕がトーキョウに帰る日まで毎日聞きに来てほしいからだよ」と微笑みながら言うのだった。「もちものぜんぶを一度に見せてしまえば君はもう僕に興味をなくしてしまうかもしれない。そうなることが怖いから、今日はここまで、続きはまた明日」
夏休みを終えると彼は当初の予定通りトーキョウに帰っていきそれから二度と会うことはなかった。わたしは彼が帰ってからしばらくのあいだ寂しい思いをしたが秋が過ぎ寒くなる頃には思い出すこともあまりなくなった。翌々年の春に中学校を卒業したわたしは生まれ育った土地から離れたい一心だけで県外の学校に進学した。そして高校一年生の時に初めてのセックスを経験した。相手はアルバイト先のひとつ年上の先輩。先輩の方から声をかけてくれたことがきっかけでわたしは恋をした。気にかけてもらえたことが嬉しかったわたしはもっと相手の気持ちを引くために求められるものをすべて差し出してしまった。同性の友人の約束よりも先輩からの誘いを優先したしお金も貸したし身体だって許した。だけど最初のセックスをした次の日から先輩はわたしに対して一切の興味を向けなくなってしまった。虚しさと哀しさと混乱の中でわたしはいつかの夏にトーキョウからやってきた彼の言葉を久方ぶりに思い出したのだった。「もちものぜんぶを一度に見せてしまえば君はもう僕に興味をなくしてしまうかもしれない」
「おれ実は子どもの頃、宇宙飛行士になりたかったんだよ」夫は近所の商店街で買ってきた大ぶりの唐揚げを口に運びながらぽつりとそう言った。職場で知り合い結婚してから十年もの時間を同じ屋根の下で過ごしてきた夫だが子どもの頃の夢について話すのはこれが初めてだった。夫にまつわる小さな新発見にわたしは今日も安心感を覚える。たとえ死ぬまで添い遂げたところでこのひとのすべてを知り尽くすことなどきっとできないだろう。テレビ画面の向こう側では背中の丸い天文学者が数千光年先に浮かぶ地球によく似た星について説明する中で「そうはいっても宇宙のことは一生かけて研究してもわからないことの方がずっと多いのです」と楽しそうに語った。

あとがき
「わたしは誰にも理解されたくない、だけど興味は持たれていたい」という話を聞きました。すべてを理解されてしまえば、その後はまるで読み終えた本のように興味をなくされてしまうからと。
とはいえひとの一生は、幸か不幸か、ひとりの他者を完全に理解できるほど長くないのでしょう。
2020/10/22/辺川銀