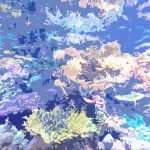きのう友だちがまたひとり死んだ。その亡骸は僕が最初に見つけた。白い砂浜で朝の日差しを浴び海の方を向いて立った姿勢のまま彼は死んでいた。そっと手で触れると彼の身体は乾いた砂糖菓子のようにぼろぼろと崩れ落ちた。身体の内側がすっかり錆びて駄目になっていた。彼が死んだことを僕は少しだけ寂しいと思った。だけど泣くほど悲しくはなかった。この島で誰かが死ぬことはもう少しも珍しいことではない。
晴れている日であれば岬に建つ古い灯台の展望デッキに彼女はいつも居る。彼女は現在この島にいる唯一の人間だ。たいてい何かの本を読みながらベンチに腰掛けている。海の方から吹いてくる強い風に長い黒髪をばさばさなびかせながら。この島に吹く風は鉄を錆びさせる粒子を多く含んでおり僕らの身体を毎日じわじわと蝕み続けているが、生身の身体を持つ彼女には特に影響を及ぼさない様子だ。
「私はこの場所でひとを待っている」展望デッキで過ごす理由について彼女はそう話す。「この場所で待っていれば、あのひとは私は迎えに来てくれる。ここで再会する約束をしている。だから私はここで待っているの」この話を彼女は何度も、何度も、幸せそうな笑顔を浮かべながら僕に聞かせてくれる。だけど彼女が灯台に姿を現してから十年以上が既に過ぎていし、そのくちもとに刻まれる笑い皺もずいぶん深くなった。
鉄を錆びさせる風がこの島に吹き始めたのは、彼女が現れるより、僕が生まれるより、もっと以前のことだ。その昔この島には人間を始めとする生身の生き物だけが住んでいたのだけど、いつの頃からか僕らのような機械の身体を持ったひとびとも暮らすようになった。人間は新しいものを考え出すことがとても得意だったし、彼らが考えたものを形にしていく際には機械の身体が必要不可欠だった。なので両者は良い関係を築きながら長い年月を共に生活した。だけど人間たちはある時いっせいに島から姿を消し、それと同時期に鉄を錆びさせる粒子が、海からの風に乗ってこの島に押し寄せるようになった。
風が吹き始めた日よりも後に生まれた僕らが見てきたのは、だからこの島が、この島での暮らしが、段々と錆付き、腐って駄目になり、終わりに向かっていく、その過程ばかりだ。明日が今日より良くなることはないし、その次の日はもっと悪くなる。僕と同年代の、若い仲間はみんな経験でそれを知っている。今日よりも良い明日が来ることはないから、生きて明日を迎えることも嬉しいことではない。生きていることが嬉しいことではないから、死ぬことも別に悪いことではなく、友だちが死んでも少し寂しいだけで、涙を流して悲しんだりはしない。
今日も彼女は展望デッキで本を読んだ。何度か読書を中断して紅茶やお菓子を嗜んだ。灯台の中には人間のための保存食や本がたくさん残されていたので彼女が飢えて死んだり、生きているうちにすべての本を読み終えてしまうということは起こりそうになかった。やがて日が暮れて文字が読めないほど暗くなると彼女は本を閉じた。あなたの待ち人は今日も来なかったと僕が言うと、「そうだね」と彼女は、だけど満足げに、くちもとに皺を刻み、微笑んでそう答えた。
あなたはどうして。たまらず僕は尋ねた。あなたはどうしてそんなに楽しそうに待ち続けることができる? あなたはもう、とても長いこと待ち続けているのに。あなたの待ちびとはこの先、何年待っても、何十年待っても、たとえあなたが死ぬまで待ったって来ないかもしれないのに!
彼女の表情は、それでも変わらなかった。笑みを静かに浮かべたまま「待つのが好きなのよ」と、彼女は僕に答えた。「私は待つのが好き。こうして本を読み、紅茶を飲み、季節ごとに変わっていく景色を眺めながら、あのひとを待つ生活を豊かなことだと思う。そして時々やって来るあなたのようなお客さんと話しながら過ごす時間だって幸せだと感じる。あのひとを待ち続ける時間そのものを私は愛しているの。だから本当は、あのひとが来るか来ないかというのも、そんなに重要ではないのよ」
次の日になると仲間がまた死んだ。他の仲間たちは誰も泣かなかった。僕も泣かなかった。岬の灯台を目指して歩いていると自分の腰のあたりから鈍い音が聞こえた。灯台のエレベーターを使い展望デッキにたどり着いたがそこにはもう彼女の姿はなかった。彼女がいつも座っていたベンチには一冊の本に挟まれた短い手紙があった。「急ですが、発つことになりました。今までありがとう」と書かれていた。
天気はとても良く風は強かった。その場で立ち尽くして、昨日までここに居た彼女のことを思った。彼女は待ちびとにきちんと会えたのだろうか。もしもそうなら喜ばしいことのはずだが、僕の気持ちはどうして沈むのだろうか。それからこの島と僕らの行く末を思った。この島はもう終わりが見えているし、仲間たちは遠くないうちにみんな死ぬだろうし、僕も同じく死ぬのを待つだけだ。
ふと思い立って、手紙が挟まれていた本を僕は手に取った。それはずっしりとした重みのある分厚い本だった。おそらく手紙が風に飛ばされることのないよう重しとしてここに置かれていたのだろう。僕はその本の最初のページをめくった。そこに書かれていた文字を読んでいった。ひとつのページを読み終えると、次のページを読んだ。気づけば彼女がそうしていたように、日が暮れるまで本を読み進めていた。