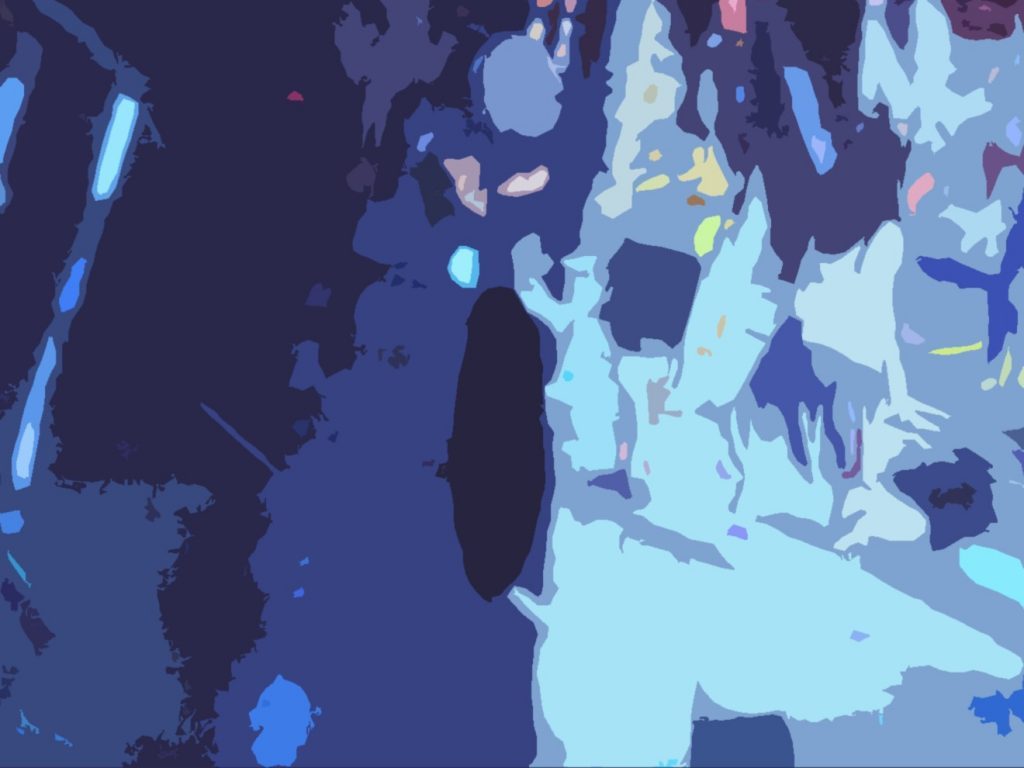定期試験の最中なので教室の中は非常に静かだった。僕は今回の定期試験に向けて事前の勉強をしっかりしてきた。なので一限目の英語と二限目の物理はそれなりの手ごたえがあったが、この三限の火星史の試験は難しい問題が多くて、なかなか解くことが出来ない。僕たちは火星で暮らしている。僕らのように火星で暮らしている子どもは、ほとんどみんな地球で親に捨てられて連れて来られた子どもだ。大人になるまでの教育と生活を保障される代わりに、火星開発計画の実験体として生きなければならないのだ。天井付近で機械が静かに稼働する音が聞こえる。通気口から教室の中に酸素が供給される音だ。隣の席のエステルは早々に問題を解き終えた様子で、窓の外に広がる薄桃色の空を見ていた。エステルはクラスでいちばん頭の良い生徒だ。その一方で身体はあまり丈夫ではないから、体育の授業はしょっちゅう見学している。真っ赤な赤毛は短く刈っているが、それでも時折、女性に見紛うほど、華奢で繊細な容姿をしている。
試験が終わると僕はエステルと一緒に、彼の秘密のガレージへと出向いた。エステルのガレージはリニアの列車が通っていない、交通の便が悪いところにある。ニンゲンが降り立って間もない頃に使われ、廃墟になっていた研究施設を彼が発見して、ガレージとして再利用しているのだ。ガレージに行くには、いちど寮に戻ってから宇宙服に着替えて、キャタピラで走るバイクに乗って向かわなくてはいけない。ガレージの中でエステルは宇宙船を作っている。この建物を始めに見溶けた時に内部に残っていた、様々な機械を器用に組み合わせ、地球へ向かうための宇宙船を内緒で作っている。宇宙船の制作はもちろん難しいことだが、エステルになら可能だ。しかし許可なく宇宙船を作ることは火星の法律によって厳しく禁止されているので、もしも警察にこのことがばれたら、きっとエステルは捕まり、罰せられるだろう。
「それでもぼくは地球に行きたいんだ」
そばかすのある色の白い頬をピンク色に紅潮させ、興奮気味にエステルは僕に話した。宇宙船はあと数日で完成するらしい。
僕たちは火星で暮らしている。私たち火星で暮らしている子どもは、ほとんどみんな幼い頃に地球で親に捨てられ、連れてこられた子どもで、僕もその中のひとりだ。だから多くの子どもは、自分がかつて地球に居たころのことを少しも覚えていない。しかし僕はほんの僅かだけど、地球に居たころのことを覚えている。誰にも話したことはないけど、少し覚えている。
あの時の僕は二本の足で歩けるようになったばかりだった。母親に連れられ、水族館に出掛けた。水槽に囲まれた青いトンネルを歩いて、そこで泳ぎ回る、色とりどりの魚たちの姿を眺めた。青白いクラゲたちが泳ぎ回る水槽の前で、母は立ち止った。すぐに戻るから、ほんの数分、その場で待っているようにと、膝をかがめて、僕に向かって言った。僕は頷き、母を見送った。
僕が母親の姿を見たのはそれが最後だった。母親が迎えに来なかったので僕は迷子として保護され、手続きを経てから、火星に送り込まれた。誰にも話したことはないけど、地球は酷いところだということを、僕は覚えている。
授業が終わると僕はエステルと一緒に、彼の秘密のガレージへと出向いた。いちど寮に戻ってから宇宙服に着替えて、キャタピラで走るバイクに乗って向かった。この日のエステルはとても興奮していた。作っていた宇宙船がようやく完成したからだ。昨夜のうちに荷物も積み終えたので、今日これからすぐ、地球へ旅立つらしい。完成した宇宙船は、ただちに飛び立てるようガレージの外に置かれており、鈍い銀色に光る球の形をしていた。
エステルが宇宙船に乗り込み、扉を閉めようとした時、遠くの方からサイレンの音が聞こえた。サイレンの音がこちらに近づいて来ることに気付くと、エステルの顔からサッと血の気が引いた。警察がキャタピラのバイクに乗ってやって来る音だ。僕が通報したんだ。青ざめたエステルに向かって、僕は静かに言った。地球は嘘吐きばかりの、とても酷いところだ。あんなところに行って欲しくはない。
だが彼が動揺したのは、ほんの一瞬だった。
「それでもぼくは地球に行きたいんだ」
エステルはすぐに落ち着きを取り戻して、それから穏やかに笑った。
「ぼくは君のことを好きだったし、そして今でも好きだ。どうかお元気で」
そう言って彼が扉をぱたんと閉じると、宇宙船は間もなく、音も立てずに、垂直に浮き始めた。警察のバイクはサイレンを鳴らしながら間もなくたどり着いたが、彼の宇宙船がもう届かないところまで登ってしまう方が、僅かに早かった。
午後は火星史の授業だった。火星開発の歴史について、若い女の先生がホログラムの映像を用いながら僕らに説明した。僕の隣はエステルの席だが、彼が宇宙船で飛び立った日を最後に、ずっと空席だ。昨日も空席だったし、明日も空席だろう。天井付近で機械が静かに稼働する音が聞こえる。通気口から教室の中に酸素が供給される音だ。僕は机に頬杖をつき、窓の外に広がる薄桃色の空を眺めた。エステルは果たして地球に着けたのだろうか。仮に辿り着けたところで、幸せになれる保証なんて、どこにも少しもない。