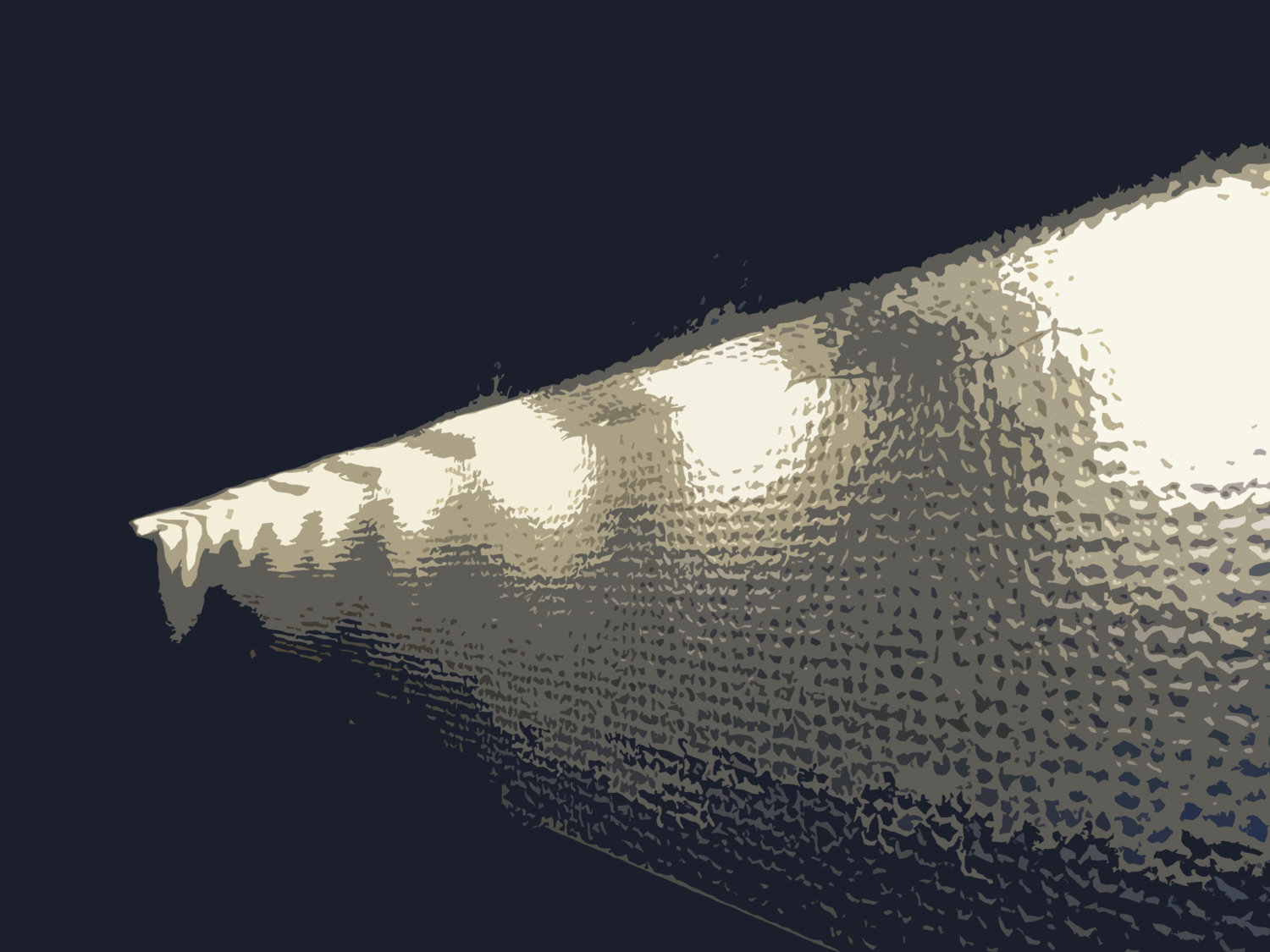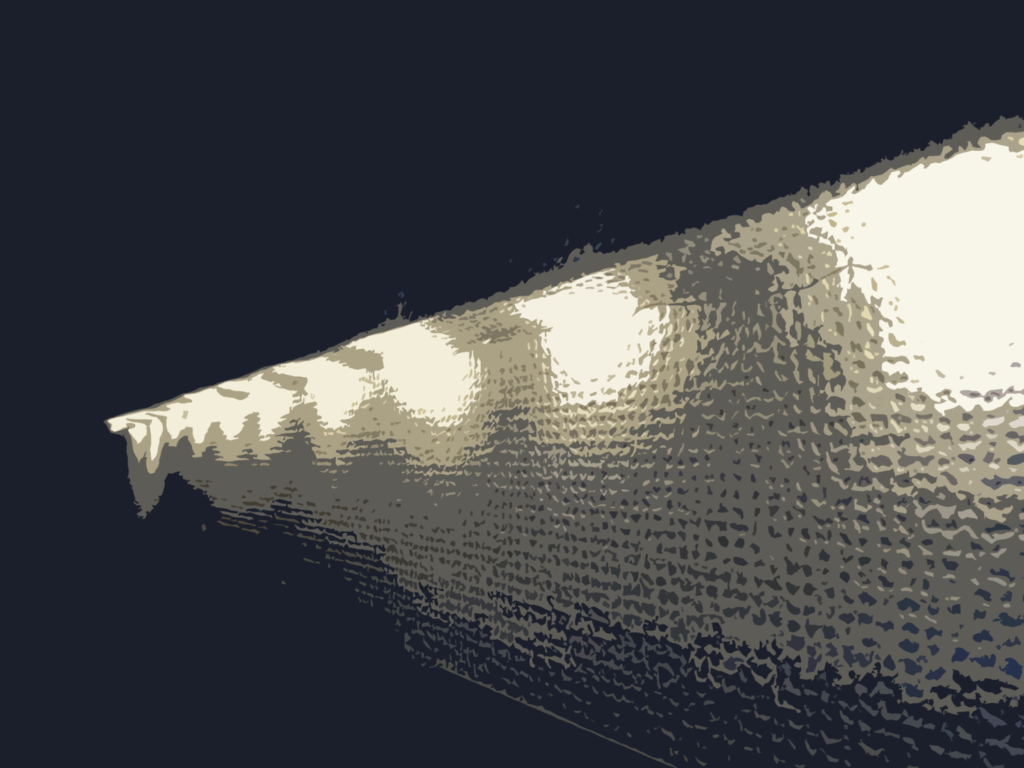
寝静まった夜の街をたったひとりで歩くことが日課だ。夜の街は好きだ。表通りにひとの姿がなくなるから好きだ。噂話を気にすることなく道の真ん中を歩けるから好きだ。だけど今夜は普段と違っていた。駅前の広場には立ち尽くしているふたりの子どもがいた。ふたりはどうやら兄妹のようで兄は見たところ十二、三歳ぐらいか。妹の方はまだ十歳にもなっていないだろう。こんな時間にどうしたのかとわたしは話しかけた。なんでも酒に酔った父親が家で暴れるので逃げてきたという。「父が暴れるのは毎度のことなんだ。だけれど今日は初めて僕だけでなく妹まで叩いた。それでたまらず家を出てきたんだ」
十年前の冬晴れの朝。わたしたちの街に悪魔が訪ねてきた。そのときわたしは十四歳だった。悪魔は痩せていて背の高い壮年の男だった。上品な黒いコートに身を包んでおり頭には山羊のような角を生やしていた。「みなさんはじめまして。みなさんのうちのひとりに悪魔のちからを少しだけ与えました」悪魔は街に住む全員を駅前の広場に集めるとそう語り始めた。「与えたのは他者の寿命を奪うちからです」語られた内容は怖ろしいものだったが騒ぐ素振りを見せるひとは誰もいなかった。悪魔の口ぶりがとても穏やかで優しげだったからだ。「もちろん悪魔のちからですから代償はあります」冷たい風が強く吹いていて悪魔のコートはばさばさなびいていた。「引き換えに、ちからを与えられたひとが本来もっていた寿命は残り一日だけになりました。つまりちからを与えられたひとは、今日のうちに誰かの寿命を奪わなければ死んでしまうのです」
わたしはそのようにして悪魔のちからを得た。もちろんわたしが望んだわけではない。知らないうちに与えられていた。どうしてわたしに与えられたのかはさっぱりわからない。悪魔のちからが与えられたあの日のわたしにはふたつの道があった。ひとつは誰かの寿命を奪って生きながらえる道。もうひとつは誰の寿命も奪うことなく命を落とす道だ。わたしは前者を選んだ。死にたくなかったし深く悩んでいる時間もなかったからだ。最初に寿命を奪った相手は広場でたまたま近くにいあわせたお爺さんだった。わたしはそのお爺さんのことを少しも知らなかったが高級そうな腕時計を手首に着けていたのできっと裕福な人生を送ってきだろうと勝手に想像した。悪魔のちからを行使して七日間だけ奪った。ちからの使い方はとても簡単だった。心の中で念じるだけで良かった。周囲のひとに悟られることなく奪うことができた。
最初に奪った七日間のうち四日目までは自分の部屋からほとんど出ることなく幾度も泣いて過ごした。悪魔のちからが与えられたことやその代償に寿命を奪われたことに対する動揺もあったが、それ以上にわたしを揺さぶったのは寿命を奪う相手としてあの見ず知らずのお爺さんを選んだことだった。既に長く生きた老人からであれば少しぐらい奪っても許されるだろうと咄嗟に思ってしまった。裕福そうな相手からなら奪ったときの罪悪感が少なく済むだろうと考えてしまった。いくら一日しか猶予がなかったとはいえ寿命を減らされる人物と減らされない人物を選別する権利などわたしにあるはずがなかった。それでも五日目にはやはり死にたくないという恐怖が再び勝るようになり外出をしてまた別の相手から七日間を奪った。
二度目以降。わたしは寿命を奪う際のルールを幾つか決めた。寿命を奪うのは週にいちどとすること。一回で奪う寿命は七日間とすること。奪う相手の選別はせず決めた曜日の外出で最初に見かけた人物から奪うこと。ただしその人物が過去に奪ったことのある相手だった場合は次以降に見かけた人物に順次見送って同じ人物から二度以上は奪わないこと。以上のルールに基づき、少しずつ、少しずつ、わたしはひとびとの寿命を奪いながら過ごした。
わたしが悪魔のちからを持っていることは誰にも知られていない。悪魔はこの街を訪れた際、この街に悪魔のちからの持ち主がいるということだけを広く伝えたが、それがわたしだということは十年経った今に至るまで公になっていない。だけど悪魔のちからの持ち主が与えられたその日に死ぬことを選ばず、他者の寿命を奪って生き延びたのだという事実はみんなが知っている。なぜなら悪魔が訪ねてきた翌日にこの街では誰も死ななかったからだ。悪魔のちからを与えられた人物は本来の寿命を残り一日だけにされてしまったので、その人物が死ななかったということはすなわち、誰かの寿命が奪われたということなのだとみんなは理解した。悪魔のちからを与えられたその人物のことをひとびとは悪魔の子と呼んだ。
ひとびとは悪魔の子を忌み嫌った。「自分もいつのまにか寿命を奪われているかもしれない」「家族の寿命を奪わないで欲しい」「ひとの寿命を奪わずに死ぬことだって選べたはずなのに。そうしなかったのは酷く自分勝手だ」「悪魔の子は自分のことしか考えていない。悪魔のちからを与えられたものはやはり心まで悪魔になっているのだ」「誰だか分からないが早く死んで欲しい」そんな会話が街のいたるところで毎日交わされた。悪魔のちからに頼らなくても生きていけるひとたちによって。
また七日間誰かの寿命を奪って生きる道。あるいは奪わず命を落とす道。そんな分かれ道に毎週直面した。そのたびにわたしは奪って生きていく道を選択を続けた。回数を重ねても寿命を奪うことはやはり苦痛だった。繰り返すことで慣れた部分もあったが、こんな行為に慣れていく自分に気づくといっそうの自己嫌悪を覚えた。自分の心が悪魔のちからを得る前とは別のものに変質していくのが分かった。酷い道でも生きて歩み続けた先には良い出来事が待っているかもしれないという希望はほんの少しだけあり、とはいえ報われることなどなくただただ罪を重ねていくのだろうという諦念はもっと強くあった。それでも微かに希望がある限り、生きるのを辞めるという道をわたしは選べなかった。だから希望を最後まで探して、どんなに探しても見つからないことをきちんと確かめてから終わりにしたかったのだ。
寝静まった夜の街をたったひとりで歩くことが日課だ。だけれど今日は駅前の広場で悪い親から逃げてきた幼い兄妹に出会った。兄妹には今夜眠る場所がなかった。だからわたしは彼らを自宅に招待した。鍋に残っていた野菜のスープを温めて出すとふたりは喜んでそれを口にしていた。夜が明けたら電車に乗って遠くで暮らす母親のもとを訪ねるつもりだという。だがその母親も今は別の男性と家庭を持っており頼りになるかは分からないのだそうだ。もし何かあればまたここに来るようわたしは兄妹に伝えた。するとふたりは同じようにして表情を緩めた。「ありがとう。今夜あなたに会えて良かったです」
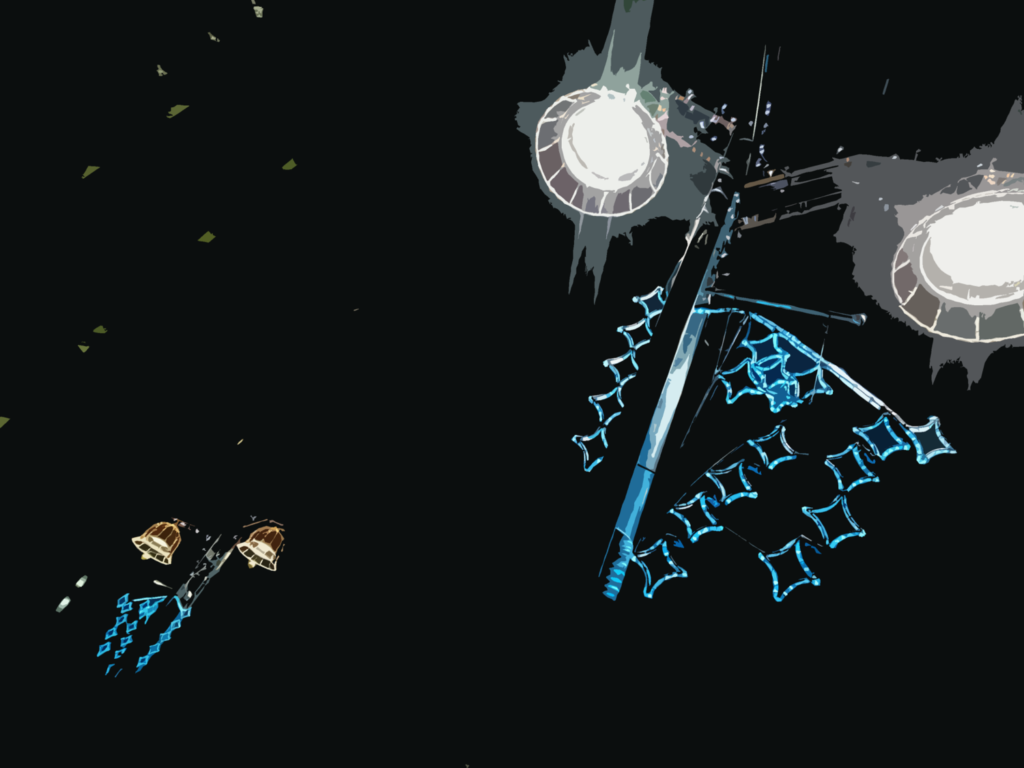
あとがき
「たぶん見つからないけど、もしかしたら見つかるかもしれない。だから探してしまう」そんな歩みは大抵徒労に終わってしまうのだけれど、徒労にもきっと意味はあるのでしょう。迷子を楽しめる人生は良い人生だなといつも思います。
2020/3/2/辺川銀