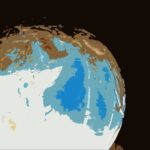冷たく強い風が吹く。巻き上げられたパウダースノーは次の瞬間ぶわぁと膨らみ太陽光できらきらと輝きながら凍った山の表面をまるで竜のように駆けて滑っていく。私は足元の雪をピッケルで突き刺しながら一歩ずつ一歩ずつ足跡を刻んで前へ進んでいく。気温は氷点下を下回っているはずだが身体はずっと熱を帯びている。目指す頂上は遥か遠くに見える。
神様が住むと信じられている雪山の麓に私の家がある。吹雪や雪崩が多い地域なので近所に他の建物があったことはない。どんなに立派な建設業者が新たな建物を作ろうと試みても完成前に雪で潰れてしまう。にもかかわらずどういうわけか私の家はいかなる雪にもいかなる風にも決して揺らがない。この家は私が生まれるよりもずっと昔からここに存在しており誰がいつ建てたのかは記録に残っていない。
だから私の家には神様を詣でに山を登る様々なひとびとが中継地点を求めて訪ねてくる。屋根は特別な塗料で塗り上げられているようで天気の良いときには深い黒色だが夜間や雪の深いときなどは七色に眩く輝いて旅人たちの道しるべにもなる。そのことから私の家はプリズムの家という名前でも呼ばれている。けっこう有名だ。
雪山に住むと信じられている神様には色々な言い伝えがある。暗闇だった宇宙に最初の光をもたらしたとか。盲目だった人間たちに視力を与えたとか。千里先まで見渡すことのできる目の持ち主だとか。ひとの心を見透かすことができるだとか。信じて祈れば失くしたものが見つかるとか。目の病気の予防や回復にご利益があるとか。
家の内装はとても変わっていて、多くのひとが来ているときにはそのぶん広くなり部屋の数も増えるが、あまり来ていないときには逆に狭くなり部屋の数も減る。私は生まれた時からずっとこの家に住んでいるがどういう仕組になっているのかは未だに分からない。そういうものだという事実だけを受け容れて暮らしている。
ひとびとが家のチャイムを鳴らしたとき私は彼らひとりひとりを適切な部屋に通さなければいけない。ひとりで来たひとなら小さめの部屋。ふたり以上できたひとなら大きめの部屋に。取材や営業に来るひとならば応接室に。気心の知れている人物であれば毎晩リビングで行う食事会に招待する。宿泊が必要なひとならば客間に。心を許した異性であれば最奥にある私の寝室に案内する。
どんなひとが訪ねてきた場合でも私は必ず彼らの話に耳を傾けた。彼らは年齢も出身地も生業もばらばらだったので何故この家を訊ねてきたのかとかどうして神様のもとを目指すのかと尋ねればいずれも違った答えが返ってきた。彼らの話を聞いて過ごす時間が私は嫌いではなかった。
私の家は様々なひとを招き入れる場所だ。だから家具や調度品は誰の目にも好ましく映るものだけが並んでいる。たとえ私が良いと思ったものでも、見るひとによっては不快に感じそうなものとか、好き嫌いが分かれそうなものであれば、もし手に入れたとしても家の中からひとりでに消えてしまい、どこを探しても見つからないのだった。たとえば干からびた多肉植物が植えられた鉢とか。底が抜けた空っぽの水槽とか。
あのひとが家のチャイムを鳴らした瞬間の驚きをはっきり覚えている。生まれてこのかたこの土地でくらしている私でさえ経験したことのない激しい吹雪が一週間以上も続いていた時期だったからだ。他の滞在者はひとりもいなかったし天気が落ち着くまでは誰も来ないだろうと私は思っていた。玄関のドアを開けて姿を見せたあのひと白いワイシャツにデニムのズボンを合わせただけというおおよそ寒冷地とは思えない格好をしていた。身体ほっそりとしておりその顔立ちは大人のようにも子どものようにも見えた。
「ここはずいぶん不思議な家ですね」とリビングで温かいシチューを食べながらあのひとは言ってくれた。私はあのひとを自分の寝室に通した。もう何日も自分以外の声を聞いていなかったからあのひとの来訪が嬉しかったのだ。だけれどあのひとは服を脱ぐこともベッドに横たわることもせず寝室の更に奥にある壁にそっと手のひらで触った。するとその壁は扉のように開いた。
私の家の最奥の寝室。その更に奥に開けたのは私自身も知らない秘密の部屋だった。そこには干からびた多肉植物が植えられた鉢があった。底が抜けた空っぽの水槽があった。熱が出た夜に見る夢を描いたかのような虹色の絵画が壁に飾ってあった。その部屋にあるのはかつて私が素敵だと思って手に入れたものばかりだった。それでいて誰にでも好かれるわけではないから家の中から消えたものばかりだった。
あのひとと私は何日ものあいだ秘密の部屋の中だけで過ごした。そのあいだあのひとは「この部屋はとても居心地よく感じる」と何度も私に言った。「ここにあるものはみんなあなたにきちんと愛されている。だから全部が素敵なものだと思う」と。何故この家に来てくれたんですか? と私が質問すると、「神様でいることに疲れてしまったから」とあのひとは笑った。
秘密の部屋を出てあのひとが家から去っていったのは半月以上続いた猛吹雪が止んだ朝のことだった。夜になると自分で寝室の壁に触れてみたが秘密の部屋への扉が開くことはなかった。以降も多くのひとびとが家を訪れた。たまに寝室に異性を招いたが秘密の部屋に到れるひとは他に現れなかった。秘密の部屋への扉はあのひとでなければ開けられないのだと私は理解した。
訪れるひとびとはみんな以前と同じようにこの家に来た理由や神様のもとを目指す理由を語ってくれたのだが私はもう彼らの話を面白いと感じることができなくなっていた。秘密の部屋の存在を知るより前の私であればひとりひとりのエピソードに対して心が動いていたのに。秘密の部屋を知ったせいでそれ以外のすべてが退屈になってしまったのだ。だがそれでも私は、あのひととふたりで秘密の部屋に行き、そこで過ごした時間を、ほんの少しも後悔していないのだった。
冷たく強い風が吹く。熱気を帯びた私の身体は凍った空気を肺の内で溶かしながら歩みを進めていく。この山に暮らす神様はあらゆるものを見渡す目を持つと信じられている。ひとの心を見通す目を持つと信じられている。今ここに立つ私の姿も見えているのだろうか。私の心も見ていてくれるのだろうか。雪上の足跡をひとつずつ増やしながら私は思いを馳せる。目指す頂上は遥か遠くに見える。

あとがき
このお話のモデルになってくださった方からコメントをいただきました。
ほんの一瞬の出来事が自分にとっての転機になることがあります。
その中にはとても強烈で、今までの自分の世界を大きく変えてしまうものもあります。
一度その出来事を経験したら、決してそれを知る前の自分に戻ることはできません。
そしてそれは、とても残酷なことかもしれない。
私は遥か高みの頂上にたどり着き、再びあのひとにめぐりあうのかもしれません。
高みにたどり着けず、無念のまま山を下りたり、ずっと退屈を感じながら生きるのかもしれません。
でも、あのひとと秘密の部屋で一緒に過ごした時間は、紛れもなく私の宝物で、
私の物語の続きを照らしてくれると信じています。