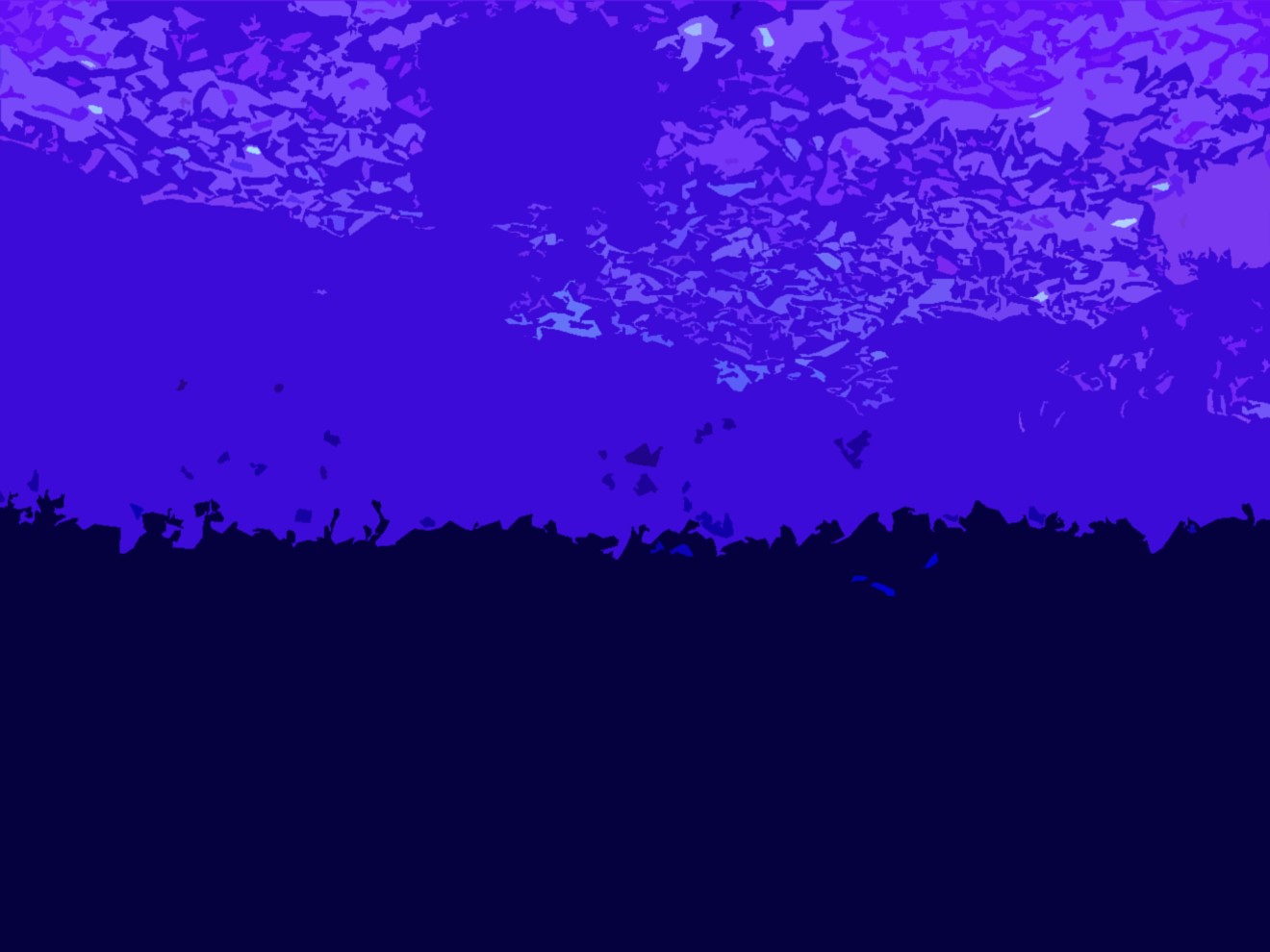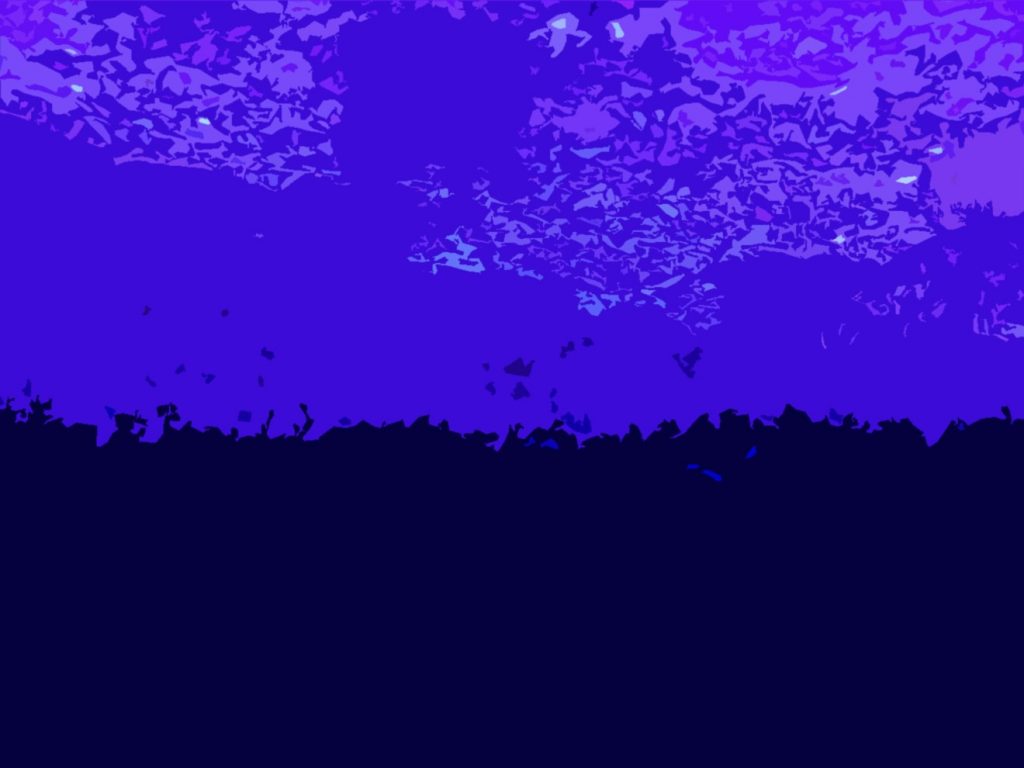暑さで目を覚ました。シャツの背中が汗で湿っている。気持ち悪い。
古いエアコンが大袈裟な音を立てて稼働しているけど送られてくる風はちっとも涼しくない。これだったらエアコンを止めて窓を明けたほうが涼しいような気がする。
わたしは上半身を起こした。隣には男が眠っている。男はわたしの恋人だけど二回り以上も歳が離れている。一緒に街を歩いたところでカップルではなく親子に見えるだろう。
男は全裸だった。一方のわたしはTシャツを着ているけど下半身には何も履いていない。男のことを起こさないよう注意を払いながらわたしはベッドを降りた。
舌が血の味を感じた。どうやら口の中を切っているみたいだ。身体のあちこちに鈍い痛みを感じる。
テーブルの上には煙草の箱がまるで積木のお城みたいに幾つも積んである。そして灰皿の中には無数の吸い殻が折れ重なっている。
初めて煙草を吸った日のことをわたしは覚えている。
場所はこの男の家。この部屋。吸った動機はごく単純だった。煙草も吸えない子どもだと思われるのが耐えられなかったからだ。そしてそれはわたしがこの男に処女をくれてやったのと同じ理由だった。初めて飲み込む煙草の煙は気体とは思えないぐらいずっしりと重たくわたしの内蔵にねばねばまとわりついた。わたしは不快感を感じた。それから激しくむせた。
男はわたしのそんな様子を見てけたけたと笑っていた。笑われたわたしは男のことを殺してやりたいと思った。
けれど二度目に吸った時には最初のような不快感がなかった。三度目の時は気持ち良いとさえ思った。そして四度目以降のことについてはあまり覚えていない。結局わたしは今まで何本の煙草を吸ったんだろうか。数える気にもならない。男とセックスした回数を一々数えてなどいないように。
ご多分に漏れずわたしは煙草をやめられなくなってしまった。やめようと思ったことがないわけではない。けれどいちど身体に染み付いてしまった喫煙習慣から脱するのはとても難しかった。ほんの数時間吸わずにいるだけでも苛立ちと不安を感じるようになった。半日以上吸わずにいようものなら指先が小刻みに震えだす始末だ。こんなふうにやめられなくなるなんて吸い始めた時には気づいていなかった。
わたしの身体には傷とか痣が多い。その多くはこの男の暴力によって作られたものだ。だけど幾つかの古傷は小さい頃に父親から殴られた時のものたちだ。身体を僅かに動かすだけで鈍い痛みが走る。
最近気づいたことだがこの男はわたしの父親に似ている。男は何かあるたびにわたしのことを殴る。喧嘩をした時はもちろん。気に入らないことがあるとき。そしてセックスをする時にもわたしを痛めつける。
最終的にわたしの父親はわたしを置いてどこかに消えてしまった。だからわたしは、父親にされたようにこの男か捨てられることを何より恐れていた。この男はわたしにとって何より有害だというのに。いつの間にか離れることが出来なくなっていた。ちょうど煙草をやめられない身体になっていたのと同じように。
それに気付いた時。ああ。本当に救いがないなと思いながら煙草を吸ったものだ。
だけどわたしは先月の半ばから煙草を吸っていない。妊娠したからだ。妊娠したことが分かるとわたしの心身は信じられないほどすんなりと煙草を手放した。誰に言われるまでもなくそうすることを選んだ。喫煙の習慣があった頃は煙草がなければ死んでしまうとまで思いながら過ごしていたというのに、いざ吸うことをやめてしまえば我慢することはそれほど苦ではなく、二週間も経った頃には吸いたいという気持ちそのものがまったく起きなくなった。自分はどうしてあんなものを好んで吸っていたのかと不思議に思うほどだ。
けれど何かを手放すというのは、やってみれば案外こんなものなのかもしれない。失ったら永遠に苦しむような気がしたってそれは錯覚だ。本当に苦しいのは手放すまでの間だけだ。ひとたびこの手を離れてしまったなら、手放した時点で苦しい時間は終わりだ。
大抵の物事はそんなものだろう。今はそう思う。
わたしは眠る男の顔を見た。愚かなこの男はわたしが煙草をやめていることにちっとも気づいていない。数時間前も何食わぬ顔でわたしに煙草を薦めた。そして断ったわたしの肩を強く殴ったのだ。だからわたしが妊娠していることだって当然知らないはずだ。もしもこの男が父親になったら、きっとわたしにするのと同じように子どもを殴るだろう。わたしの父親がそうであったように。
わたしは携帯電話と財布だけをズボンのポケットに仕舞った。そして玄関から家を出ると外から鍵を掛けた。郵便受けに鍵を放り込むと、自分の広角が自然に上がるのが分かった。
外は風があった。家の中よりも案の定涼しかった。まだ目立たないお腹をさすりながら、駅の方に向けてわたしは歩き出した。もう一時間も経てば始発が動き出す。
今のわたしならばどこまでだって行けるような気がする。何もかも失っても。