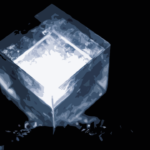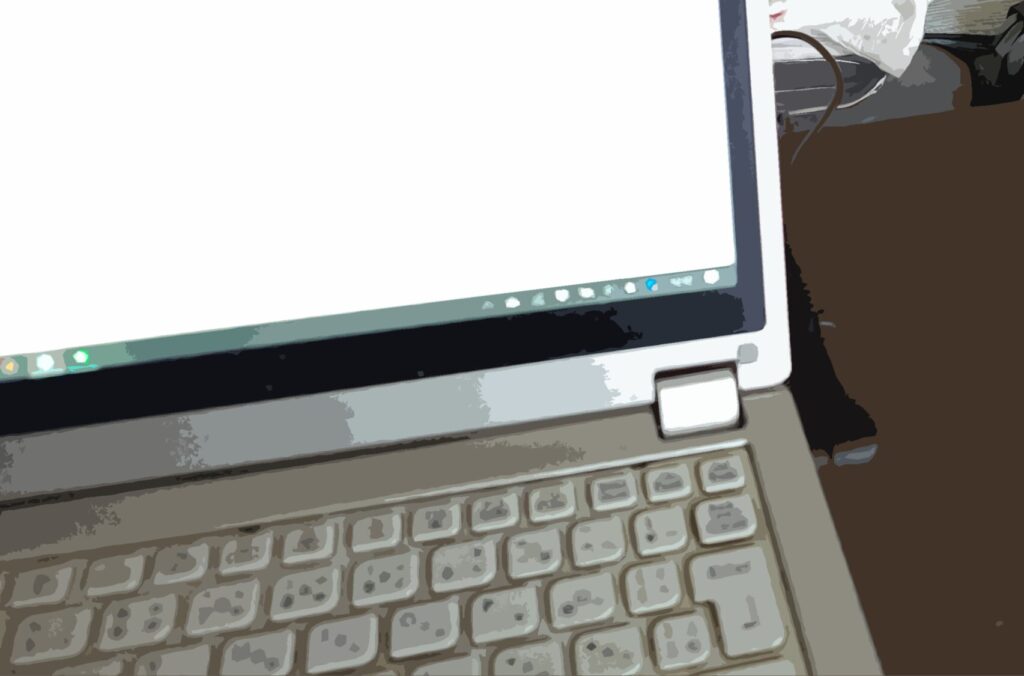
あたしの眼鏡の度数は合っており矯正視力に問題はない。だってほら手元のパソコンの画面に映っている文字や数字は問題なく読める。キーボードの端っこにはそれぞれ色の違う五枚の付箋が貼りつけてあって作成を頼まれている資料の要件と依頼主の名前がメモしてあるのだけどそれらもきちんと読める。でも顔を上げるとあたしの席のすぐ前に立っている男性の顔が見えない。時計の文字盤とか壁に掲示された営業部の成績表だってちゃんと見えているのに。ひとの顔だけが見えない。まるで映り込んだ一般人の顔にぼかしをいれるテレビ番組みたいにひとの顔だけが見えない。
「ねえニシさん、おねがいしていた書類なんだけど予定よりも一日早くもらうことはできない?」と男性はあたしに尋ねる。この男性が誰で頼まれていた資料は何だっただろうかと付箋のメモを横目で見ながらあたしは推察する。現在あたしが作成依頼を受けている資料は五件。そのうち二人はリモートワークをしておりここにはいないはずだ。残る三人のうち一人は女性だった。この時点で二人にまで絞ることができた。いま目の前にいる男性はスズキさんかサトウさんのいずれかだとわかった。どちらだったとしても依頼内容からして締切りを一日早めることは可能だ。
だからこの時点で個人を特定しないまま「大丈夫ですよ」とだけ答えることもできた。先週までのあたしなら実際そのように答えていただろう。だけれど今日はそうしたくなかった。「大丈夫ですよスズキさん」と、ぼかしのかかった顔に向けてあたしは口にした。
それから数秒の間があく。ああ。間があいたことで自分が間違えたことをあたしは理解した。あたしはまた間違えてしまった。「僕はサトウだよ」と男性はあたしに言った。
そう。あたしにはひとの顔が見えない。
誰しもの顔が見えないわけではない。関係性が深い相手の顔であれば見える。たとえば家族の顔ははっきり認識できる。つきあいの長い友だちの顔もわかる。あたしのことを好きだといってくれる男の子の顔も分かる場合がある。でもそれ以外は見えない。
ある日とつぜん見えなくなったわけではなく近眼が進行するのと同じように少しずつ見えづらくなっていった。小学生の頃ははっきり見えていた。中学生の頃も見えていたとおもう。見えにくいことを自覚しはじめたのは高校生の頃だ。
高校時代のあたしには苦手なひとたちがいた。クラスのなかでも華やかで目立つグループに所属していたひとたち。いわゆるスクールカーストといわれるものの上位層に位置していたひとたち。彼らは顔がきれいであったりお洒落であったりした。あるいはスポーツが得意であったりした。話す姿は堂々としており気の利いたジョークで周囲を笑わせたりすることができた。叱られたり傷ついたりしない程度に化粧や夜遊びを楽しんだりもしていた。そのくせ要領がよく定期テストの点数もけっこう良かったりした。そのようなひとたちのことがあたしは苦手だった。
別に彼らに何かされたわけではない。それどころか会話をしたことさえほとんどない。ただ彼らをみていると自分のことが脇役のように思えて嫌な気分になった。期末試験が近い時期の昼休みにあたしは教室で勉強していたけどそのすぐ近くで彼らは夏休みに行く予定だという旅行について意見を出し合っていた。それでいて彼らの何人かは試験の順位があたしより良かったりするのだ。そういうことが積み重なって、やってられないと思った。彼らのことを見たくないと思った。
そんな鬱屈とした気持ちを抱えながら過ごしていたら彼らの顔がだんだんと見えにくくなっていった。三年生の春を迎える頃には特に親しい相手を除き、ひとの顔がほとんど、見えなくなっていた。
この症状はあたしを楽にした。なにせ見たくないものを見なくて済むのだから。親しいひとや自分のことを好きでいてくれるひとだけが視界に映る生活。それは喋ったこともない相手と自分を比べて劣等感に苛まれていた頃と比べればずっと楽だった。自分は誰かの人生の脇役などではなくあたしの人生の主人公であるのだと思うことができた。もちろん人間関係とか仕事において不便に感じる場面はあったけれど良くなった部分と比べれば些細なことだった。
先週のことだ。オフィスに来客があった。パンツスーツに身を包んだ背の高い女性だった。うちの会社が導入を検討しているサービスの営業担当者だという。もちろんあたしには相手の顔は見えないがアポイントメントがあることを確認したうえで会議室に案内した。来客用に冷やしておいたペットボトルのお茶を手渡した。数分で担当者がやってくるはずなので座って待っていてほしい旨を伝えた。ここまでならば何の変哲もない普段通りの来客対応だった。
「もしかしてニシさん?」
それが普段通りの来客対応ではなくなってしまったのはあたしの名前を彼女が呼んだからだ。彼女は高校時代あたしと同じクラスだったという。そう言われてみれば確かに名前に聞き覚えがあった。いつも教室の中心にいたグループのうちのひとり。あたしが心から苦手だと思っていたひとたちのうちのひとりがすぐ目の前にいた。
「懐かしい」と彼女はあたしに言った。「会えて嬉しい」とも。「高校の頃はあんまり話したことなかったけど」「ニシさんは試験前になると休み時間でも勉強してたからわたしも見習わなきゃっていつも思ってた」「口数は少ないけど何でも真面目にやる姿をいつも見ていたから化学の実験とか体育の授業とかで同じグループになると心強かった」「それにしてもひさしぶり」「すごく垢抜けてキレイになったよね」「ねえねえ今度いっしょにごはん食べに行こうよ」
彼女の言葉のひとつひとつに自分がどんな返事をしたのかはっきり思い出せない。ただただ無理だと思った。彼女があたしを覚えているという事実が。当時のあたしが覚えられているという事実が。きっと彼女は、彼女のようなひとは、過去のクラスメートであれば誰と会ってもそういうふうに当時のことを褒めたりできるのだろう。あたしは彼女の顔も見えないというのに。
昼休みになるとあたしはオフィスのそばの公園を訪ねた。ベンチでお弁当を食べているひとりの男性の姿をみつける。顔は見えないがおそらく先ほど資料を一日早く仕上げてほしいとあたしに頼んできたサトウさんだろう。サトウさんはいつも公園でお弁当を食べていると聞いたことがあるからきっとそうだろう。依然として顔は見えないが「サトウさん」とあたしは声を掛ける。また間違えていたらどうしよう、と思いながら。
「ニシさん」と返事が返ってくる。「資料の件ありがとう。ニシさんの仕事はいつも丁寧だからとても助かるよ」と。会話が噛み合った。どうやら今度は間違えなかったらしい。サトウさんに気取られないよう胸をなでおろす。
あたしは彼女に「さっきのことを謝りにきました」と伝える。「名前を間違えてしまってごめんなさい」と謝罪の言葉を伝える。「なんだ、そんなのぜんぜん気にしてないよ」とサトウさんは明るい声で答える。
ああ。先週までのあたしならば、顔の見えない相手に、こんなふうにわざわざ謝りにくるなんて、きっとしなかった。
あいかわらずぼかしがかかったようにサトウさんの顔は見えない。だけれどこのとき、ほんの少しだけぼかしが薄くなり、目や鼻の位置とか、笑った表情だとかが、見えるような気がした。

あとがき
「他者を見るときの解像度が低く、上げた方が良いのかもしれない」ということでお話いただきました。相手がよく見えるとそのぶん負荷も大きくなるので、だいたいみんな自分にとってちょうどい解像度に調節して人付き合いをやってるわけですが、そんななかで解像度を上げることは、けっこう勇気と根気と誠実さを必要とすることだと思います。そういうことを試みるのひとは、やっぱり主人公であり続けるものだなとも。
2024/05/22/辺川銀