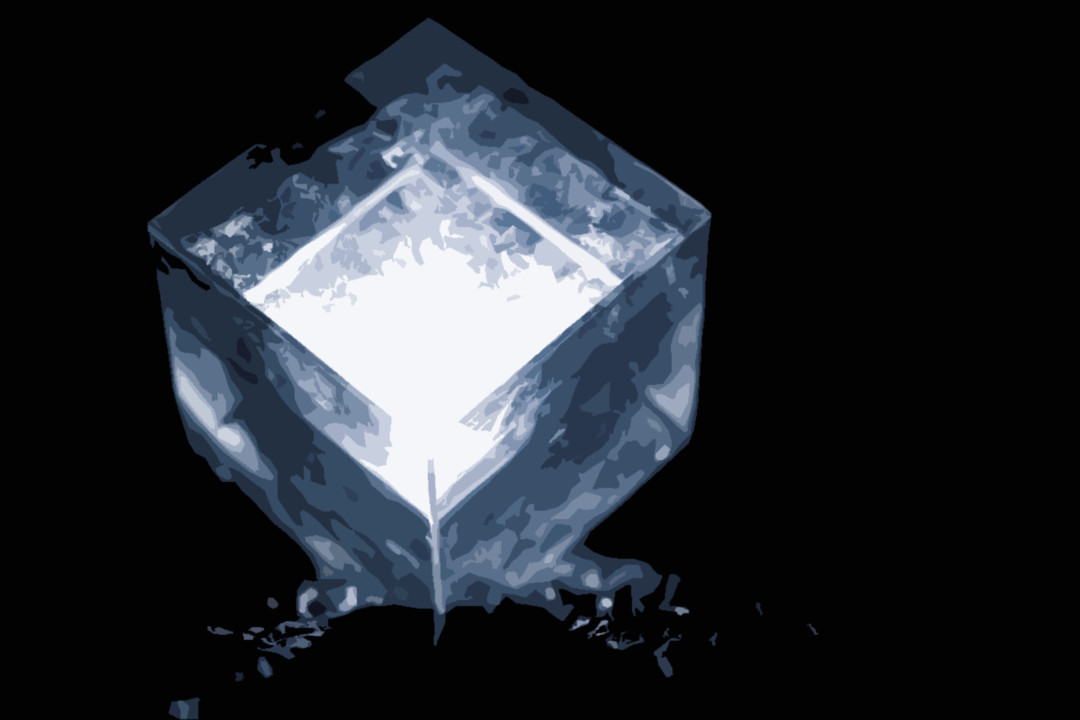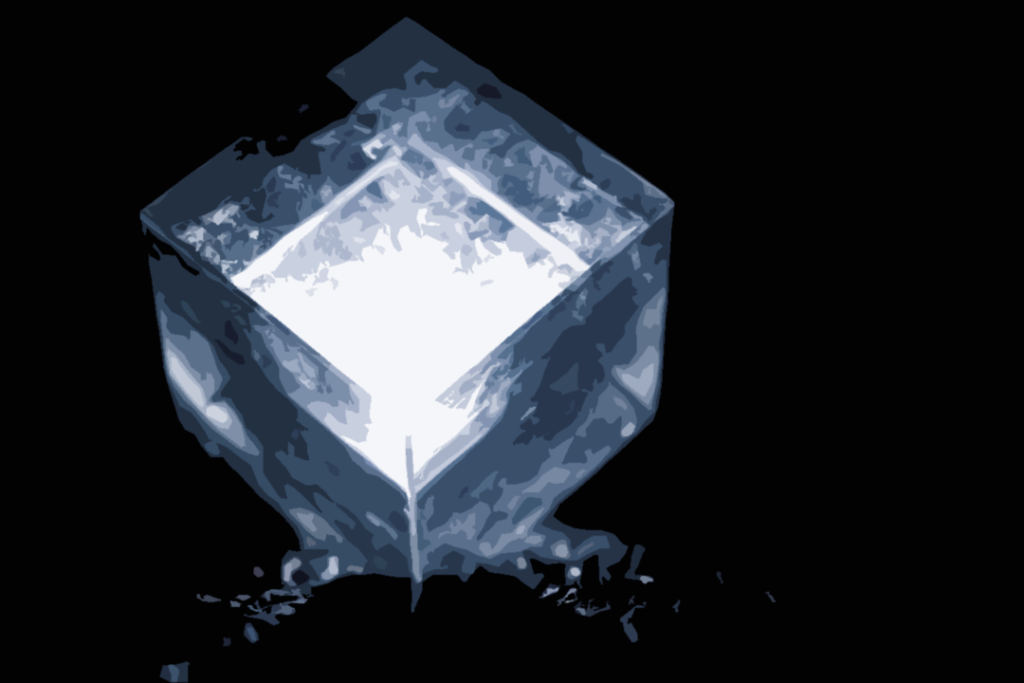
わたしたちのコミュニケーションはあまり噛み合いがよくない。仕事から帰宅すると先に返っていた彼がリビングのソファに座りテレビを眺めていた。わたしは彼に「ただいま」と伝えた。返事は返ってこなかったが「今日は職場で悲しいことがあったよ」とわたしは話を続ける。「先月採ったばかりの新人さんが辞めてしまったんだ。上手くやっていけているように見えたのに残念だった」それでも彼から返事は返ってこない。テレビ画面の向こう側ではベテランの男性キャスターがニュースを読み上げる。地球の総人口における異星人の割合が一割を超えたというニュースだった。そのタイミングで彼は口を開いた。「駅前に新しくできたラーメン屋があるでしょ。さっき行ったけど全然おいしくなかった」それに対してわたしは「そうなんだ」と相槌を打つ。それで会話が終わる。このようにわたしたちのコミュニケーションはあまり噛み合いがよくない。
それからわたしは浴室に行きシャワーで汗を流した。身体を洗っている最中にふと自分の左腕にある無数の白い傷跡が目につく。自傷行為による傷跡。最後に切ってから四年経つが未だにけっこう目立つなあと思う。おそらく一生消えることはない。自傷行為をはじめてしたときわたしは十代だった。学校に行けなくなってしまったとき。母親が異星人だからという理由で仲間外れにされてしまったとき。その時々の恋人とうまくいかなくなってしまったとき。母親との会話が成り立たなくなってしまったとき。そういうときにわたしは自傷をした。自分の身体に傷をつけるとわたしの不安はいくらか和らいだ。心の傷は目に見えないから他人に理解されない。でも身体の傷であれば目に見えるから理解されやすい。身近なひとに理解されることはわたしにとってとても大切だった。なぜならわたしを理解しないひとはわたしに興味がなくいつかわたしを見捨てるはずだと思っていたからだ。わたしの母親がそうであったように。
浴室を出て髪を乾かしスキンケアをしてパジャマを着た。それからリビングに戻ると彼はキッチンの換気扇の下で煙草を吸っていた。「お風呂出たよ」とわたしは彼に言った。すると彼は「パフェが食べたくなったんだけど今からファミレス行かない?」とわたしに提案した。お風呂上がりに外出するのはちょっと面倒くさいけれど「着替えてくるからちょっと待ってて」とわたしは返事をした。寝室に行きクローゼットからジャージを取り出した。クローゼットの奥には銀色の箱が鈍く光っていた。彼の母星には生まれた子どもにああいった箱を渡す文化があるのだという。箱の中には日々の暮らしにおける思い出の品々を入れて保管する。結婚するときとか戦場に向かうときとか死に支度をするときとか、そのような人生の節目には箱の中身を見て、これまで生きてきた軌跡を振り返るのだそうだ。パジャマからジャージに着替え終えて玄関にいくと靴を履いた彼が既に待っていた。
彼の箱の中身をいちどだけ覗いてしまったことがある。あれは四年前でわたしたちが同棲を始めたばかりの頃だ。わたしは彼に自傷を咎められた。わたしは自傷する理由を彼に説明したが理解は得られなかった。理解を示さない彼に対してわたしは強い怒りと不安を覚えた。理解されれなければ見捨てられてしまう。見捨てられないためには理解されるためには心の傷を目に見える形にしなければいけないと思った。もっと自傷をしなければならないと思った。だけど彼はそのときわたしが普段自傷に使うナイフをどこかに隠してしまった。わたしはナイフを探した。家中のいたるところをひっくりかえして探した。キッチンや食器棚はもちろん浴室もトイレも郵便受けのなかも本棚の本の隙間だって探した。それでも見つからなかった。だからわたしは彼の箱を開けた。探していない場所はもうそこだけだった。そこにはナイフはなかった。入っていたのは他のものだっった。
彼は異星人だ。わたしの母親とはまた別の星から来た異星人だ。地球にくるときのことはつきあいはじめる前に軽く話してもらった。彼が母星を逃れてきたのは三十年以上まえのことだという。彼の母星はそのとき戦争をしていた。そのため戦火から逃れるために脱出する若者があとをたたず彼もその中のひとりだったそうだ。彼は当時の恋人といっしょに脱出の計画を立てた。一台の宇宙船にふたりで乗り込んで生まれ育った星を出発した。けれど母星の大気圏を離れたその直後にエンジンが爆発した。「脱出を許さない母星の軍に撃たれたのか、敵対する星の偵察機にやられたのか、あるいはそのへんの宇宙ゴミにぶつかっただけなのか、いまとなっては確かめられないけど、とにかくおれと彼女をのせた宇宙船はその場でダメになった。気付いたときには地球に不時着していて、おれは生きていたけど、彼女は死んでいた」
彼の箱。日々の暮らしにおける思い出の品々を入れて保管するのだという彼の銀色の箱。同棲を始めてまもない時期にいちどだけ開けてしまった箱。そのとき入っていたものはわたしのナイフではなかった。まず最初に目についたのはビニールの小袋にしまわれた髪の毛だった。母星を逃れたときに亡くなった恋人の遺髪だとすぐに分かった。それからツーショット写真。そこに映る彼はわたしが知る姿よりもずいぶん若かった。あとは美術館の半券、テーマパークの記念メダル、映画のパンフレット、そういった類のものが無数に。それを見たわたしは、ああ、彼の気持ちを分からなければならないと思った。今わたしたちは好き合っているのだから彼のことを理解しなければならない。理解することによって見捨てないことを証明しないといけない。だいすきなひとが死んだあとそのひととの思い出を三十年以上も手元におきながら生きてきたひとの気持ちを理解しないといけない。理解しなければ。理解しなければ。
ああ、無理なんだ、と、そのとき理解した。
彼の運転する車でファミレスにたどりついた。空いている店内でイチゴパフェを食べた。「ここのパフェはじめて食べたけどけっこう美味しいね」とわたしは彼に伝えた。「ここのファミレスも喫煙席なくなっちゃったなあ」とパフェを食べながら彼は嘆いていた。わたしたちのコミュニケーションはあまり噛み合いがよくない。彼はわたしを理解しようとしない。理解されることをわたしに求めない。にもかかわらず箱の中身を見てしまった四年前のあの日以来わたしは自分の腕を切らなくなった。
ファミレスからの帰り際にわたしたちはレジの横に置いてあったガチャガチャを回した。カプセルのなかから出てきたのはファミレスのキャラクターが描かれたキーホルダーだった。家にかえると彼はそのキーホルダーを銀色の箱の中にそっと仕舞っていた。

あとがき
このお話をご依頼頂いた方から、あとがきのコメントを寄せていただきました。
わからないことをわからないままにしておくことが出来なかった。
彼の「箱」を覗くまでは。わたしはわたしの孤独を、彼は彼の孤独を。
それぞれが抱える領域に、絶対に立ち入ることが出来ないのだと、わかるのが遅すぎなくて良かった。わたしたちのコミュニケーションは、あまり噛み合いが良くないけれど。わたしの心は、今では強く、かろやかだ。
辺川さん、いつも素敵な小説をありがとう。わたしの生きてきた時間を、過ちも含めて、こんなに愛おしく大事だったと思わせてくれる。またお願いします。