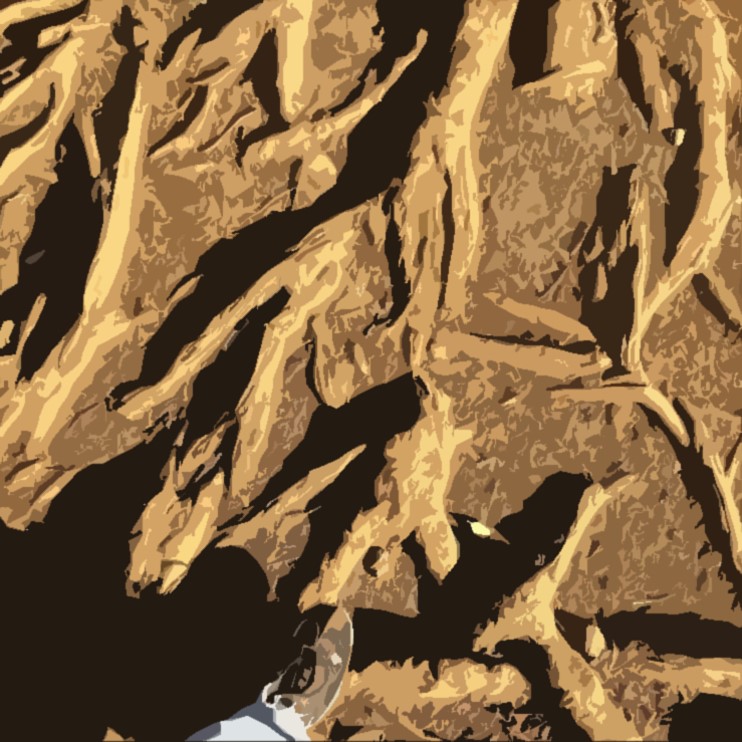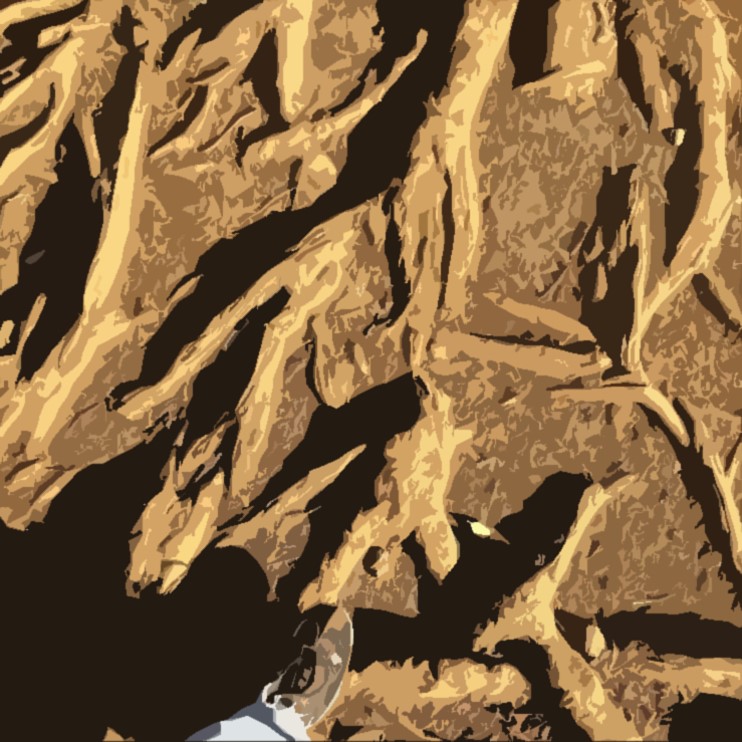
百メートルトラックのゴールラインというのは、スタートラインの側から見ると、実際の距離よりもずいぶん遠く見える。この感覚は陸上を始めたばかりの頃から変わることがない。競技場のスタンドはとても賑やかで選手たちの名前を呼ぶ声が四方八方から聞こえる。周りの選手たちはみんな僕よりも背が高くて、ピリピリした空気を身体に纏っている。僕はというと別にそれほど緊張していないが、その代わりに、数十秒後にやってくる未来を想像して、ただただ気持ちが暗い。軽く足首をほぐしてから、その場で二回、小さくジャンプをした。身体のコンディションはそれほど悪くない。位置について、のアナウンスを合図に、僕らはゆっくりスタートラインについた。賑やかだったスタンドがしんと静まり返った。
中学生の頃。彼は僕にとって唯一の友達だった。彼は陸上部に所属していた。学年でいちばん脚が速かった。放課後のグラウンドで短距離走の練習を繰り返す彼の姿に僕は憧れた。彼は正しい走り方を僕に教えてくれた。真っ直ぐ前を見る。腕をきちんと振る。腿は大きく上げる。どれも彼から教えてもらったことだ。当時の僕は体育の授業以外でスポーツをした経験なんかほとんどなかったけど、彼に走り方を教わるのはとても楽しかった。練習をするたびに脚が速くなっていくことを実感でき、それも楽しさのひとつではあったけれど、それ以上に、僕に走り方を教えてくれる時の、彼の得意げな笑顔を見ることが僕には、何より楽しかった。僕なんかと一緒に居ることで楽しそうな顔をしてくれるひとがいるのだ。その事実が僕には、何より嬉しかった。
高校生になると彼と僕は別々の高校に進学した。彼が入ったのは陸上の名門として有名な私立高校だった。もちろん彼は陸上部に入った。けれどそれから半年ほど経つと彼は陸上部を退部してしまった。名門校の陸上部には彼よりもすごい選手がたくさん所属していたので、彼はすっかり自信をなくしてしまったのだという。
「あそこに居た連中は生まれつきの才能からしておれとは全然違った。あんなやつらと競えるわけがない」
陸上部を退部した直後の時期に彼はそう言った。それからしばらくのあいだ塞ぎこんでしまった。塞ぎこんでいる彼を見ていると僕は悲しくなった。早く元気を取り戻して欲しいと願うばかりだった。
やがて僕らはそれぞれの高校を卒業して大学生になった。彼が入学した大学には陸上部がなかった。彼が大学で所属したのはとても小さい陸上サークルだった。そのサークルは大会にも記録会にも一切出場せず練習するのも月に三日か四日だけだった。そしてそこには彼より速く走れる選手はひとりも居なかった。
「サークルには入ったはいいけどメンバーのレベルが低すぎて嫌になっちゃうよ」
大学生になった今でも僕と彼とは時々会っている。彼は会うたびに自分の所属する陸上サークルの文句を口にする。
「やっぱりもう少し陸上の強い大学に行けば良かったかな。おれはこんなところに居るべき選手じゃない。お前もそう思うだろ?」
そういうふうに彼が言うと僕は必ず首を縦に振る。僕が頷くと彼はとても得意げな笑顔を見せてくれるからだ。かつて僕に走り方を教えてくれた時と同じように笑ってくれるからだ。彼のこの笑顔を、僕はこの先も損ないたくはない。できることならば。
位置について、のアナウンスを合図にスタートラインについた。賑やかだったスタンドがしんと静まり返った。審判がピストルを空に向かって掲げた。百メートル先にあるゴールラインをまっすぐに見据えながら僕は考えた。もしもこのレースに勝てば僕はこの国でいちばん脚の速い大学生になる。そうなったら当然、テレビにも僕の顔が映るし、彼もそのことを知ってしまうだろう。そしてその時、彼は恐らく僕の傍から離れていくだろう。それは僕にとって何より怖いことだ。レースを放棄して逃げ出してしまおうかという考えが一瞬頭を過ぎった。けれど次の瞬間スタートの合図が競技場に響くと、僕の身体はいつものようにゴールラインを目指して、非の打ち所のない最高のスタートを切った。