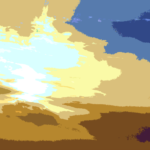父が入院する精神病院を訪ねる。面会場所である談話室には南向きの大きな窓があって五月の午後の自然光でいっぱいに満たされて過剰にやわらかな雰囲気が演出されている。父はずいぶん痩せて六十歳にもなっていないのに枯れ木のような見た目になってしまったし常にぼうっとしてほとんど喋りもせず娘のわたしがこうして会いに来ていることさえたぶん分かっていない。ねぇお父さん子どものころ毎年一緒に行っていた花火大会さあ去年が最後だったんだって今年からはもうやらないらしいよと話しかけても返事はないし視線も動かない。電源が入らない壊れたスマートフォンをずっと持っていて蜘蛛の巣みたいに割れた液晶画面にときおり指を這わせている。
面会を終え病院の正面玄関から外に出たところでわたしを迎えに来てくれた恋人の姿をみつけるとプールの水面から顔を出したときみたいに大量の酸素が肺に一気に流れ込んでくるような感覚を覚えた。緊張感と息苦しさから開放された途端ぐらりと目眩がして思わずその場に座りこんでしまった。恋人は慌てた様子でこちらに駆け寄ってくると膝をついてわたしの手をとり「大丈夫ですか」と声をかけてくれた。先月で大学三年生になった彼はすでに二年も交際しているにもかかわらずわたしより十歳も歳下だからという理由で未だ敬語で話す。わたしはすぐに立ちあがることも顔をあげることもできないまま視界を占める彼の赤いスニーカーをぼんやりと眺めた。
父が経営していたインターネットのサービスを作る会社はわたしが高校二年生のときに倒産した。それをきっかけにおおらかで優しい性格だった父は別人のように変化してしまいほとんど口にしなかったお酒を昼間から飲んだり「おれのことを馬鹿にしてるんだろう」「売春してるんだろう」「お前もいきなりいなくなるんだろう」などとわたしを怒鳴りつけたり家のなかにあるものを投げたりするようになった。あるとき父の投げたお酒の瓶がわたしの顔に当たった。わたしの右目の視力はその出来事で大きく落ちてしまい治る見込みはない。父の状態はそれ以降も悪化の一途を辿りいよいよ意思の疎通ができなくなると入院させるしかなかった。そして今に至る。
恋人はタクシーを拾ってわたしを自宅まで送り届けると「あなたはお父さんと距離を取ったほうが良いと思います」と言った。彼はわたしの父が入院している理由やわたしが週にいちど面会に行っていることや面会のたびに先ほどのように気分が悪くなり立てなくなったり吐いたり過呼吸を起こしたりしていることを知っておりだから今日だってわたしのことを心配して迎えに来てくれた。「もちろん家族を大切にするのは素敵なことだけどそれにしたってあなたの人生が犠牲になりすぎてる。いちどお父さんと距離を置いて自分が苦しい気持ちにならないよう暮らしてほしいです」と真剣な口調で彼はわたしにいった。それに対してわたしは、そうだね、と答えた。
父はひとりで娘のわたしを育てた。母親についてはどこかで自由に暮らしているということしか聞いたことがない。だけど子どもの頃のわたしは自分が父に愛されていることを理解できていたので寂しくはなかった。象徴的な出来事として思い出されるのは初めて花火大会に連れて行ってもらった幼い日のことだ。破裂音とともに夜空に広がる色とりどりの花火は美しくて目が離せなかったけれど同時に大きくて眩しくて圧倒的で恐ろしいとも思った。だからそのときわたしは父の大きな身体にぎゅっとしがみついた。すると父は、とんとん、とんとん、と一定のリズムでわたしの背中を優しく叩いてくれた。わたしはそれで安心していつの間にか眠りに落ちていた。
父によって傷つけられた記憶を消すことができればどんなに良いだろうとわたしは考える。酒瓶をぶつけられて右目の視力が戻らなくなったことを忘れてしまえたらどんなに良いだろうとわたしは考える。そうすればわたしは今でも子どもの頃と同じように父のことを大好きでいられるだろうと思う。あるいは愛された記憶を消すことができればどんなに良いだろうとわたしは考える。一緒にご飯を食べたことや寝かしつけてもらったことや抱きしめられたことや花火大会に連れて行ってもらったことを忘れられたらどんなに良いだろうとわたしは考える。そうすれば恋人のいうように私は父との距離を置いて今よりもいくらかは楽な気持ちで過ごせるはずだと思う。
深夜三時に頭痛で目を覚ました。窓の外からは雨音がかすかに聞こえてくる。右目を痛めてからというもの雨が降るとこうして頭がずきずき痛む。恋人はわたしの隣ですやすやと眠っており服は着ていない。わたしは自分より十歳も若い彼の身体を人差し指の先でなぞってみる。日焼けしているのに肌理の細かい滑らかな肌を指でなぞってみる。二週間前に大学のサークルでサッカーをして転んだ際に負ったといっていた肘のすり傷があとかたもなく治っていることに気がつく。若い身体だなと思う。ちょっとした怪我ならすぐに治ってしまう身体だなと思う。治らない傷を負ったことのない身体だなと思う。わたしはきっと来週も父のところを訪ねるだろうと思う。
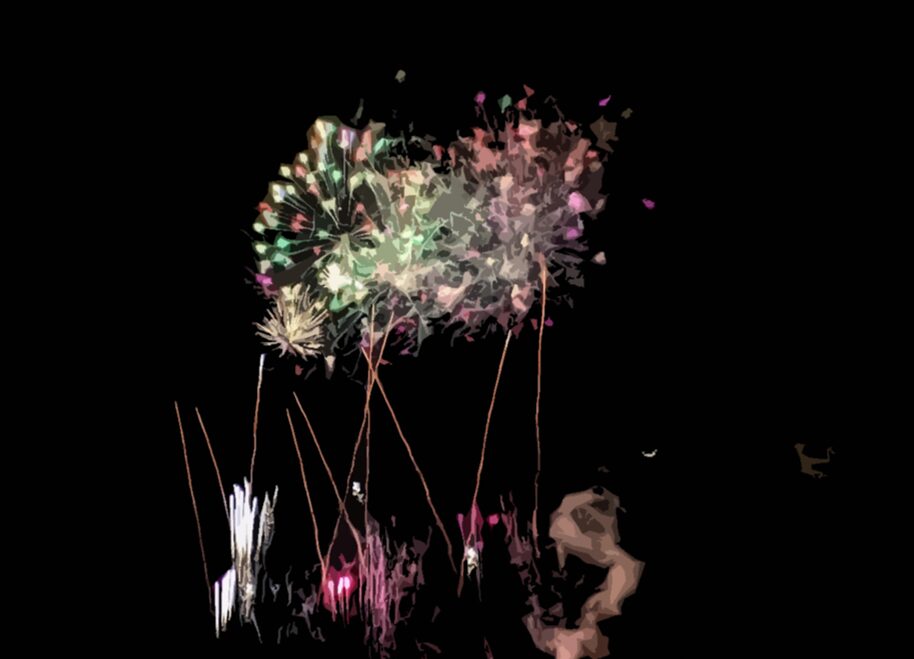
あとがき
親との関係がひどく悪いとしても、嬉しかった思い出というのが数えるぐらいはあり、そのことがむしろ自身を苦しめる要因になる……。そんなケースについて話していただき、これを書きました。
2024/09/21/辺川銀