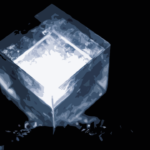カシマが死んだらしい。それでもおれは今日も仕事をする。ふだんどおりに働く。つとめて明るく働く。今日は十二月らしいカラッとした晴天。おれは自社でとりあつかう賃貸物件にむけて車を運転する。後部座席には内見を希望する若い夫婦が座っている。夫婦には春に子どもが生まれる予定だという。つまり彼らが探しているのは生まれてくる子を育てるための家だ。重視するポイントは治安が良く静かな環境であること。これから向かう物件が彼らの希望を満たすものであればいいと思う。今日はじめて会った彼らの未来が幸福なものであることをおれは心から願った。
カシマが死んだらしい。おれにそのことを知らせたのは今も地元で暮らしている幼馴染の男だ。「東京出張に来たから飲みに行こうぜ」と誘われてそこで知らされた。数年ぶりに会う彼のする話は共通の知人や友人にまつわる噂話ばかりだった。いつ会ってもそうであるように。地元の人間の多くがそうであるように。ここにいない人物の噂話ばかりだった。誰と誰が結婚したとか誰々が家を建てたとか病気になったとか借金を作ったとか。そういう話題をいくつも聞かされた。そういう話題のうちのひとつとしてカシマが死んだことをおれは知らされた。
カシマは夏の海で死んだらしい。もう四ヶ月も前だ。ひどく酒に酔った状態で海に入って溺れて死んだらしい。砂浜で倒れているところを発見されたのは朝になってからでその時にはもう息がなかったらしい。「一応事故ではあるけど」と噂好きの幼馴染は言った。「半分は自殺みたいなもんだってみんな言ってるよ。だってカシマは自殺未遂とか入院とか何度もやってたから。いつかこうなると思ってたってみんな言ってるよ。それよりお前たまには地元に帰ってこいよ。もう何年も帰ってきてないじゃん。そろそろ会いたいってみんな言ってるよ」
中学三年の春にカシマは転校してきた。母親とふたりで東京から引越してきたという彼女は物静かだが背筋の伸びた美しい立ち姿をしていた。だがそんなカシマ母娘を地元の連中は気に食わないよそ者と見做した。母子についての悪い噂が町を飛び交った。わざわざこんな田舎に引越してくるなんて後ろ暗い理由があるはずに違いないだとか。実は父親が犯罪者なんだろうとか。怪しいカルト宗教を広めにきただとか。そのうちのひとつもおれは信じなかった。卒業するまでカシマ本人と話したことがいちどもなかったからだ。おれがカシマとはじめて話したのは中学を卒業した後のことだった。
中学を卒業するとおれは隣の市の高校に進学した。地元の街にはふたつの高校があり同級生のほとんどはそのうちのどちらかに進学したがおれは隣の市の高校を選んだ。そこが現実的に通えるなかでいちばん偏差値の高い高校だったからだ。毎朝五時に起きて一時間に一本しかない電車に乗って登校した。放課後は予備校で学力を伸ばすことにつとめた。高校を卒業したらぜったいに東京の大学に進学すると決めていたからだ。高校を卒業したらぜったいに地元から離れると決めていたからだ。こんなに息苦しい田舎町など捨ててやると決めていたからだ。
おれがカシマとはじめて話したのは高校二年の冬休みの夜のことだった。その日おれは予備校で冬期講習を受けてからぎりぎりの時間まで自習室で勉強をした後に走って駅へと向かった。終電の五分前に駅にたどり着いた。改札を通り階段を登ってホームに行くとカシマの姿を見つけた。ホームの端の黄色い点字ブロックの上にカシマは立っていた。カシマの姿を見るのは中学校の卒業式ぶりだったがすぐに彼女だと分かった。背筋の伸びた美しい立ち姿が中学時代と変わっていなかったからだ。冬休みであるにもかかわらずカシマは高校の制服を着ていた。
カシマ。とおれは思わず小さくつぶやいた。すると彼女は点字ブロックの上に立ったまま視線をこちらに向けた。それから「ひさしぶり」と言って微笑みを浮かべた。点字ブロックから降りてこちらに近づいてきた。「中学のとき一緒だったよね」とスカートの裾がおれのコートの裾に触れるぐらいの距離でカシマはおれに言った。「中学のとき一緒だったよね。喋ったことないけどあなたのことはちょっと覚えてる。教室でひとりだけ居心地悪そうにしていたから」スピーカーから音楽が流れた。間もなく最終電車が到着するというアナウンスが流れた。
なにしてるの。とおれはカシマに尋ねた。絞り出したような情けない声で尋ねた。「電車にひかれたらどうなるかなって考えてた」とカシマはおれを見上げながら答えた。「考えてただけだよ。本当にはやらない」ホームに電車がすべりこんできた。扉が開いて何人かが下車した。この電車が終電であり間もなくドアが閉まることを伝えるアナウンスが流れた。にもかかわらずカシマはおれを見上げたまま動こうとしない。乗らないの。とおれはカシマに訊いた。「乗りたくなくなった」とカシマはふたたび微笑む。ドアが閉まる。電車は行ってしまった。
駅を出て親に電話をした。今日は予備校の友だちの家に泊まると親に嘘を伝えた。電話を切ると「これからどうしよっか」とカシマは言っておれの手を取った。「ラブホテルでも行こっか。わたしそういうのぜんぜん平気だよ」なにが平気なのかさっぱりわからなかった。結局公園で一晩を過ごした。コンビニで買ったコーヒーとかスナック菓子とかを口にしながら過ごした。そのあいだカシマは中学時代の物静かな印象が嘘のように喋り続けていた。喋った内容はあまり覚えていない。だけどカシマがずっとにこにこしていたことだけ印象に残っている。
翌朝の始発に乗っておれたちは帰った。始発に乗り込み椅子に腰掛けるとカシマはすぐに眠りに落ちてしまった。おれの肩のうえに頭を乗せながらすやすや眠っていた。おれは少しも眠たくならなかった。地元の駅が近づくとおれはできるかぎり平静を装いながら彼女の肩を軽く叩いて起こした。駅の改札を出たところでおれたちは別れた。「高校を卒業したらあなたどうするの」とカシマは別れ際におれに訊いてきた。東京の大学にいくつもりだとおれが答えると「ふうん」と薄い反応を返した。それでおしまいだ。それ以降二度と会うことはなかった。
カシマが死んだらしい。四ヶ月も前にカシマは死んだらしい。おれはそのことを昨日知らされた。子育てのための物件を探しにきた若い夫婦は結局三つの物件を内見した。そして最後に見た物件で契約すると決めた。キッチンがカウンタータイプになっており料理をしながらリビングの様子が見えるところが気に入ったのだという。店舗に戻り仮契約の書類を書いてもらってから夫婦を送り出した。おれは今日も働く。普段どおりに働く。つとめて明るく働く。明日もきっとそうする。カシマのことを思い出すことはこの先きっと何度かあるのだろうと思う。でもそのことで自分勝手に悲しんだりとか泣いたりとか誰かに話したりだとかはきっとしないだろう。

あとがき
「もしも私があした死んだなら、残された人はきっと、もう喋れない私の気持ちを好き勝手に代弁して消費するんだろう。そういうのはちょっと嫌だなと思った」という言葉から膨らませたお話です。
2024/06/30/辺川銀