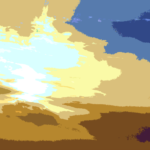私は走る。終電後の線路沿いの道を自分の足で走る。十二月の夜風をかきわけて走っていく。走り出してから十五分ほど経つとこの季節でも汗が滲んでくる。意識するのは呼吸だ。吸う、吸う、長く吐く、吸う、吸う、長く吐く、四拍子のリズムに合わせてこれを繰り返す。とくに大切なのは肺の中が空になるまで強く吐くことだ。強く吐きさえすれば吸うほうはそれほど意識しなくても空っぽになった肺が自動的に多くの酸素を取り込む。そういうふうに身体ができている。ランニングシューズの丸みを帯びた爪先が地面を捕まえてこの身体を前に進めていく。
仕事を終えたあとのランニングが私の日課になりそろそろ一年が経つ。私は現在三十三歳という年齢だがこの一年は台風が来ようと雪が降ろうと血を流そうと熱が出ようと一日たりとも休むことなく走ることを継続した。仕事で泊まり込むことになった日でさえ一度帰宅して走ってから会社に戻ったほどだ。この習慣により心肺機能や筋持久力は一年前より大きく向上したがそのせいで痛みや苦しみを感じるまでに必要な速度や距離も多くなってしまった。もっと速くもっと長く走らなければ痛く苦しくならない。そして私はさらに加速する。
用水路にかかる橋を渡りきったところでランニングを終えてショートパンツのポケットからスマートフォンを取り出すと顧客からのメッセージが届いていることに気づいた。クールダウンのために歩きながらメッセージの内容を確認すると昼間に納品したデータで変更を頼みたい箇所があり可能であれば朝までに対応してほしいという旨が書かれていた。かしこまりましたと私は返信する。帰宅してシャワーを浴びたらすぐに準備してタクシーを呼び会社に戻ると決める。
自宅に帰り着くと夫がリビングでスマートフォンをいじりながらビールを飲んでいた。私がただいまを言うと彼は私の方を見て「おかえり」と言い「きみも飲む?」と尋ねる。シャワーを浴びたら会社に戻るので今日は遠慮しておくと私は返事をする。冷蔵庫からペットボトルのスポーツドリンクを取り出してコップに注いで飲む。彼は「無理はしないようにね」といつものセリフを言い画面に視線を戻す。
それから私は脱衣所に行き汗で湿った衣服を脱いで洗濯機に放った。あらわになった私の左腕には十代の頃にした自傷の跡がある。それは手首から腕の関節にかけて無数に残っている。跡はケロイドになっており指でふれるとぼこぼこと盛りあがったその形がわかる。十五年以上も前の跡だから今はもちろん痛くも痒くもないがこれ以上目立たなくなることはおそらくないだろう。
-
幼い頃。お母さんはたまにカッとなって私のことを叩いた。それは頻繁ではなかった。だけど一回や二回でもなかった。私を叩いたときお母さんは必ずハッとした表情を浮かべた。数秒後には目に涙を浮かべながら私を抱きしめ「ごめんなさい」と言った。「ごめんなさい。また叩いてしまった。叩くべきではなかった」そして震える声で叩いた理由を説明するのだった。「あなたがひとりで家のそとに出かけようとしたから」「あなたがお父さんに会いたいというから」「あなたがクラスに気になる男の子がいるだなんていうから」「あなたがいつかママのもとを離れて暮らすなんていうから」「だから頭に血があなたを叩いてしまった。ごめんなさい。本当にごめんなさい」と。
でも当時の私はお母さんに叩かれることが嫌いではなかった。私はお母さんのことがとても好きだった。ほとんどの幼子がそうであるように自分のお母さんのことが何より好きだった。ほとんどの幼子がそうであるようにお母さんに抱きしめてもらうことは至上の幸せであり至上の安心だった。だから私はお母さんに叩かれることが嫌いではなかった。叩かれたあとは必ず抱きしめてもらえたから叩かれることが嫌いではなかった。幼い頃の私にとって叩かれる痛みはそのすぐあとに自分を包み込む感動的な幸せや安心の前兆なのだった。
けれど思春期に差し掛かると私はお母さんに叩かれなくなった。それどころかお母さんとの関わりそのものがめっきり希薄になった。「今日は仕事が遅くまでかかりそうで」「今日は彼氏の家に泊まる予定だから」「テーブルにお金は置いておくから何か買って食べてね」そのように言ってお母さんが家に帰ってこない日が週に数度はあった。起きてから寝るまでお母さんと会わずに過ごすことも珍しくなかった。お母さんは明らかに私から距離を置こうとしていた。距離を置かれた理由はもちろん理解できた。私がひとりで出かけられるようになったからだ。私が友達を作ったり恋心を抱いたりできるようになったからだ。私がお母さんの望まざるものになってしまったからだ。
思春期における世界の広がりや恋心や身体の変化は時に本人の意思に関係なく発生するものだ。私もそうだった。だが一方でこの時のわたしにはお母さんを裏切ってしまったという罪悪感があった。私にとって思春期の好奇心や胸躍る新しい出会いは常に罪悪感と表裏一体だった。学校で意中の男の子と二言三言の会話を交わせば軽やかな甘酸っぱさで胸が満たされたが数時間後にお母さんのいない家に帰り着いたときには黒く重たい鉛の心になった。それは耐え難かった。抱きしめてほしいと思った。痛みとともに抱きしめられて安心感に包まれたいと思った。だけれどお母さんはもう私に痛みを与えることをしない。
それで私は自傷行為をするようになった。カミソリを手に取り自分で自分に痛みを与えるようになった。そうすれば自分で自分を抱きしめられるような気がした。いつしか痛み自体を安心感と混同していきそれは常習化した。
-
シャワーを浴び終える。バスタオルで身体を拭いて衣類を身につける。ドライヤーで髪を乾かす。スキンケアをする。腕を切るような自傷は今はしていない。常習化したといっても十代後半のほんの数年だけだ。だが三十三歳の今、自傷そのものをしなくなったかというとちょっとわからない。もしかしたら今でもやっているのかもしれない。たとえば受験生時代に睡眠時間を極限まで削って勉強したことや、会社に泊まり込んででも仕事をすること、熱が出ようが血が流れようがランニングをしていることなども、痛みのためかもしれない。もちろんいつもそう考えながらやっているわけではないが、自傷行為の一種であるかもしれない。志望校に合格したり顧客や上司からの評価が上がったり収入が増えたり走れる距離が長くなったりすることはあくまで痛みの副産物にすぎないかもしれない。もっとも、痛みのためたとしてもそれで暮らせているのだから今は別にそれで良いとも思う。いつか何らかの形で限界がくるのかもしれないが。今はこれで良いと。
リビングに戻ると夫はさきほどと変わらずビールを飲んでいた。私が戻ってきたことに気付くと「ねえそういえば」と言いスマートフォンの画面を私の方に見せてきた。「三月に市民マラソンがあるでしょう。あなたも出てみたら? エントリー期限は今週末だって」とはずんだ声で言う。そうだね。と私は思わずため息をついて答える。せっかくだから出場してみようか。理由はともあれせっかく、走っているのだから。

あとがき
好きこのんで経験したわけではない出来事、後悔していること、あるいは楽しく前向きにやってきたこと。そのいずれにも「せっかくだから」を見つけ出せますように。
2024/10/9/辺川銀