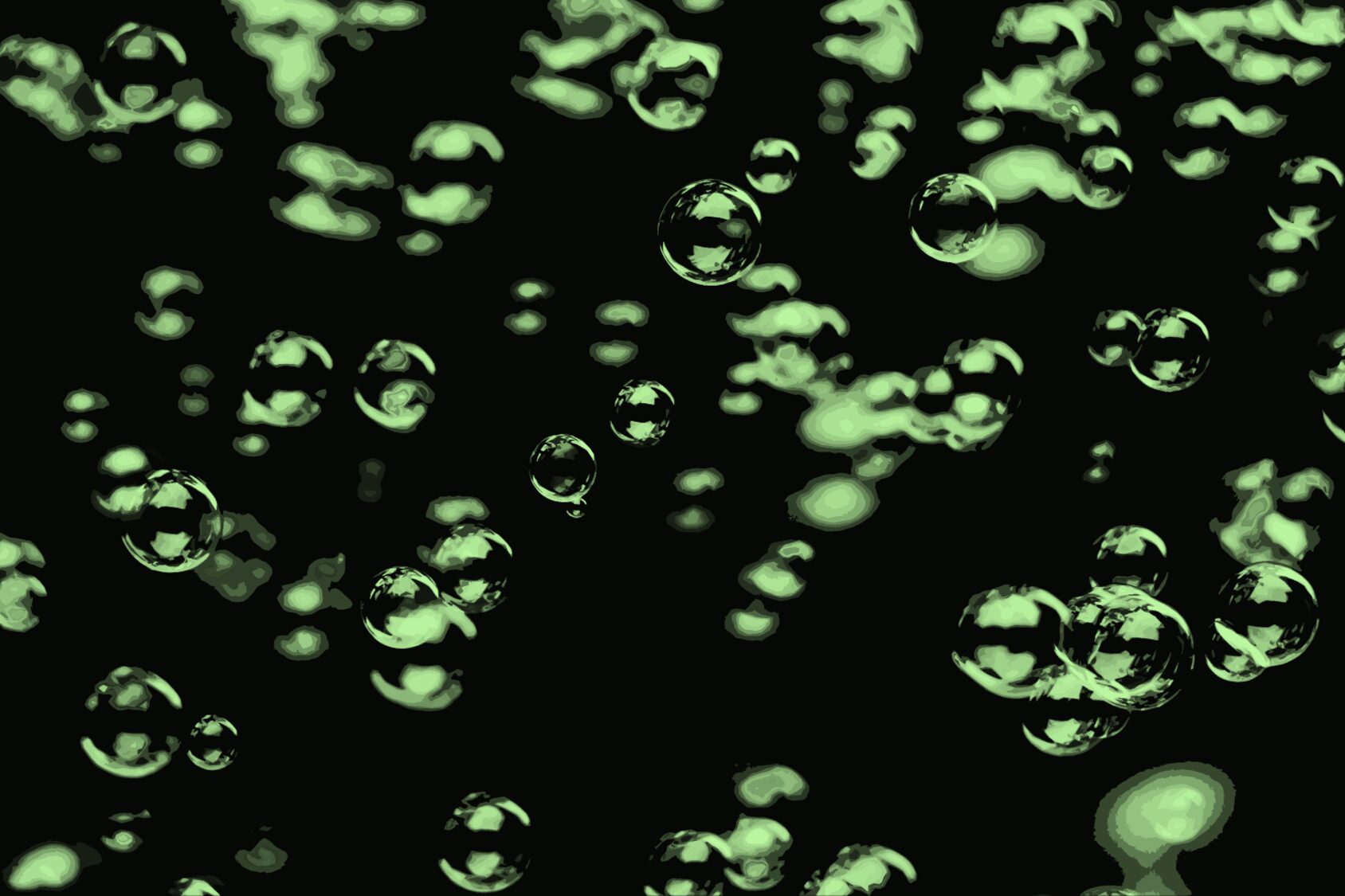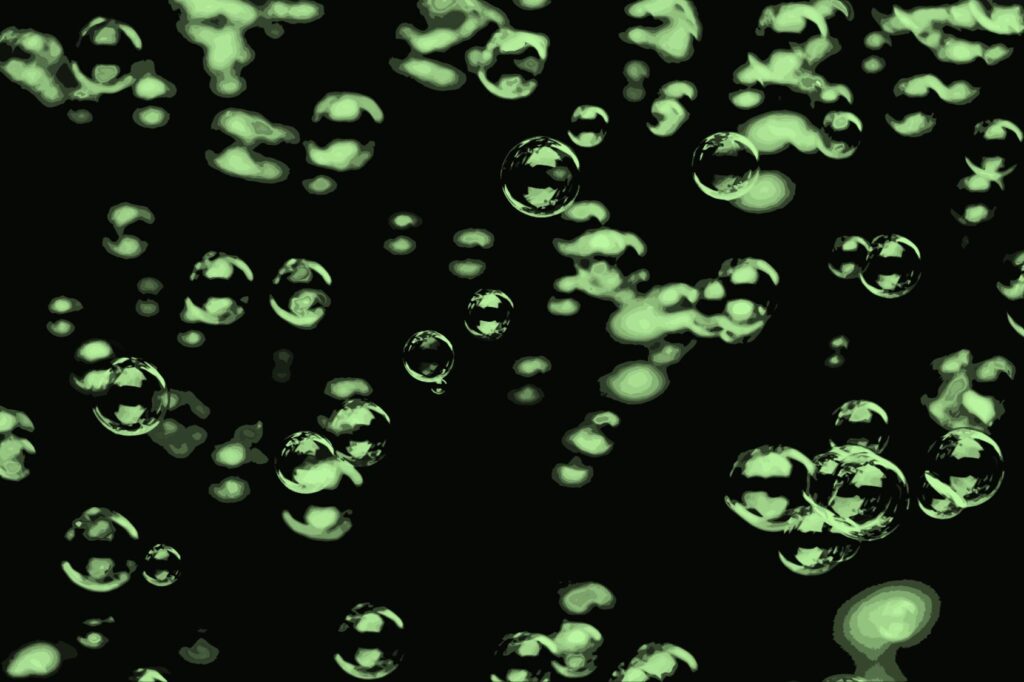
地方の役所にわたしは勤めている。良い職場だなと思う。忙しくないときであれば適度に軽口が飛び交う。例えば今日であれば、毎週火曜の夜に放送中の、ドラマの話題に花が咲いている。女子学生が担任教師との恋に落ちるドラマだ。「ああいうことが実際にあると役所は困るのだ」と誰かがが口にする。「そうだよねえ」と誰かが合意する。「とはいえあれはなかなか良いドラマよ」と誰かが反論する。そういった雰囲気であっても、課せられた仕事については、各々きちんとこなす。
――
昼休みには所内の食堂で後輩と食事をした。彼女は今年の春に大学を卒業した新人である。この町の出身であり、過疎化が進む地元を少しでも良くしたいと考え、役所への就職を選択したという。入職してから七ヶ月が過ぎたが、物覚えがよく、頼りに感じる場面が徐々に増えてきている。いつも背筋をピンと伸ばし、一生懸命なので、わたしを含めた職場の皆が彼女のことを、親戚のこどものように好意的に思っている。日替わり定食のカルボナーラを食べながら彼女は「先週末は、一緒に住んでるお祖父ちゃんと競馬に行きました」と笑顔で話してくれた。
――
夜。退勤したわたしは車で浜辺へと向かった。浜辺の近くは街灯は少なく、月も出ていないので、車を停めてヘッドライトを消すとずいぶん暗くなる。ドアを開け、車の外に出た。冷たい空気に触れ、海の匂いを鼻腔が捉えると、わたしの身体からは、ぼんやりとした緑色の光があふれだし始める。
身体が緑色に発光したままの状態でわたしは砂浜に降り、海の方へと歩く。海が近づくにつれてあふれ出す光の量は多くなっていく。そしてわたしが、波打ち際まで、たどり着いて立ち止まると、緑の光はまるでシャボン玉のような小さな光の玉になり、ぽこぽこ、ぽこぽこ、と、少しずつこの身体から離れて、波に飲み込まれて、海へと消えていく。
そのまま波打ち際にしばらく立ち尽くしていると光の量はだんだん少なくなり、やがて完全になくなる。周囲が暗くなる。海が、わたしの中からあふれる光をすべて飲み干したのだ。わたしは目眩をおぼえる。ふらつきながら、波打ち際から数メートル離れて、乾いた砂のうえにへたりと座り込む。ズボンのポケットにあらかじめ入れておいた錠剤を取りだし、口の中に放って、噛まずに飲み込んだ。
今、わたしの身体に起きた現象は、呪いによるものだ。一般的には「海の呪い」といわれているものだ。この呪いにかかった者は、海に近づくと身体から緑色の光があふれでるようになる。そして週にいちど、その光をこうして、海に捧げに来なくてはいけない。もしも光を海に捧げないまま八日以上がすぎると、おとぎ話の人魚姫みたいに、身体が泡になって消えてしまう。そういう呪いなのだ。
緑の光の正体は、わたしの中にある、元気とか活力とか、喜びとか、そういった好ましいエネルギーが可視化されたものだ。だから光を海に捧げた後は、全身から力が抜け、気分がひどく落ち込む。幸いなことに、その症状を緩和する薬は、病院に行けば処方してもらえる。わたしが先ほど飲み込んだ錠剤がそうだ。これを飲むことで、帰りの車を運転できる程度には元気を回復できる。しかしいくら薬があるといっても、この呪いがひどく不快なものであることに変わりはない。また、海に来ない期間が長期間になれば身体が泡になるので、海から離れて生きることができない。
一応、薬とは別に、根本的な解呪の方法も確立されている。その方法はたいへんシンプルだ。愛するひとを見つけて、相思相愛となり結ばれればよろしい。下世話な方法だが、とにかくその方法で海の呪いは解ける。解けるのだが、しかしわたしは未だに呪われている。
呪いを解こうと試みた時期もあった。つまり誰かと結ばれようと試みたことはあった。しかし上手くはいかなかった。いわゆるマッチングアプリだとか街コンとか、そういったものを試して、実際にわたしに好意を抱いてくれる異性に出会うこともできた。だが、そうして出会った誰とも、相思相愛となるところまでは至らないのであった。彼らに落ち度があったわけではない。ただただわたしが、相手を愛するところまで至れなかったのだ。誰か特定の異性を恋愛的に愛している自分、というのが、どうにも気持ちが悪く、我慢がならなかった。気持ち悪く思っているという事実から目を逸らしながら交際までこぎつけることまではあっても、やはりそれでは、呪いは解けなかった。やがて呪いを解こうと思うことをやめた。
海を憎く思う。呪いと縁なく暮らせる人たちは、海は世界に通じているというが、わたしにとっての海は、ただただわたしを束縛するものであり、世界を狭める存在でしかないのだ。風が強く吹く。初雪はまだだが、もう数週間のうちにはきっと降るだろう。
ふと、風下に目をやる。そこにわたしは光を発見した。緑色のぼんやりとした光だ。それはまさしく、海の呪いを受けた者が発する光に間違いなかった。わたしは立ち上がり、光の方へと近づく。この町に、わたし以外にも呪われた者がいたのか。
そこにいたのは、あの後輩であった。いつも背筋をピンと伸ばし、一生懸命に働く、あの後輩だった。それが波打ち際でうつむき、下唇を噛んで、緑の光を海に捧げていた。わたしが声を掛けると、彼女は顔を上げ、それから「せんぱい」と小さく呟いた。それは波より小さな声であったが、わたしの耳には聞こえた。
――
翌日。わたしは普段通りに役所に出勤し、後輩もそうした。この日の職場は、地元のプロ野球チームに所属するスター選手が、海外リーグへの挑戦を表明したことについての話題で持ちきりだった。「彼ならきっとどこにいっても活躍できるだろう」と誰かが口にする。「果たしてそんなに甘いものだろうか」と誰かが疑問を呈する。「年俸はいったい幾らになるんだろう」と誰もが邪推をする。わたしも意見を求められて、「できれば海など渡らずにいてほしいですけれどね」と答える。そんななかであっても、各々が与えられた仕事は、きちんとこなしていく。良い職場だなと思う。
――
昼休みには所内の食堂で後輩と食事をした。彼女は普段よりもすこし緊張した様子で、日替わり定食のドリアを食べる速さも、かなりゆっくりだった。「病院には行っているのかい」と、わたしは質問する。彼女は視線を落としたまま、首を横に振った。「行ったほうが良い」と、わたしは口にする。「薬はちゃんと効くし、わたしはそれでずいぶん楽になった」彼女はこくりと短く頷く。午後も仕事は続く。

あとがき
自分を信じていようと、信じていなかろうと、日々、着々と積み上げた軌跡はきっと、道に迷った誰かにとっての標(しるし)となるはずです。
2024/10/24/辺川銀