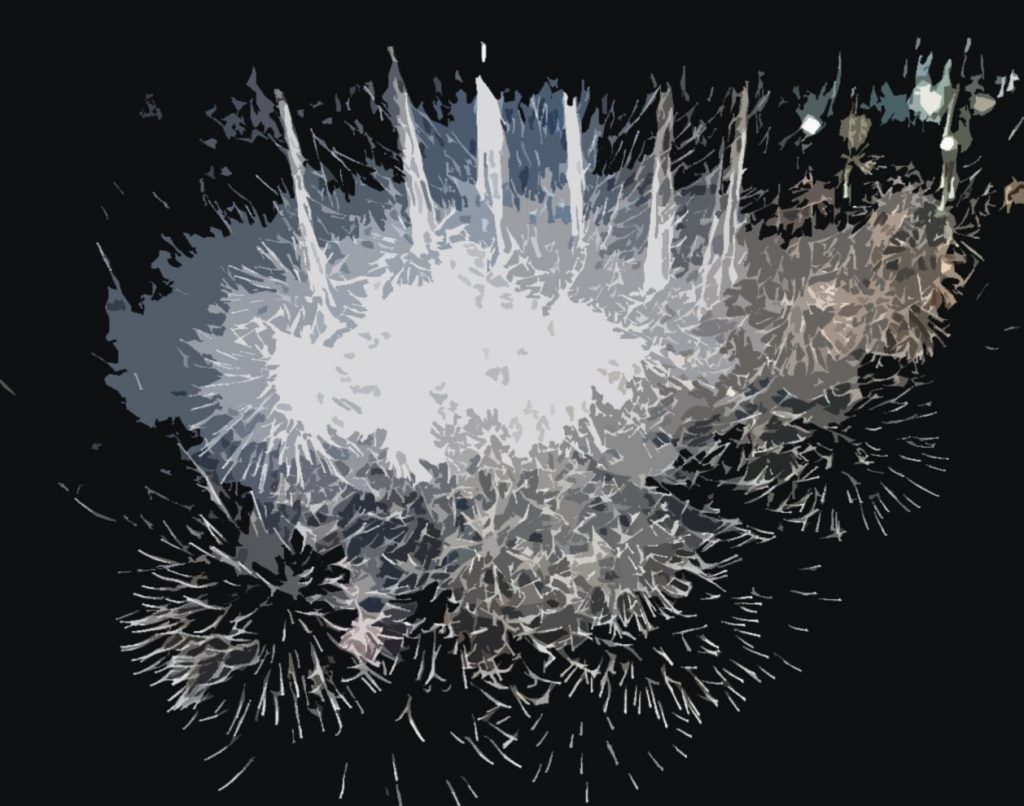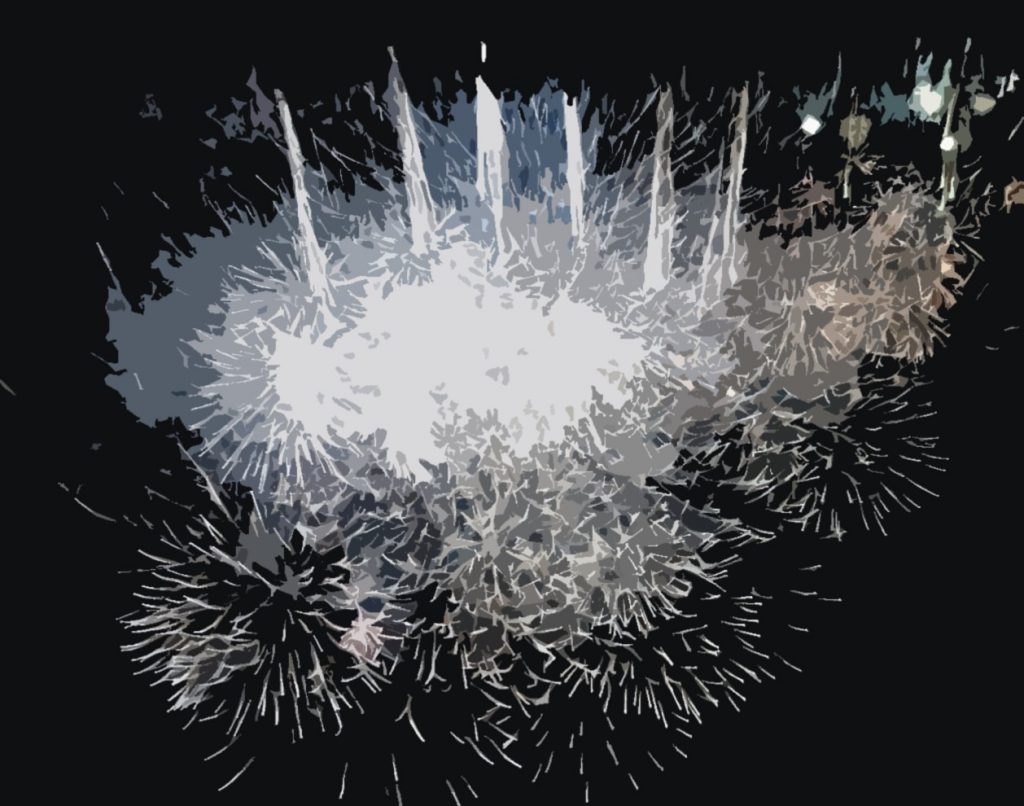シュミットの話をする。シュミットは小太りで丸い眼鏡を掛けた中年の男だった。シュミットにはふたつの仕事があった。ふたつのうちのひとつは町の広場の噴水の前でサックスの演奏をすることだった。シュミットの演奏は町のひとびとから概ね愛されていた。通行人の多くがシュミットの楽器ケースの中に小銭を投げ込んだ。シュミットのふたつ目の仕事は正義の味方だった。貧乏人や困ったひとに手を差し伸べる優しいヒーローだった。町のひとびとはシュミットのことをゴールデンマンという奇妙な名前で呼んだ。僕は幼い頃からシュミットの家族だった。
シュミットがゴールデンマンと呼ばれていた理由はとても単純だった。シュミットの身体に流れていた血液が黄金だったからだ。人間の血液というのは普通赤いものだがシュミットのそれは輝く黄金だった。シュミットはこの黄金を使って多くのひとを助けた。町の路地裏でお腹を空かせたひとを見つけた時などは、ナイフを使って指先を切り、空腹を満たすためのパンと次の仕事を探すためのスーツを買うように言って黄金の血液を渡した。この町にはシュミットのそういった行為に救われたひとが多く暮らしている。ゴールデンマン・シュミットはみんなのヒーローだった。
シュミットの家は町から少し離れたところにあった。シュミットの家には僕とシュミットの他に、シュミットの妹のメアリー、それから何匹もの犬とか猫が居た。そこに暮らしていた犬や猫の多くは人間に捨てられるなどして行き場を失っていたところをシュミットに拾われた子たちだった。人間だろうが動物だろうが分け隔てなくシュミットは優しかった。かくいう僕もシュミットに救われたひとりだ。幼い頃に他所の町からひとりでやってきて、路頭に迷っていたところを、シュミットに助けてもらったのだ。どうして彼は見ず知らずの人間や動物たちに対してこんなに優しいんだろうと僕は時々疑問に思ったけど、尋ねたところでシュミットは答えず、口元の髭を軽く触って笑っただけだった。
冬のある日に強盗事件があった。犯人の男は銃やナイフをたくさん持って銀行に押し入ると百万円を脅し取って車で逃走した。しかしシュミットはひとりで犯人を捕らえた。ゴールデンマン・シュミットは強いヒーローなのでとても強かった。ブルドーザーより力持ちだし新幹線より速く走ることが出来て銃弾も効かなかった。しかしシュミットは捕らえた犯人を警察に引き渡さなかった。犯人が悪い男ではないと判断したからだ。犯人は銀行強盗をしたけど周囲のひとをひとりも傷つけなかったし人質も取らなかった。犯人の男は貧しい男だった。ずっとまじめに働いていたが景気のせいで仕事を失い食べるものもなかったので銀行強盗に走った。シュミットは奪われた百万円を犯人から取り戻したが、代わりに自分の黄金の血をコップ一杯分だけ犯人に与えた。
シュミットの妹のメアリーは可愛い女の子だ。正確な年齢は分からないがきっとシュミットよりも十歳以上は若かった。どうして正確な年齢が分からないのかというとシュミットの家ではメアリーの誕生日会が毎晩行われていたからだ。シュミットの家では春夏秋冬を問わず毎日がメアリーの誕生日会だった。ケーキの上に載せられたロウソクは必ず十五本で増えることも減ることもなかった。メアリーは十五歳の誕生日を迎える前日に交通事故に遭った。その事故のせいで脳に障害を持っており記憶が不自由だった。メアリーはその日一日の記憶を翌日にになるとすべて忘れてしまうのだ。なのでメアリーの生活はいつまで経っても十五歳の誕生日から先に進むことがなかった。シュミットは毎晩、妹の誕生日を祝うためにサックスを演奏した。
夏のある日のことだった。町は大騒ぎでみんなが慌てていた。大きな隕石が地球に迫っていることが明らかになったからだ。隕石はちょうど僕らが住む場所の真上で爆発して町を丸ごと吹き飛ばしてしまうだろうという予報だった。町のひとびとはみんな避難した。僕もメアリーや犬や猫たちを連れて遠くへ避難したがシュミットはひとりで町に残っていた。町のひとびとがシュミットに助けを求めたからだ。避難しても町が吹き飛ばされてしまったらその後の生活が立ち行かなくなってしまう。けれどブルドーザーより力があって新幹線より速く走れるシュミットだったら隕石を受け止めることだって出来るかもしれないとみんなは期待したのだ。
「助けてゴールデンマン!」
「町を救って、ゴールデンマン!」
「我らのヒーロー、ゴールデンマン・シュミット!」
だけど僕はシュミットに残って欲しくなかった。僕らと一緒に避難して欲しかった。いくらシュミットでも隕石を受け止めることなんで不可能に決まっている。町がなくなるのはもちろん嫌だが、シュミットが死んでしまうのはもっと嫌だった。僕らを避難させる前日、シュミットはいつものように家でメアリーの誕生日会を開いた。メアリーのためにサックスを演奏した。ケーキに十五本のロウソクを立ててみんなで一緒に食べた。僕らが避難のバスに乗り込む時、シュミットは僕を呼び止め、避難先でもメアリーのことを頼むよと言って笑った。僕はそれを聞いて悲しい気分になった。どうしてシュミットはいつも自分を犠牲にしてまで他人を助けるの? 僕はシュミットに尋ねた。シュミットは、少し間をおいてから、忘れられるのが怖いからさと、口元の髭を軽く触って笑った。
隕石が降ってきたのは僕らが避難した翌日のことだった。隕石は予報通りに町の真上で大爆発を起こした。町は半分吹き飛んだけど半分は無事なまま残った。被害が予測よりも少なくて済んだのはゴールデンマン・シュミットのおかげだというひとも居たけど、そもそもの予測が間違えていたというひとも居たので真偽は分からなかった。シュミットや僕らが暮らしていた家は無事だったけどシュミットは二度と帰って来なかった。メアリーはシュミットが現れないことを不思議がりながらも、相変わらず毎日、十五歳の誕生日を迎え続けている。メアリーの様子は以前と少しも変化がないように見えたが、シュミットが毎晩、彼女のために演奏していた曲を、時々思いついたように口ずさむようになった。