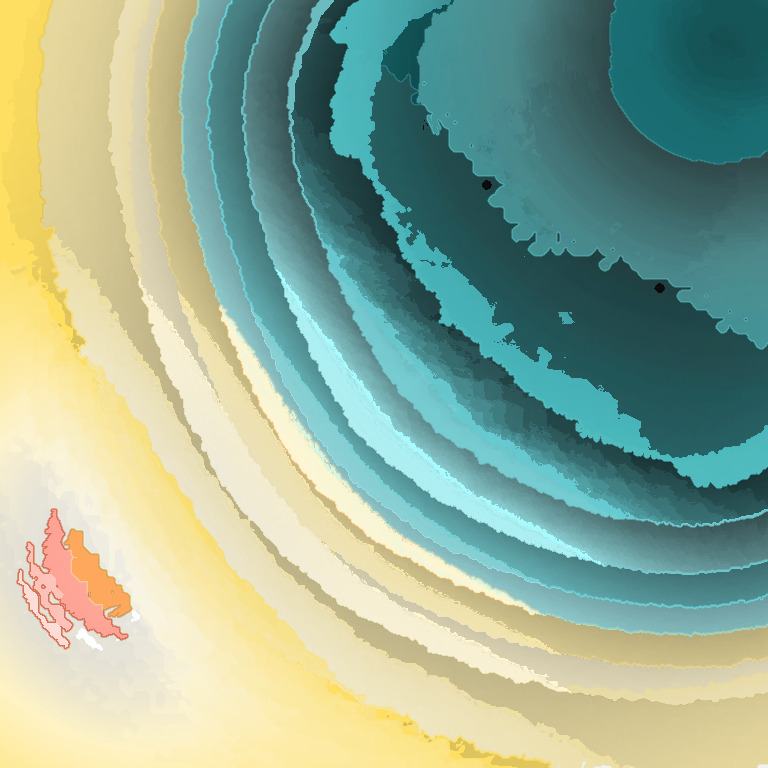
今日もまだ暗いうちに目を覚ました私はベッドを降りてシリアルだけの朝食を摂ると洗顔と着替えと化粧を済ませてから窓辺に置いた観葉植物の鉢にコップ一杯の水道水を与える普段どおりのルーティーンを正確にこなした。仕事のある日の朝に決まりきった行動をすることは私にとって非常に重要だ。フライト前の飛行機に行われる点検と同じで朝の行動を普段どおりにこなすことができればこれから撮影現場に赴く今日の私が“異常なし”であると分かるからだ。もしも一緒に暮らす家族がいれば体調を崩しても「今日あなた具合悪そうだよ」と言ってもらえるだろう。だがひとり暮らしをしている以上は何らかの形で自分の異変を察知する術を持つ必要があるのだ。玄関で靴を履き撮影機材の入ったリュックを背負うと黙ってドアを開け私は出発する。まずは駅を目指す。
駅にたどり着き空いている電車に乗り込めばあとは一時間近く座っているだけで目的地の最寄り駅まで行ける。だだんだだんと規則的な音を立てながら私を乗せた下りの電車は都心を離れて郊外へと走ってゆく。向かいの席に腰掛けている十代と思しき一組の男女は恋人同士だろうか或いは片思いの最中なのだろうか。リラックスした様子でスマートフォンをいじる女の子に対し男の子の方は視線があちこち泳ぎ回ってどうにも落ち着きがない。たまたま居合わせた無関係の他人を見て「ああではないか」「こうではないか」と想像を働かせる癖は私の職業に関係する。私はカメラマンとして生計を立てており主に寄せられる依頼はカップルや夫婦などの在りようを撮影することだ。そして今日これから行う撮影は高校時代からの友人に毎年いちど必ず依頼される特別なものだ。
ところで私は過去に一度も恋をしたことがなく他者から恋心を向けられることも苦手だ。翼を持たない生き物が空を飛ばないように恋をするうえで必要な何かが私の中には存在しないのだろう。だが空飛ぶ鳥を見て劣等感を抱く人間があまりいないのと同じで私も自分が恋愛できないことについて特に引け目を感じる事はない。「恋をしないひとが恋人やカップルを撮ってるんですか」と驚かれることもあるが自分の身に起こりえない事象だからこそ深く知りたいし理解したくてカメラを向けるのだ。目の前のふたりはお互いをどのように想い合いどのような関係を編み上げてきたのだろう? それを自分なりに読み解きながらシャッターを切るのが私は好きなのだ。そしてわたしカップルや夫婦を撮るきっかけになった人物こそこれから撮りに行く旧くからの友人に他ならない。
その友人――アサダは高校時代から恋多き男で常に恋人が途切れなかったのだがひとつずつの交際は長く続かなかった。そんな彼に対し私が最初に抱いた印象は「なんか不思議な生きもの」というもの。当時の私は野良猫とか野鳥といった人間ではない生きものたちを好んで撮影した。じっと観察して尻尾の動きや視線の向け方などから彼らなりの思考や感情や習性を読み取れると嬉しい気持ちになった。だから放課後に女の子と手を繋いで歩くアサダをこっそりと尾行して隠し撮っていたのも野良の生きものを撮影するのと同じ感覚だった。幾度目かの尾行でついに隠し撮りがバレてしまった時はさすがの私も責められることも覚悟したのだが、私が撮った写真を見た彼は逆に「自分が相手に、相手が自分にどんな目線を向けていたのか分かって面白い」と喜ぶばかりだった。
それ以降アサダは定期的にその時々の恋人を伴って私が構えるカメラの前に立った。恋するアサダを撮り続けて分かったことは彼は恋多き男でこそあるが決して遊び人ではないということだ。恋人が変わるたびにその人に合わせた目線の向け方や声のかけ方や距離感をゼロから模索しているのだとカメラ越しにも分かった。アサダに対する理解を深めていくにつれて私自身も自分のことを彼に話すようになり「自分はどうやら恋ができないらしい」とある時うちあけた。うちあけた時のアサダの反応は昨日の晩に食べたものを聞かされたかのような簡素なもので私はそれをありがたいと感じた。私は誰とも恋愛をしないがそれは彼との友人関係を続けることになんの影響もないのだ。アサダとの親交は高校を卒業して別々の学校に進学してからも続き恋する彼を私は撮り続けた。
私とアサダは二年間ほど一緒に住んでいた。当時の私はカメラマンとしての仕事が思うように増えず金銭的に行き詰まりつつあった。そんな私に「うちに住みな」とアサダが声をかけた。共同生活となったマンションは彼が恋人と同棲するために借りたものだった。だが肝心の同棲が実現するより前に恋人との関係が破局してしまい2LDKの間取りを彼曰く「持て余し」た。かくして始まった共同生活は気楽なものだった。共通の知人が揶揄したような肌の接触はもちろん起こらなかったし相変わらず恋多かったアサダはたびたび女性を家に連れ込んだ。それでも「いってきます」「ただいま」を言い合ったり、具合が悪い時に気づいてくれる相手が傍にいるというのはなかなか悪くなかった。共同生活は彼の結婚が決まるまで続いた。その頃には私の仕事も充分増えていた。
改札を出ると一年ぶりに会うアサダとその家族が私を出迎えた。今年でそれぞれ五歳と三歳になった彼の娘たちは前回見た時よりずいぶん大きくなった。駅の傍にある広い公園を回りながら一時間ほどかけてアサダの家族写真を撮影した。アサダが結婚してからというもの私たちは以前のように頻繁に顔を合わせることこそなくなったが彼は毎年この季節になると私に撮影を依頼してくれる。彼は家族に対し「おれがいちばん信頼しているカメラマンだ」と私を紹介する。彼が家族に向ける視線は歳を重ねるごとに深く静かな慈しみの色に満ちていくようだ。かつて恋多き男だったアサダが今やすっかり家族一筋だが彼の恋愛を高校時代から撮り続けた私にとってそれは少しも意外なことではない。数多の恋と失恋を経ながら彼はずっと家族になれる相手を探していたのだろう。
撮影後にはアサダの自宅を尋ねてランチを振る舞われた。いま現在のアサダの住まいは私と共に暮らしていたところよりも二回りほど広い。リビングの棚に並べられた五つのデジタルフォトフレームには家族写真がスライドショーで代るがわる表示されておりその中には私が過去に撮影したものも多く含まれていた。家具や家電は結婚を機にどれも新調したとのことで私と一緒に暮らしていた頃の気配はひとつも残っていない。昼食を食べ終えると「また来年」と言い合ってから彼ら家族の住まいを後にした。ひとりで住まう自分の家へと帰る。
翌朝も私はまだ暗いうちに目を覚まし今日の私が“異常なし”であることを確認するために普段どおりのルーティーンを実行に移していく。ひとりで暮らし続ける私が自分の身体や心に起こる異常を見つけるにはこのルーティーンが必要不可欠だからだ。ベッドを降りてシリアルだけの朝食を摂ってから洗顔と着替えと化粧を順に済ませる。それから窓辺においた観葉植物にコップ一杯の水道水を与えようとした時、私は思わず手を止め「あれっ?」と声を漏らした。普段どおりではないことがそこに起こっている。観葉植物が丸く小さな蕾をつけていたのだ。私はそっと指を伸ばして蕾に触れてみた。それはまだ硬くてひんやりとしていた。




