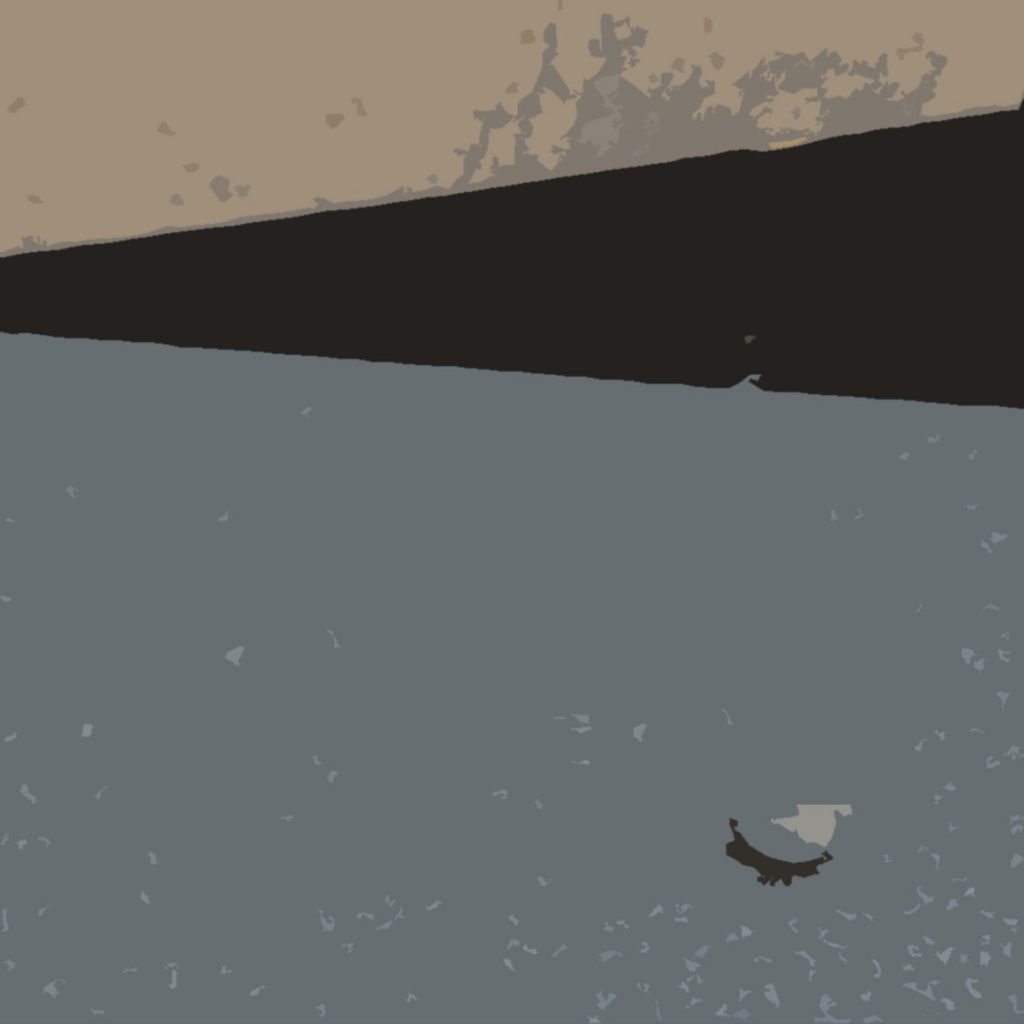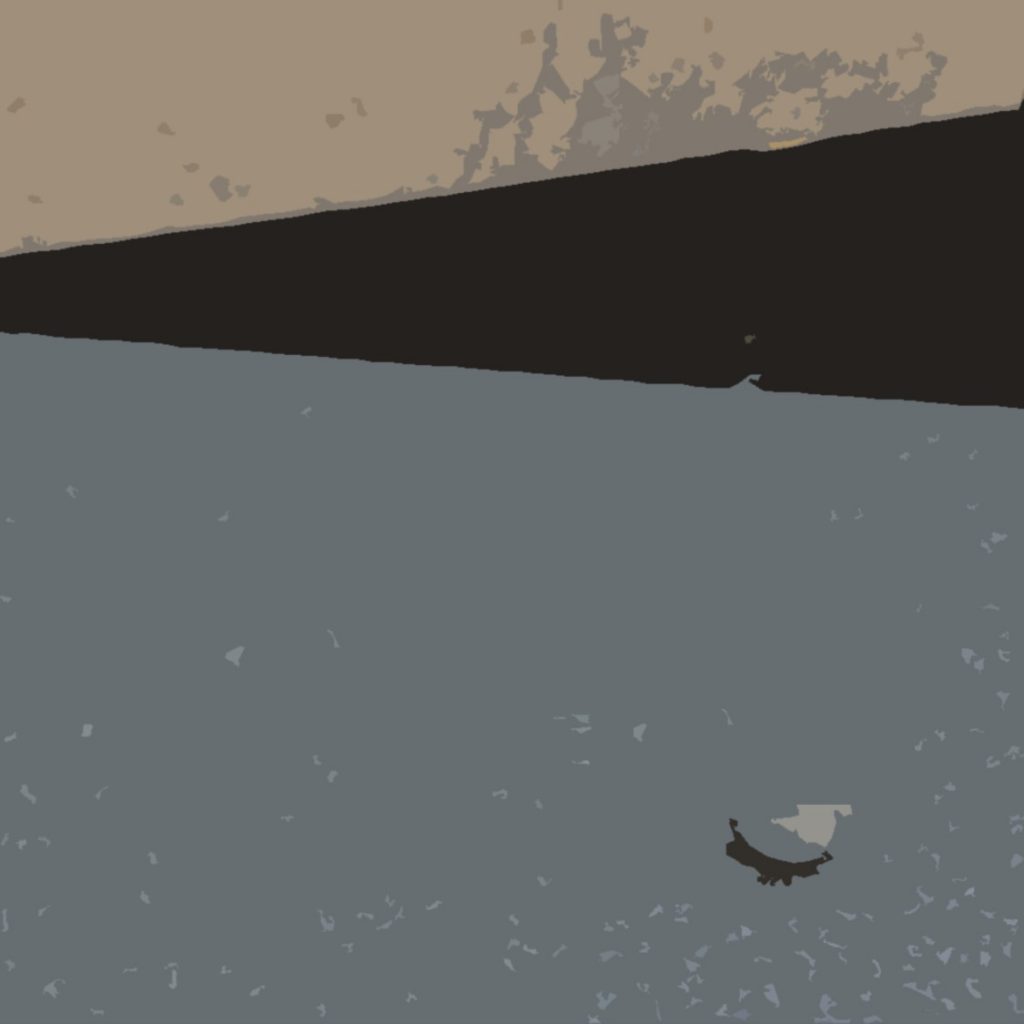数学の授業中にわたしは鉛筆を削った。カッターナイフを使って削って削って削った。必要以上に細く鋭利に削った。鉛筆に対して悪い事をしているような気分だったがわたしはやめなかった。教室の中は暖房が利いていたし窓の外はカラッと晴れていたので鉛筆を削るにはちょうどいい日和だと感じた。初老の数学教師が黒板に板書をしていた。わたしはそれを書き写すこともせずに鉛筆を削り続けた。わたしは勉強が苦手だし学校自体もあまり好きではない。だけど不登校になるほど嫌なわけではない。とにかく退屈なのだ。不登校になるほど嫌な学校なら良かったのにとわたしは考えた。鉛筆の芯を可能な限り鋭く尖らせると、また削るために芯をへし折った。乾いた音が鳴った。
わたしは毎日トモエさんの家に通った。トモエさんの家は学校からほど近い場所にあるアパートの二階だった。トモエさんは十九歳でひとり暮らしをしていた。耳にはたくさんのピアスを付けており髪は真っ赤だった。部屋の中には葉っぱの赤いポインセチアの鉢植えが幾つも置かれていた。トモエさんは不幸なひとだった。遠く離れた田舎の町で生まれ育ったが思春期を迎える頃になると父親から毎日のように酷い事される生活を送っていた。だからひとりで地元を離れて東京へ逃れてきた。わたしはトモエさんに対して憧れを抱いた。辛い境遇と戦いながらも負けることのない生き方を格好良いと感じた。
校門を出て駅への道を歩いた。日が暮れかけており空が真っ赤だった。駅の傍にはひとがたくさん居た。青いタイルが敷き詰められた遊歩道を歩きながらわたしは指で銃の形を作った。指で作った銃を使って道行くひとびとの背中に何度も発砲した。心の中で、ばーんっ、ばーんっ、と銃声を叫びながら無差別に銃撃した。わたしは家に帰るのがとても憂鬱だった。わたしのお父さんは優しい。お母さんは少し厳しいけどやっぱり優しいひとだ。そしてわたしは彼らに愛されている。不自由のない生活をさせてもらっている。けれど退屈なのだ。自分の家族が口も利きたくないぐらい酷い家族なら良かったのにとわたしは時々思う。そうすればわたしもトモエさんのように、ひとりで遠くへ逃げて暮らせるのに。指の銃で何度もひとを撃った。指の銃からは弾が出ないから何回撃ったところでもちろん誰も死んだりなんかしない。
雪が降った日だった。わたしはいつものようにトモエさんの家を訪ねた。部屋の様子はいつもと違っていた。幾つも置かれていたポインセチアの鉢植えはひとつ残らず割れて砕けて床に散らばっていた。ポインセチアの赤い葉っぱは土で汚れていた。食器も同じようにすべて壊れていた。お酒の缶が無数に転がっていた。トモエさんはベッドの上に居た。カッターナイフを右手に持って羽毛布団に何度も突き刺していた。トモエさんは酔っぱらっていた。無残に裂かれた布団の羽毛が宙を舞っていた。お酒の匂いと濡れた土の匂いが部屋に充満していた。トモエさんは泣いて笑っていた。
夜中に目を覚ました。時計を見ると午前の二時だった。セーターを着て分厚いコートを羽織った。カバンを持って自分の部屋を出た。台所に立ち寄って白いお皿をカバンの中に入れた。お父さんが大切にしているグラスを持っていくつもりだったけど考え直して白いお皿にした。わたしは家を出た。ひとりで児童公園に向かった。途中の道では誰にもあわなかったし児童公園にも人影はなかった。わたしはもうトモエさんのようになりたいと思うことはなかった。これから先も思わないだろう。今の生活は退屈だけど死ぬほど嫌だというわけでもないから、わたしはきっとよほどのことが起きない限りはどこへも行けないのだ。カバンの中からお皿を取り出した。滑り台の下でお皿を地面に落とした。落ちたお皿はガシャンと音を立てて壊れた。