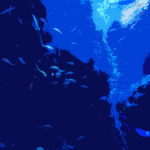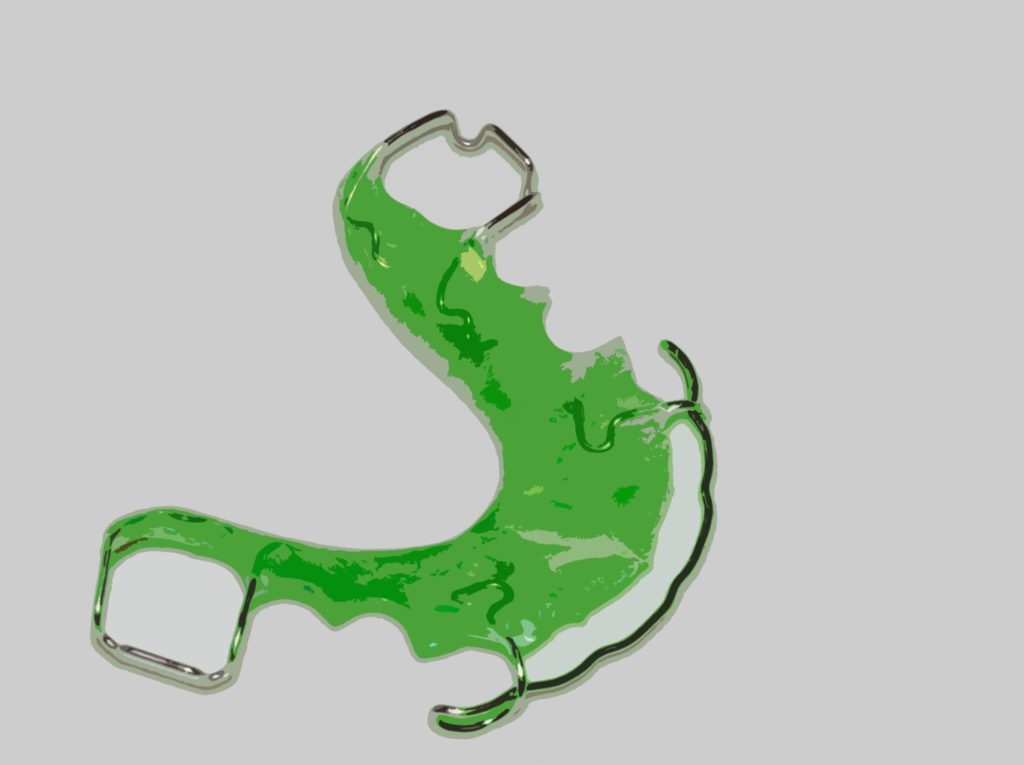
「あたし美人になりたい」と、高校二年の春の終わりにリーコはそう言った。
わたしたちが通う学校から徒歩で二十分ほどの場所にあるコーヒーチェーンの奥の席で言った。最初わたしは聞き間違いかと思った。リーコは容姿がとても醜いからだ。酷く乱れた歯並びだとかスチールウールを思わせるチリチリした癖毛はまるで手入れをされたことのない野良犬みたいだった。おでこや頬には絶えず無数のニキビが散りばめられていたし、脂肪に埋もれた両目はそれでどうしてものが見えるのだろうと思うぐらいに細くて、黒縁眼鏡のぶ厚いレンズは皮脂や埃でいつも曇っていた。
なんでもリーコは恋をしたのだそうだ。恋した相手の気を引くために美人になりたいそうだ。恋の相手は彼女の家からほど近い書店で四月の末から働いている若い男だという。接客の際に関西訛りの喋り方をするからおそらく上京してきたばかりの大学生だろうと彼女は推測していた。自分にとってこれは初恋なのだと照れくさそうにリーコは話していた。それを聞いたわたしはほとんど溶けたアイスコーヒーの氷をプラスチックのストローの先でカラカラと鳴らしながら、まぁ頑張ってみたら、とだけ伝えた。
リーコがその話をわたしにした理由はとてもシンプルだ。リーコには友だちがわたししか居なかったからだ。同学年の女子の多くは日頃から可能な限りリーコの存在に気づかぬふりをして過ごしていた。彼女たちの目は公園にダンボールを敷いて眠るひとたちを見た時と同じ動きでリーコのことを避けた。なぜならリーコが醜かったからだ。男子に至ってはもっと残酷だった。リーコに関わる際の彼らは、例えば定食屋で前のお客さんが残していった残飯とか、冷蔵庫の中で腐っていた賞味期限切れの肉とかに対して抱くような類の嫌悪感を顔に浮かべていた。それもリーコが醜かったからだ。
そういうわけでリーコには友だちがわたしだけしか居ない。悩みを相談したり楽しいことを共有したり「一緒に帰ろう」と声を掛けられる相手が他に居ないのだ。それでもわたしはリーコを蔑む級友たちのことを軽蔑したりはしない。だって彼らがリーコを蔑む理由とわたしがリーコの友だちでいる理由は同じなのだから。リーコが醜かったからだ。わたしがリーコの友だちで居るのは彼女がわたしより醜かったからだ。
翌週になり彼女の不揃いな乱杭歯に銀色の矯正器具が着いているのを見つけるとあたしは苛立った。「あたし美人になりたい」とリーコは再び言った。歯の矯正は順調にいけば約一年後に完了するのだという。そのタイミングで意中のひとに告白するつもりなのだとリーコは宣言した。
幼い頃のわたしは自分のことを美人だと思っていた。同じ家で暮らしていたおじいちゃんが何かにつけてわたしの容姿を褒めそやしたせいだ。お酒を飲みながらわたしの頭をがしがしと撫で「こんな美人は見たことがない」とうるさく笑うのが彼の日課だった。テレビ画面にアイドル歌手が映れば「お前のほうが何十倍か美人だ」と言ってわたしの背中を大きな手のひらで叩いた。そんなおじいちゃんの言葉をわたしはあまりにも素直に受け取りすぎた。美人という言葉はわたしの自信でありアイデンティティになった。
だが実際のところわたしはちっとも美人などではない。孫可愛さに盲目同然だった年寄りの言葉をどれだけ真に受けて勘違いしたところで美しいひとに育つことなどできるわけがなかった。わたしがそのことに気づいたのは思春期にさしかかり教室の中で恋の話題があがり始めた頃だ。同級生からの視線、特に男子からの「誰々は可愛い」「誰々はブスだ」という評価は、ほんの少しの容赦さえなくわたしに現実を投げつけ、自信を打ち砕いた。砕かれた自信の残骸はコンプレックスとしてわたしの中に残った。中学校を卒業する少し前におじいちゃんが死ぬと、わたしのことを美人と呼ぶひとはいよいよ世界にひとりも居なくなった。
こうしてわたしは美人であることをすっかり諦めた。諦めるしかなかった。だからリーコが美人になりたいと言った時にわたしは苛立った。わたしよりも醜いリーコにそんな言葉を吐く資格などあろうはずもないと、叫びたいほど気持ちが波立った。
リーコの容姿は時間と共に変化していった。特に大く変わったのは夏休みの前後だ。夏休み中にアルバイトをして資金を手にしたリーコはチリチリだった髪の毛にストレートパーマを掛けた。メガネを外してコンタクトレンズに変えた。その状態で始業式の学校に現れて周囲を驚かせた。決して美人ではないが同級生の言葉を借りると「ずいぶんマシ」な姿かたちになった。その後も彼女は徐々に変わり続けた。スキンケアやジム通いを始めるとニキビは数を減らし身体も引き締まって脂肪の中にうずもれていた両目は徐々に開いていった。歯の矯正も順調に進んでいる様子だった。
何割かの同級生はリーコへの態度を大きき変化させた。以前のように避けられることは少なくなり「どうやって痩せたの」とか「美容室どこ行ってるの」などの言葉を掛ける子たちが出てきた。それでもリーコがホームルームの後に「一緒に帰ろう」と誘うのはいつもわたしだった。
リーコの見た目が良くなるにつれてわたしは彼女と一緒に過ごすことを苦痛だと感じるようになっていったのだが、だからといって自分から距離を取ってしまうというのも、リーコなんかに負けを認めてしまうように思えて、それだけはできなかった。だが一方でこの期に及んで勝ちだの負けだのと考えている自分がどれだけ薄汚いかということも薄々分かっており、分かっているだけにいっそう苦しかった。
そうしてわたしたちは三年生の春を迎えて受験生になった。ある晩自宅で英単語の暗記をやっているとリーコからのメッセージがスマートフォンを鳴らした。メッセージには「あのひとにフラれちゃった」と短く書かれていた。気がつけばもうリーコが歯の矯正を始めてから一年が経過していた。
翌日は土曜だったがわたしたちはいつものコーヒーチェーンで会う約束をした。向かう途中の電車の中でわたしはニヤついていた。どう? 思い知ったでしょう。ちょっと努力しただけであんたなんかが美人になれるわけないんだ。だってわたしが諦めたんだから! あんたよりマシなあたしがちっとも美人じゃないのに、それより醜いあんたなんかが美人になれるわけないじゃん! 一年越しの告白がみじめに失敗して、きっとさぞかし落ち込んでいるであろうリーコの傷口を、どんな言葉で抉ってやろうかと思いを巡らせた。
それなのにコーヒーチェーンで落ち合ったリーコの表情は晴れ晴れとしていた。普段目にする制服姿ではなくグレーのカーディガンを羽織っており顔には薄っすらと化粧までしていて、なんだか大人びた雰囲気さえ湛えているようだった。決して美人といえる水準に達したわけではない。けど一年前に同じ場所で「あたし美人になりたい」と言った時のリーコとは似ても似つかなかった。
「確かに告白は失敗しちゃったけど」と、穏やかな、穏やかな調子で、リーコはわたしに言った。「この一年、今日は昨日より少し綺麗になった、きっと明日はもっと良くなれるっていう実感がずっとあって、あたしなんかでも良くなれるって思えて、それが楽しかった」すでに矯正器具は外れており、綺麗に並んだ白い歯がこちらを覗いていた。わたしが来る途中に考えていた酷い言葉たちは、頭の中でぐちゃぐちゃに溶解して、形を為さなくなった。
今年の梅雨は例年よりも少し早めに明けた。放課後になり学校を出たわたしとリーコはバスに乗り込みふたりで街に向かった。あともう少しで高校最後の一学期が終わる。一学期が終わり夏休みになったら受験に向けた夏期講習が始まる。夏期講習には私服を着ていくので、今日は一緒にで服を選びに行く。少し気が早いが、進学したら化粧もするようになるので、そのために必要なものも幾つか買っておいて夏の間に少し試してみたい。

あとがき
「他人から見て優れたものでありたい」という気持ちと、「昨日の自分より良いものでありたい」という気持ち。前者に軸足を置くべき時もあれば、後者の方が楽な場面もきっとあるのでしょう。とはいえどっちも自分の足ですから、いい塩梅で使い分けたいものですね。
2019/07/19/辺川銀