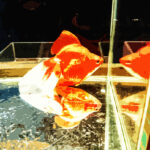目が覚めるとベーコンの焼けるにおいがした。ベッドを降りてリビングに行くと朝食の支度をしていたナツノさんがぼくに「おはよう」と声をかけた。「おはようナツノさん」とぼくもそれに応じた。こんな生活が果たして自分に相応しいのだろうかとぼくは考える。ベランダでは鉢に植えられて丁寧に育てられた植物が日差しを浴びて花を咲かせている。ぼくとナツノさんは向かい合って食卓につき「いただきます」を言う。駅前のパンで買ってきたのだというクロワッサンをかじる。こんな生活が果たして自分に相応しいのだろうかとぼくは考える。今日はナツノさんもぼくも仕事が休みだからふたりで出かける約束をしている。映画を見てからお昼ご飯を食べてそのあとはデパートで買い物をする予定になっている。「晴れて良かったねえ」と目玉焼きの黄身をフォークで刺しながらナツノさんは子どもみたいに笑う。こんな生活が果たして自分に相応しいのだろうかとぼくは考える。朝食を済ますとぼくは洗面所で歯を磨いたり髭をそったり洗顔したりする。鏡に自分の姿をみてぼく自身であるにもかかわらず何を考えているのかわからないなと思う。こんな生活が果たして自分に相応しいのだろうかとぼくは考える。こんなにすばらしいのは分不相応じゃあないかと。
かつてのぼくの生活はたとえるならば沼の底だった。中学校では教科書やノートや筆箱が何度もなくなった。新しいのを買いなおしてもすぐになくなるから机の上になにも置かずに授業を受けていた。だから授業の内容はちっとも分からなかった。かつてのぼくの生活はたとえるならば沼の底だった。だけどいちばん気の毒だったのはぼくのお父さんだ。血のつながらない子どもであるぼくの面倒をみなければならなかったからだ。お父さんは「血のつながらない子どもの面倒をみなければならないおれはなんて気の毒な男なんだろう」といつもぼやいていた。かつてのぼくの生活はたとえるならば沼の底だった。大人になり働き始めると平日よりも休日のほうが憂鬱に思えた。仕事がない日に何をすればいいのかさっぱり分からなかった。そのことを同僚に話すと「それは死んでいるのと同じだ」とひどく心配された。かつてのぼくの生活はたとえるならば沼の底だった。毎日まじめに仕事をしていたのにある日とつぜん身体が上手くうごかなくなり働けなくなった。上司のすすめで受診した病院では精神の病気であるといわれた。仕事を離れても動かなくなった身体はなかなかもとに戻らず家からほとんど出られない日々が一年ほど続いた。
ナツノさんと映画を見にでかけた。大きな賞を獲った海外の映画だった。国内では今日から公開されるので街にはあちこちにポスターが貼られていた。映画好きのナツノさんは公開されることを楽しみにしていた。劇場はほぼ満席だった。けれどずいぶん前からナツノさんが予約をしてくれていたので真ん中よりも少し後ろの良い席に座れた。幕があがる前に僕は劇場に入る前にコンビニで買っておいたペットボトルのお茶を一口飲んだ。ナツノさんもそれを手にとって飲んでから蓋を締めた。映画の主人公は麻薬中毒の男だった。周囲のひとたちに支えられながら中毒から立ち直ろうと藻掻く話だった。けれど大切なひとたちと少しずつ積み上げてきた麻薬のない日々は小さな誘惑ひとつで再び崩壊した。そういう男の人生が約二時間にわたって描かれた映画だった。映画が終わり場内が明るくなるとお客さんたちは席を立って出口に向かっていく。僕とナツノさんはいちばん最後に立ち上がって劇場をあとにした。それから近くのカフェに入って昼食を済ませた。店内のスピーカーからはさきほど見た映画の主題歌が流れていた。
沼の底から這い出るときの感覚がすきだ。たとえば中学時代にぼくのぼくの教科書やノートや筆箱を盗んだ同級生を殴ってやれたとき。もちろん当時の担任やお父さんや相手の親からはひどく叱られた。だけどそれからというものぼくの教科書やノートや筆箱はなくならなくなった。沼の底から這い出るときの感覚がすきだ。たとえば休日にすることがないぼくに「それは死んでいるのと同じだ」と言った同僚が「もう使わないから」とペイントソフトのCD‐ROMを譲ってくれたとき。それまで絵を描くという行為そのものを小中学校の授業の他ではしたことがなかったけどペイントソフトは触れば触るほどできることや描けるものが増えていき自分がどんどん自由になっていくようだった。ぼくにとってはじめて趣味というものができた瞬間だった。沼の底から這い出るときの感覚がすきだ。精神が病気になり働くことも家から出ることもできなかった時期は起きている時間のほとんどをペイントソフトの練習のために使った。ペイントソフトに触れているときは病気のことや仕事のことや将来のことを考えなくてもよかったので曜日の感覚も昼夜の感覚も薄れていくなかでイラストをつくり続け出来上がったものはSNSに公開するという日々をしばらくすごしていると「いいね」とかコメントとかをもらえる数が次第に増えてきた。そしてあるとき「イラストの仕事をお願いできますか?」と連絡がありその連絡の主がナツノさんだった。沼の底から這い出るときの感覚がすきだ。できれば何度でも味わいたいほどすきだ。でもそのためには今の生活を捨ててまた沼の底に沈まなければならない。ぼくはさきほどの映画を見て麻薬中毒者の気持ちがよくわかると思った。
ファーストフード店を出たぼくとナツノさんは予定を変更して周辺を散策した。とても気持ちがいい天気なのですこし歩きたいとナツノさんが言ったからだ。ナツノさんは歩きながら野良猫に話しかけたりぼくにそのへんの雑草の名前を教えたりしてにこにこ笑っていた。ぼくは雑草の名前など気にしたことがなかったのでナツノさんに教えてもらったことを嬉しいと思った。ナツノさんとの生活を捨てることを僕は考える。それを実行したらきっとつらいだろう。寂しいだろう。後悔するだろう。だからこそだ。沼の底から這い出るときの感覚がぼくは好きなのだ。沼の底から這い出るためにはつらく悲しい沼の底に何度だって沈まないといけない。あの感覚を味わうためなら大事なものをすべて放りだして沼の底に何度だって沈まないといけない。「さっきの映画」とナツノさんが言ったのは公園のベンチに並んで腰掛けてぼくがペットボトルのお茶を飲んでいるときだった。「さっきの映画は期待していたほどじゃあなかったね」とナツノさんは続けた。「わたしはもっと面白い映画をたくさん知ってるよ」そう言ってぼくの手からペットボトルを抜き取る。「家に帰ったら一緒に見ましょうよ」そう言うとペットボトルに残った中身をぜんぶ飲み干した。

あとがき
幸せになったはずなのに、つらくかなしかったはずの日々が何故か誘惑してくることって、きっと珍しいことではないんだなと思います。
2024/04/25/辺川銀