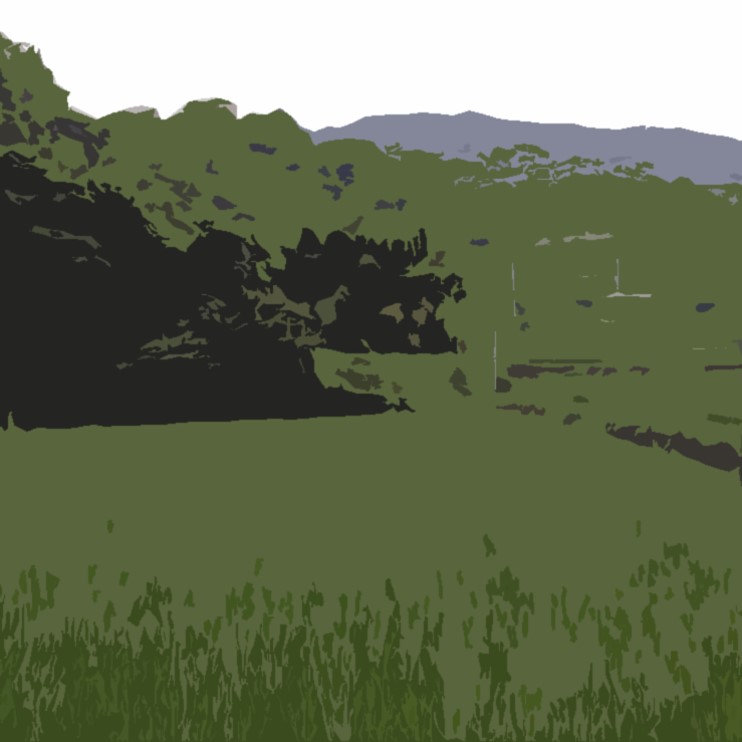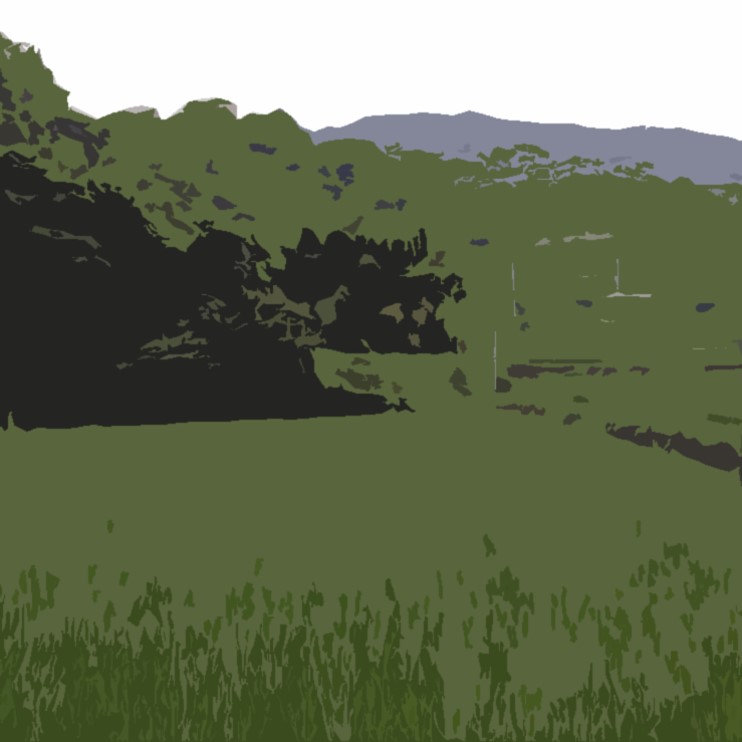緑色をした田園地帯の真ん中を通る水溜りの多いあぜ道で、あいつはいつも石を投げつけられた。新品の可愛らしい洋服を着て学校にやって来ても、帰る頃には決まってぼろぼろになっていたし、華奢な肩とか白い頬は常に傷だらけだった。どこからしらから流血しているのは日常茶飯事だったし、気絶するまで蹴られることも、顔に大きな紫色の痣を作っていたことだってあった。けれどどんなに酷い目に遭っても、あいつは自身は決して怒ったり泣いたりすることなく、前歯が一本欠けた口元を緩めて、へらへら笑っていた。強がっているとか我慢しているふうでもなく、あくまで本心から笑っている様子だったので、あいつの笑顔を目にするたびに、おれは胸を痛めた。おまえはいったい何がそんなにたのしいんだ? と、ある時あいつに訪ねた。だけどあいつは、教えてあげないよ。なんて言って、やっぱりへらへら笑った。
あいつが石を投げつけられるのはあいつがハエだからだ。ハエは一見普通の人間と区別がつかない見かけをしているが、洋服を脱ぐと背中に一対の羽根をもっており、そこだけ違っている。ハエはだいたいクラスにひとりかふたりぐらいの割合で居て、人間の子どもたちと同じように学校に通っているのだけど、十中八九仲間外れにされるし、罵られたり、殴られたり、物を盗られたりとかするのだ。彼らに暴力を振るうことは決まりでも認められているから、ためらうひとは少ない。ハエは人間と同じ形をしているが、人間よりもずっと劣った汚い生き物だと、一般的にはいわれる。
だけどあいつは図工の時間に誰より上手に絵を描くことが出来る。田園の風景を写生すれば飲み込まれてしまいそうになるほど綺麗な作品を描いたし、人物の姿を描写すれば紙の中から飛び出してきて喋り出しそうなほど表情豊かに描いた。だからおれは、あいつの描く絵を見てからというもの、あいつや他のハエたちに対して、暴力を振るったり罵ったりすることが出来なくなってしまった。ハエは人間よりも下等で卑しいものだとみんなは言っているけれど、あんなに凄い絵を描ける奴が他の奴より劣っているだなんて、おれにはどうして思うことができなかった。ある日あいつは利き手に石をぶつけられ骨を折られてしまった。これじゃあしばらく絵は描けないよなぁと、あいつはおれに、へらへら笑って言った。
ある雨の日。おれは傘を差し、田園地帯の真ん中を通るあぜ道を歩いて、連中のもとへ向かった。連中は学校のクラスメートなのだが、このあぜ道で待ち伏せをして、ハエが通るたびに石を投げつけるという遊びを、日々の娯楽にしているような奴らだ。連中の遊びには、ハエの身体のどこの部分に石を当てられたら高得点を得られるなどといったルールが細かく決まっていた。奴らはこの暴力を純粋な娯楽として楽しんでいるのだ。おれは意を決して、あいつに石を投げるのをやめてくれないか。と、連中の中で最も大きな身体をした、リーダー格の男子に向かって言った。すると連中はゲラゲラと声を上げながらおれの周りをぐるりと取り囲んだ。雨は降り続いていた。おれが差していた傘は十数秒後ぐにゃりと折れ曲がった。
雨が降るあぜ道の真ん中でおれは泥だらけになりながら仰向けに倒れていた。連中はおれのことをぼろぼろになるまで殴った。身体中が痛んで、なかなか立ち上がれず、あいつはいつもこんな目に遭っていたのかと、ぼんやり考えた。しばらくしてからあいつはやって来た。半袖に半ズボンという夏らしい服装をしていたけど、既に他のところで酷い目に遭わされた後のようで、露出した肌のいたる部分が青あざだらけだった。利き手の右腕はやはりギプスで固定されており、それが何より痛々しく映った。きみこんなとこで何してんの? と、あいつは尋ねてきたけれど、おれはそれには答えず、雨が傷に染みて痛えよ。とだけ言った。
痛くても雨は降るよ。と、あいつは前歯が一本抜けた口元を緩めてへらへらと笑った。