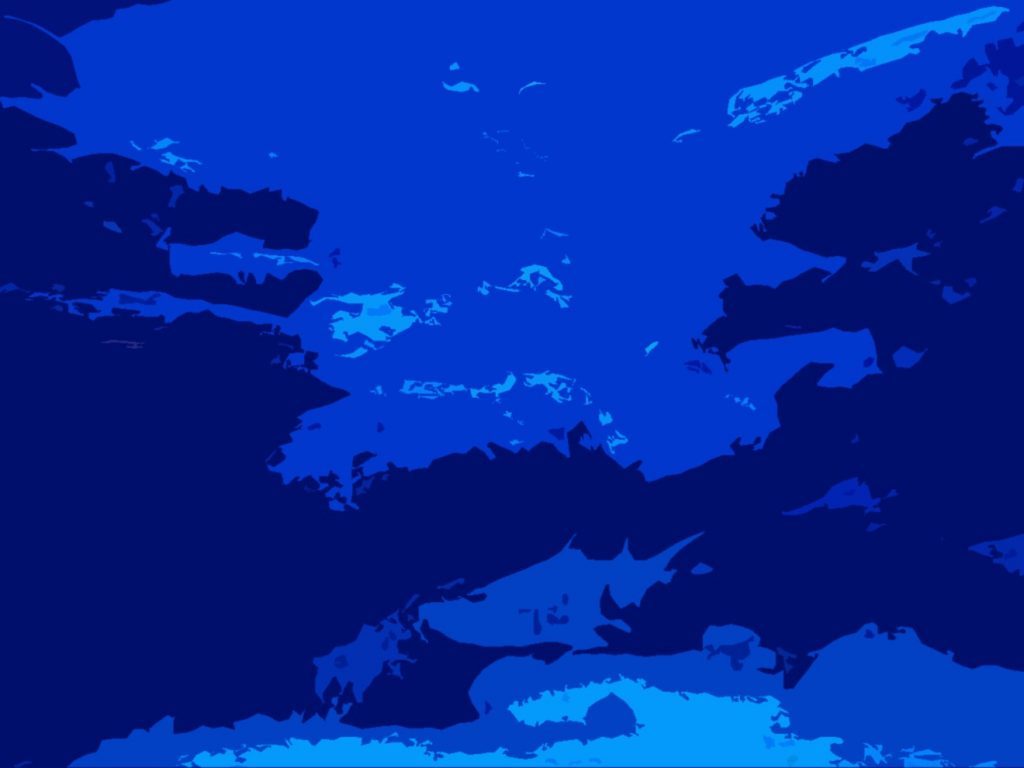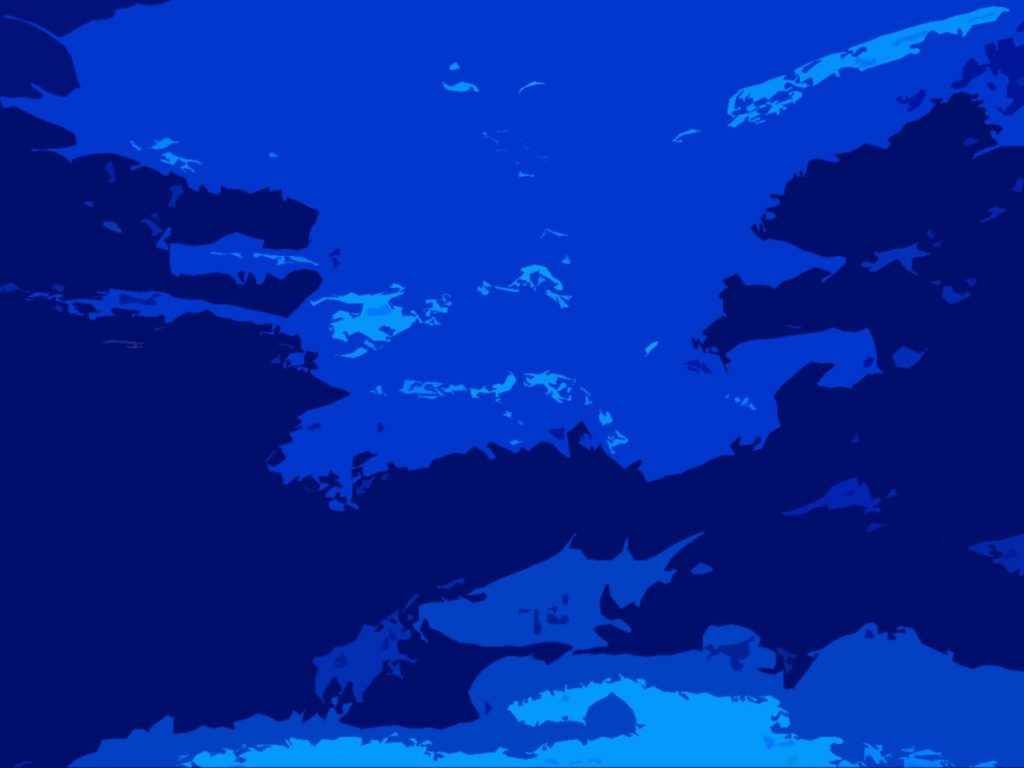丘の上には古い屋敷がある。僕はひとりでそこに暮らしている。毎朝必ず暗いうちから目覚める。ベッドの上で身体を起こすと胸に繋いだ電源コードを抜く。扉を開けて自分の部屋から出る。階段を降りて玄関ホールへ行く。壁に飾った父の写真に両手を合わせて祈る。玄関を出て外から施錠する。まだ太陽が昇っていないが晴れた空にはオーロラがなびいているので明るい。館の庭には発電用の大きな風車が三台そびえている。がらがらと音を立てて風車は回転する。僕は川沿いの道を歩いて丘を降っていく。
丘を降りると白い浜辺がある。東の空から朝日が昇り始める。太陽が出るとオーロラは見えなくなる。海の表面がきらきら光って揺れる。僕はまっすぐ海へ入っていく。水の温度は非常に低いが僕の身体は金属なので凍えることはない。細かな泡をかき分けながら僕は泳いで深いところへ潜る。僕の両目は水の中でも周囲がはっきり見える。海の底には町が沈んでいる。コンクリートの高層ビルが見渡す限りに連なる通りがある。アスファルトの道路や鉄の線路もある。駅前に広がる広場には止まった時計がある。生きているのものはひとつも見当たらない。
海に沈んだ廃墟の街をひとりで散策する。僕の身体は機械で出来ているから呼吸は必要ない。廃墟の町はとても大きく毎日のように訪れたって見飽きることはない。ビルとビルの間を気の向くままにぷかぷか漂って彷徨う。適当な建物の窓硝子を外して内部にお邪魔する。誰も居ないので大抵の場所には自由に立ち入れる。写真やビデオのデータが入ったディスクやメモリーカードを見つけることがある。持ち主の姿は見当たらないので拾って持ち帰る。修理できそうな機械や使い方のわからない道具なども時折発見する。余裕があればこれらも拾って帰る。
散策が済んだら泡と一緒に上へ浮かんで行く。海の表面から顔を出した時には既に夜が来ている。頭の上では淡い色をしたオーロラがなびいている。遠くの方から氷が軋んだ音が聞こえてくる。僕は砂浜に上陸する。身体は濡れている。川沿いの道を歩いて丘を登って行く。館に着く頃には身体も乾いている。錠を外して玄関ホールに入る。壁に飾った父の写真に両手を合わせて祈る。階段を使って二階へ行き自分の部屋に戻る。廃墟の街で拾ったものを机の上に広げる。ディスクが五枚とメモリーカードが三枚。そしてヒビが入ったソーラーパネルが一枚。
五枚拾ったディスクの中から一枚を手に取りプレイヤーに差し込む。このプレイヤーも廃墟の町から持って帰って修理したものだ。液晶画面にビデオが再生される。あの町が海に沈むより前の映像が収められている。立ち並ぶビルは廃墟ではなく舗装された道には無数の人間が行き交う。映像の中心に収められているのは幼い少女の姿だ。母親に手を引かれてはしゃぎながら歩き回っている。時折聞こえる音声から、撮影したのが父親なのだと分かる。あまり長い映像ではなかったが画面に映る人間の多くはにこにこ笑っている。彼らの様子を僕はまじまじと見つめる。
いつものように暗いうちから目覚める。ベッドの上で身体を起こすと胸に繋いだ電源コードを抜く。部屋の窓枠がカタカタ揺れている。風が轟々と吹きすさぶ音が聞こえる。カーテンを開けて外の様子を見る。分厚い雲が空を覆って渦を巻いている。数秒ごとに雷が落ちて空気を震撼させる。大粒の雨が斜めに降りつけている。嵐だ。今日も沈んだ廃墟に出掛けるつもりだったがこれでは外出できない。僕の身体は機械で出来ているからそこそこ頑丈だが嵐の時に外出するのは危険だ。嵐はこの世で最も怖ろしい。強い嵐は人間の町さえ海に沈めてしまう。
扉を開けて自分の部屋から出る。エレベーターで地下深くにある制御室へと降りる。パネルのボタンを幾つか弄って庭にそびえる発電用の風車を地下に格納する。嵐にやられて風車が駄目になったら電気が作れない。電気がなければ僕は死んでしまう。風車を仕舞うと一安心して玄関ホールへ行く。壁に飾った父の写真に両手を合わせて祈る。僕は父のことをあまり詳しく知らない。父は科学者で機械の研究をしていた。僕は父の手によって作り出されたが生まれた時からずっと眠っていた。目覚めた時には父は居なかった。僕が父について知っているのはたったこれだけだ。
嵐のせいで外出することができない。今日のような日は館の掃除をする。裏口の傍の掃除用具入れから大きな掃除機を取り出す。この掃除機も廃墟の町から持ち帰って修理したものだ。掃除機の電源コードを僕の胸に繋いでそこから給電する。電源を入れると掃除機は動き始める。修理したとはいえ、もともと非常に古いものなのでモーターの音が非常に騒がしい。しかし掃除をするという役割に関してはきちんと果たしてくれる。床に落ちている塵や埃を床用ノズルが貪欲に吸い取る。館の中はなかなか広いので全体を掃除し終えるにはちょうど一日掛かる。
掃除機を用いて掃除をしていると気付く点がある。人間が作り出した機械や道具には往々にしてはっきりとした役割が与えられている。そして役割を遂行するために適した姿形をしている。例えば掃除機は床に落ちているものを吸い取れるように長いホースとノズルが付いている。ディスクのプレイヤーには映像を映し出すための液晶画面と音声を流すためのスピーカーがある。速く移動することを目的とした自動車には四つのタイヤがある。その機械が何のために生まれてきたのかは形を見ればだいたい理解できる。機械はどれも生まれるに足る理由を持って生まれてきたと分かる。
僕の身体も機械で出来ている。僕が生まれた理由というのはいったい何だろう。僕の身体には腕が二本と脚が二本ある。首の上には頭が乗っている。顔には目と耳と鼻の穴がそれぞれふたつずつあり口がひとつある。全体として人間に良く似た姿形をしている。しかしこれでは自分がいったい何を目的に作り出されたのかを理解することができない。歩くことができるが、それでは僕は歩くために生まれてきたのだろうか。泳ぐことができるが、それでは僕は泳ぐために作られたのだろうか。僕は自分の生まれた理由を知らない。掃除機やディスクのプレイヤーや自動車などと違って僕は自分が何をして生きれば良いのかさっぱり分からない。
一夜が明けると嵐は去っている。まだ暗いうちに目を覚まして胸に繋いだ電源コードを外す。玄関ホールで父の写真に両手を合わせて祈る。玄関を出て川沿いの道を歩いて丘を降っていく。空は晴れておりオーロラが出ている。昨日の嵐でたくさん雨が降ったので足元はぬかるんでいるし川は増水している。日の出とともに浜辺にたどり着く。海に入って深い所へ潜る。海に沈んだ廃墟の町を目指す。細かな泡をかき分けながら僕は考える。人間という生き物についてもっとたくさん知りたい。どういうことに喜んでどういうことに心を痛める生き物だったか知りたい。そうすれば僕は自分が生まれた理由を理解できるような気がする。
廃墟の町に到着すると普段と少し違った気配がする。水の流れが微かに違っている。昨日の嵐のせいだろうかと僕は仮説を立てる。そうではないと僕は判断する。どこか近くに動くものが居る。耳を澄ますと僕が今まで聞いたことのない音が聞こえてくる。音は近くのビルの中から聞こえる。中に入って様子を確かめる。近くまで来ると僕は音の正体に感付く。これは呼吸の音だ。生きているものの気配だ。呼吸の主は柱の裏に居る。僕はひっそりそこを覗き込む。その生物は身体の長さが二メートルほどある。この生き物はいったい何だろう。僕は自分の知識を検索する。そして思い出す。この生き物はイルカだ。
イルカの姿を目にした僕の身体はにわかに熱を帯びた。とても興奮している。生きているものをこの目で見るのは生まれてはじめてだからだ。僕は溜め息を吐き、熱を逃がして自分の身体を冷やした。イルカという生き物には高い知能がある。だからイルカは僕の言葉を理解してくれたし、僕の方でもイルカの言葉を概ね理解できた。僕の出会ったイルカはマカロニという名前を持っていた。ここよりずっと南の海で暮らしていたけど嵐に乗ってここまで流れてきた。マカロニに対して僕は質問した。南の海はどういうところなの? マカロニは答えた。南の海にはイルカに限らず生きているものがたくさん暮らしている。
「正直言って結構驚いてる。北の海には生き物が居ないという話は噂に聞いていたけど、本当にすっかりなにも居ないんだな」ビルとビルの間をぷかぷか漂いながらマカロニは喋った。「あんたも南に行ったらいいと思うよ。ここと違ってあまり寂しくない」南の海には人間も住んでる? 僕はマカロニに尋ねた。「人間は居ないよ」とマカロニは答えた。「人間なんかとっくの昔にみんな滅びてしまった。今はどこにも居ないよ」マカロニはそう言って口から泡を吐いた。だったら僕は南の海へは行けない。僕は人間のことをもっと知りたいんだ。どうして自分が生まれたのかを僕は確かめたいんだ。
「生まれた理由なんてそんなに大事なことかい?」マカロニは僕の周りを素早くぐるりと一周回って言った。大事なことだと思う。僕はマカロニの質問に答えた。機械はみんな生まれるに足る理由を持って生まれてくるものなんだ。生まれた理由が分からなければどういうふうに生きれば良いかもずっと分からない。僕がそう言うとマカロニは笑った。あまり楽しそうな笑い方ではなかった。「おれは暖かい南の海で生まれた。おれは両親にとって最初の子どもだった。おれの両親は子どもを育てるのがあまり得意ではなかった。おれの両親はおれを産んだことをいつも後悔していた。おれはそうやって生まれたから、生まれた理由が大事というのはあんまり分からないな」
それから僕は毎日マカロニと過ごした。海に沈んだ廃墟の町をふたりで泳ぎ回った。僕はこれまでずっとひとりで過ごしてきた。だから他者と一緒に居ることがこんなにも楽しいとは少しも知らなかった。その一方で心配なこともあった。マカロニの体力が日に日に落ちていることだ。廃墟の町には生きているものがマカロニ以外に居ない。それはすなわちマカロニの食糧になるものがないということを意味した。「おれは別に良いんだ」僕の心配を他所にマカロニはそう言って笑った。「それよりお前は南の海に行きなよ。お前はけっこう寂しがり屋だから、南の海で過ごした方がきっと楽しいよ」
いつものように暗いうちから目を覚ました。ベッドの上で身体を起こして胸に繋いだ電源コードを外した。部屋の窓枠がカタカタと揺れ、風が轟々と吹きすさぶ音が聞こえた。カーテンを開けて外の様子を見ると激しい嵐が来ていた。嵐はこの世で最も怖ろしい。広く大きな廃墟の町も嵐によって沈んだ。廃墟の町に居るマカロニのことを僕は心配した。あんなに痩せて弱った身体で、嵐の海にひとりでいたら、きっと死んでしまう。マカロニが居なくなることを僕は想像した。僕の身体は熱くなり頭の中でパチパチ何かが鳴った。マカロニを助けに行こうと思った。父の写真に祈ることも忘れて、僕は館を出た。
雨に濡れながら丘を駆け下りて砂浜にたどり着いた。海面がかなり上がっており砂浜の広さは普段の半分もなかった。数メートルもある高波が何度も繰り返し押し寄せては砕けて白い飛沫を上げた。僕の身体はぐんぐん温度を上げ、頭で響くパチパチという音も更に大きくなった。マカロニを助けに行かなければいけないという思いはますます強固になった。僕は迷わず海に入っていった。押しつぶされそうなほど強い海流が僕の身体を襲った。しかし何とか泳ぐことはできる。僕の両目は水の中でも周囲がはっきり見えるし、身体はそこそこ丈夫に出来ているからこれくらいの水流では自由を失わない。
深いところを目指した。廃墟の町に近づくとコンクリートの破片や剥がれたアスファルトが巻き上げられていた。マカロニはまだ無事でいるだろうか。小さな砂の粒が目に入ったので一瞬目を瞑った。するとその時、首の後ろに突然強い衝撃が走った。何かが頭にぶつかったのだと気付いた時にはもう手遅れだった。たった一度の衝撃で自由を失った。上下左右が分からなくなり水の流れに飲まれた。自分にはもう成す術がないということをぼんやり理解した。僕はこのまま自分の生まれた理由も知らずに死ぬのだ。僕は目を閉じた。すると耳元で微かに声が聞こえた。「何をやってるんだ。ばか」
目を覚ました。日差しが眩しかった。僕は白い砂浜に横たわっていた。身体があちこち壊れているのが分かった。それにバッテリーも残りが僅かしかない。館に戻って充電しなければ。どうして自分はこんな所で倒れているのだろう。朦朧とした頭のままで僕は記憶を辿り、すぐに思い出した。嵐の海に潜って行って海流に飲まれたのだ。砂の上に手を突いて何とか身体を起こし、辺りの様子を見た。痩せたマカロニの身体が、波打ち際にごろりと転がっていた。「やあ、生きてたか。そんな顔するなよ」慌てて駆け寄った僕の顔を見ると、マカロニは力なく笑った。尖った口からたくさんの血を吐き出しており、助からないと分かった。「最後はこういうふうに生きるっておれが決めたんだ」マカロニはそう言い、それから間もなく息を引き取った。
いつものように暗いうちから目覚めた。ベッドの上で身体を起こすと胸に繋いだ電源コードを抜いた。部屋の隅にある机に向かって座った。ドライバーを握った。数時間を要して海に沈んだ廃墟の町で拾い集めた材料を組み合わせた。携帯用のソーラー電池を作った。発電量はあまり大きくないけれど、僕が一日活動する程度の電力ならば半日ほどで作ることができる。太陽光が届く場所ならどこでも充電できるのが利点だ。ソーラー電池が完成してからカーテンを開けると朝日が昇っていた。エレベーターで地下深くにある制御室へと降りた。パネルのボタンを幾つか弄って庭にそびえる発電用の風車を地下に格納した。
裏口の傍の掃除用具入れから大きな掃除機を取り出して館の掃除を始めた。掃除機の電源コードを僕の胸に繋いでそこから給電した。電源を入れると掃除機は動き始める。モーターの音が非常に賑やかで、僕に何かを訴えかけているようにも聞こえた。この掃除機をはじめ、僕があの廃墟の町から持ち帰って修理したものが、この家の中にはたくさん置かれている。すべての箇所を念入りに掃除するだけの時間はなかったけど、目につくところはだいたい綺麗にした。一通りの掃除を終えると、僕は掃除機のボディを柔らかい布で拭ってから、掃除用具入れに戻した。
自分の部屋に戻った。今まで集めたディスクの中から一枚を手に取ってプレイヤーに差し込み、再生ボタンを押した。液晶画面にビデオが流れ始めた。あの町が海に沈むよりも前の映像だ。映像の中心に映っているのはソファに座った白髪の老婆だった。老婆の腕の中には孫と思しき小さな赤ん坊が抱かれていた。赤ん坊はすやすやと眠っていた。老婆は笑顔だった。僕はこれまで、海に沈んだ廃墟の町で、写真やビデオのデータが入ったディスクやメモリーカードを、何百枚も拾った。そこに記録された人間たちの様子を何千回も眺めた。そして最近ひとつの仮説を立てた。人間というのは、親しい他者と一緒に居る時に幸せを感じる生き物だったのではないだろうかという仮説だ。
携帯用のソーラー電池と何枚かのディスクを鞄に詰め込んだ。玄関ホールへ行き、壁に飾った父の写真に、真っ直ぐ向き合った。僕は父のことをあまり詳しく知らない。父は人間だった。父は科学者だった。父は機械の研究をしていた。そして父は僕を作り出した。僕が目覚めた時には既に居なかった。僕が父について知っていることはたったこれだけだ。父はどうして僕を作ったのだろう。僕はいったい何のために生まれてきたんだろう。はっきりしたことは今も分からない。もしかすると、これから先も分からないかもしれない。いってきます。と父の写真に言い、両手を合わせて祈った。
玄関を出て外から施錠した。川沿いの道を歩いて丘を降っていった。白い浜辺にたどり着いた。砂浜の真ん中には鉄の板を張り合わせて作った十字架がひとつ立っている。十字架の下にはマカロニが眠っている。彼はイルカだけど、僕は人間のやり方で彼を弔った。鞄に入れて持って来た何枚かのディスクを十字架の傍に供えた。波打ち際に真っ赤な色をしたモーターボートが一隻止めてある。このボートもソーラーパネルで動く。例の如く、海に沈んだ廃墟の町から僕が引き上げて、手を加えたものだ。僕はボートに乗り込んで、一度大きく息を吐いてから、エンジンを掛けて海へと漕ぎ出し、南に舵を切った。