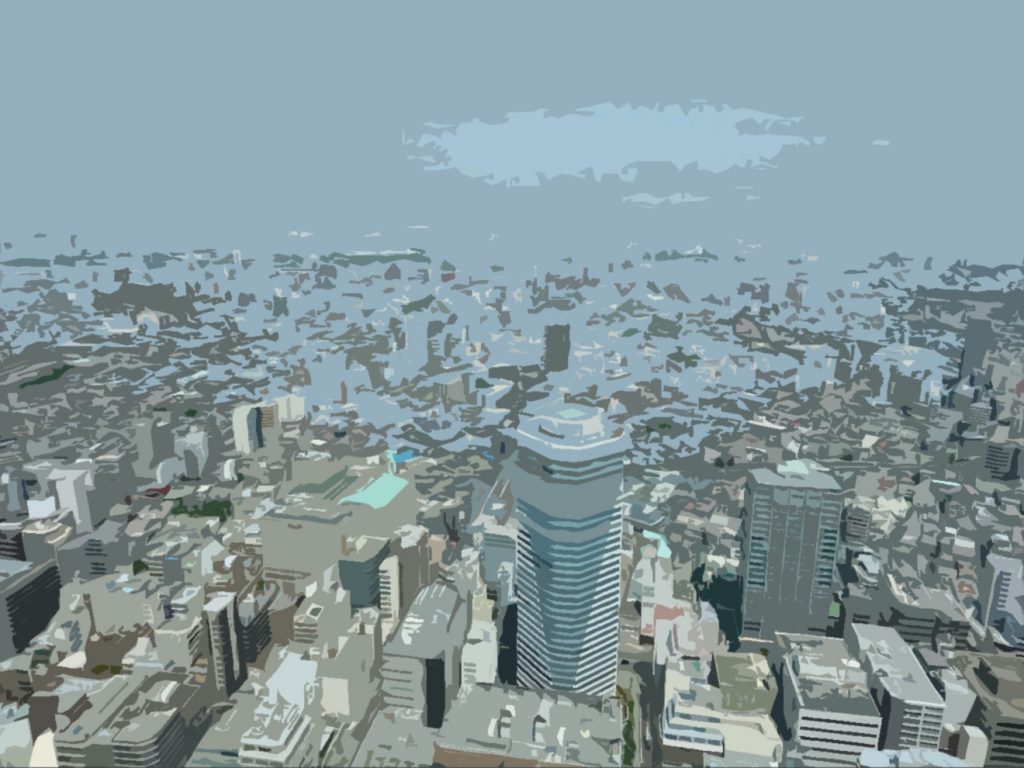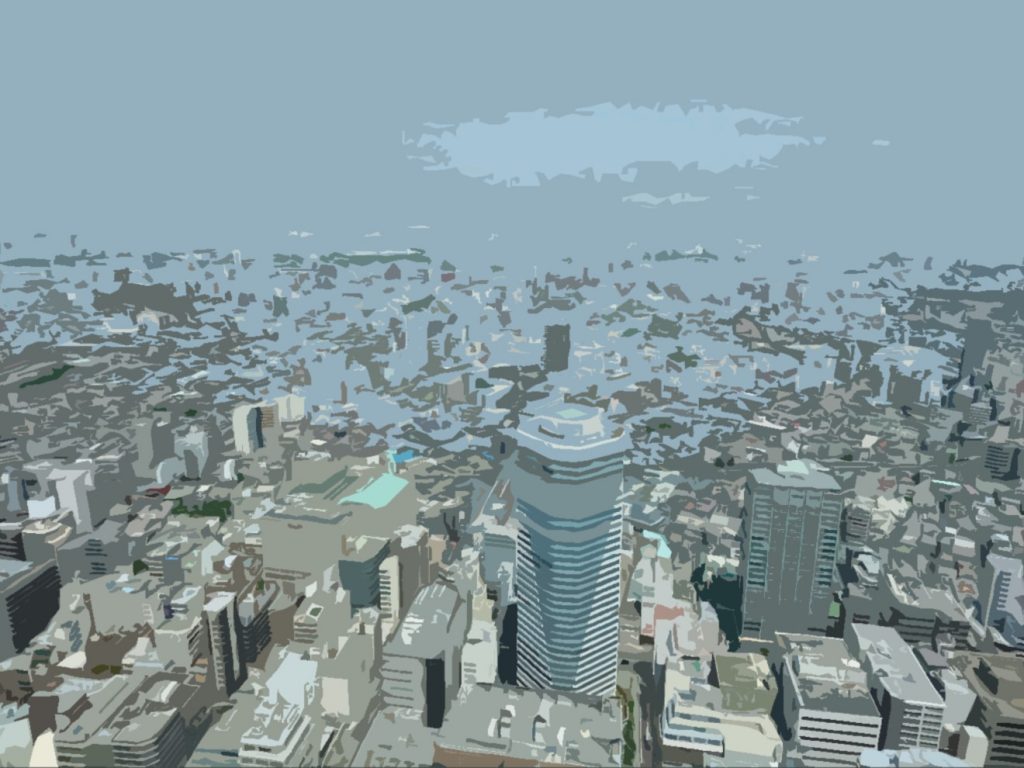春の日差しがカーテンの隙間から差し込んでいたので蛍光灯を付けなくても部屋は明るかった。昼食を済ませてコーヒーを淹れるとラジオを点けて部屋に音楽を流した。ピアノの音楽で曲名も分からなかったが遅いテンポのゆったりとした曲だった。図書館で借りてきたハードカバーの本を読み進めて一時間ほど過ごした。十四時ちょうどに本を読み終えた。私は椅子から立ち上がって髪の毛を結ってから軽く化粧をした。家の扉に鍵を掛けてから階段を使って一階まで降りた。マンションの外に出ると暖かい日差しが顔に当たったので一瞬目を細めた。
青と紫のタイルが敷き詰められた遊歩道をしばらく真っ直ぐ歩いた。途中で喉が渇いたので自動販売機からジュースを一本買った。ジュースを飲みながら歩き続けていると不意に大きな影が足元を横切ったので私は空を見上げた。すると背中に白い翼を生やした子どもの姿を見つけた。翼の生えた子どもは私の頭上を滑空しながら通り過ぎて行った。大きな翼は太陽の光を反射してきらきらと光っていた。とても美しかったので私は思わず見惚れて足を止めた。遠ざかっていく子どもの姿が建物の陰に隠れて見えなくなるまでのあいだずっと目で追い続けた。
生まれた時から白い翼を背中に生やした子どもたちが居る。翼を持った子どもは何万人かにひとりという割合で生まれてくる。どうして彼らは翼を持って生まれてくるのだろうか。何人もの医者や学者が長年に渡って研究しているけど未だに分からない。しかし背中に翼があっても健康上の悪影響はないので、自分の子どもが翼を持って生まれてきたとしても親は悲しまない。それどころか翼を持って生まれてくることは非常に喜ばれる。美しいからだ。翼を持った子どもはこの世でいちばん美しいもののひとつだといわれている。どこに行っても誰からも可愛がられる。
私も翼を持って生まれてきた子どもだった。だから私の両親は私のことを大いに誇っていたし、周囲の大人たちは私のことをいつも特別に扱って宝物のように接した。可愛がられることは非常に気持ちが良かった。大抵の我儘は叶えてもらえたし多くのことが思い通りになった。同じ年代の子どもたちだって私を羨んだ。妬まれることもあったがそれさえ心地良かった。マンションの屋上から飛び立って町の上空を滑空するのがいちばん好きだった。町を行くひとびとは私の姿を見つけると羨望のまなざしを送った。私はそれが何より楽しかった。
翼を持った子どもは数万人にひとりしか生まれてこないのでとても珍しい。けれどこの国には老若男女を全部合わせると一億と数千万人ものひとびとが暮らしている。そのうち未成年の人数はだいたい二千万。なので翼のある子どもはこの国全体で数百人ほど居るし世界を見渡せばもっとたくさん居る。しかし一方で翼のある大人というのはこの世にひとりも居ない。何故なら翼は子どもの頃だけのものだからだ。まるでオタマジャクシの尻尾のように成長と共に小さく衰えていき成人する頃にはすっかり消えてなくなる。翼を持って生まれてきた赤ん坊は特別な子どもとして育てられるけど大人になれば普通のひとになる。
私の翼もやはり例外ではなかった。はじめに異変を覚えたのは十三歳の頃だ。最初の生理を迎えるよりも少し前だった。乳房が徐々に膨らみ始めるとそれにしたがって飛ぶのが下手になった。きっと体重が増えたせいだと考えたので食事を減らして身体を軽くしたが以前のように上手く飛ぶことは出来なかった。私の翼はどんどん小さくなり、高校生になった時にはまったく飛べなくなった。飛ぶことは出来なくても翼は生えていたので周囲は相変わらず私を甘やかしたが、私は怯えていた。みんなが私に優しくしてくれるのは翼があるからだ。この翼が完全に消えてしまったら誰も私に見向きもしなくなる。そうなった後どういうふうに生きていけば良いのかまったくわからなかった。
十八歳の誕生日に私はマンションの屋上へ登った。かつて自由に空を飛べた頃はそのベランダから飛び立って滑空するのがいちばん楽しかった。もういちどで良いからあの頃のように自分の翼で空を飛びたいと思った。十八歳になった私の翼は張りぼてで作った飾り物とほとんど変わらなかった。こんなちっぽけな翼だけに縋って生きていることもとても情けないと感じた。小さい頃にやったように空を飛ぼうとした。屋上のフェンスに手を掛けて乗り越えようとした。けれど私はそこから先へ身を乗り出せなかった。翼を失った後のことを考えると酷く恐ろしかった。しかし眼下に見える地上に落下して死ぬことを想像したらもっと怖いと感じた。私はその場でへたりこみ暗くなるまで泣いた。
青と紫のタイルが敷き詰められた遊歩道をしばらく真っ直ぐ歩いた。天気が良くて風も程よく吹いていたので歩いているだけでもなかなか気分が良かった。コンビニの手前にある曲がり角から細い路地に入った。路地の隅には猫が三匹居てそのうちの一匹は首輪をつけていた。路地を抜けると幼稚園がある。薄青色のスモックに身を包んだ幼い子どもたちが親の帰りを待ちながら園内の庭を所狭しと走り回っていた。正門を通って私は園に足を踏み入れた。私の姿を見つけた娘がこちらに駆けてきた。私は娘の小さな身体を抱き上げると頬にキスをした。娘の背中に翼は生えていない。