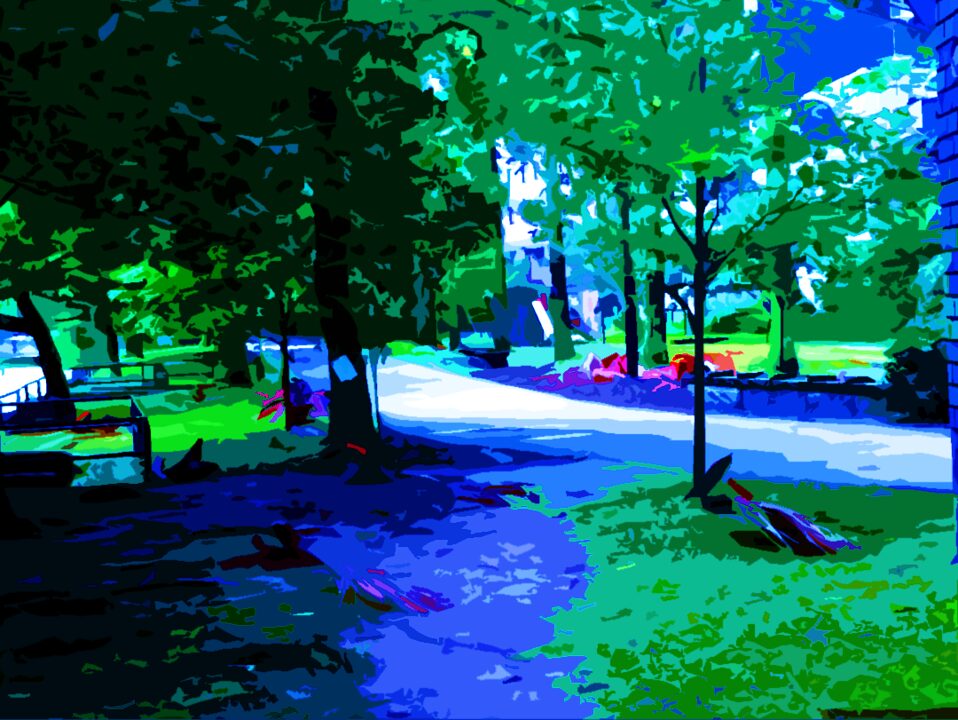
ケイタはうなだれている。音もたてずに降る十一月の夜の冷たい雨のなかでスーツ姿のケイタはうなだれている。公園のベンチで傘もささずにケイタはうなだれている。柔道で鍛えた広い背中をダンゴムシみたいに丸めて、合皮の靴のつま先をぼんやり眺めながら、ケイタはうなだれている。ケイタは落ち込んでいるのだ。ケイタは落ち込むとこの公園のベンチにやってきてしばらくのあいだひとりで過ごすのだ。小学生の頃からケイタはそうなのだ。
――
ケイタが落ち込んでいるのは今日の昼間に職場の後輩とのあいだで不和があったせいだ。ケイタが所属する営業部に今年の春から配属されたその後輩は社会人経験約半年にしてひとりで客先をまわりひとりで契約を取ることができる将来有望な若手社員である。だがその一方で報告連絡相談が疎かになることが多く直属の上司や同僚を困らせる場面も何度か見受けられた。
そんな後輩にケイタは注意をした。「もうちょっとみんなに連絡してくれると嬉しいな」と。なるべく柔らかい言葉を選んで後輩を諌めた。このままではいつか大きなトラブルが起きるのではないかと心配したからだ。それによって会社や営業部はもちろん後輩自身も不利益を被るのではないかと心配したからだ。
だが注意された後輩の反応は芳しいものではなく「はァ」と空気が抜けたみたいな返事を返すばかりだった。それからあとは露骨にぶすくれて退勤するまで最低限しか口を開かなかった。
だからケイタは落ち込んでいるのだ。もっと上手い注意のしかたがあったのではないかと考えて落ち込んでいるのだ。言い方を間違えてしまったのではないかと考えて落ち込んでいるのだ。
――
十一月の夜の冷たい雨粒が公園の街灯の光の中を羽虫みたいにきらきらと漂う。オレはベンチにピョンと跳び乗ると項垂れて落ち込んでいるケイタに「元気だせよ」と声をかけてみた。「ケイタは間違ってねえよ。あいつみたいな生意気な若者には誰かが厳しく言わなきゃダメなんだ。そんなことよりスーツがびしょ濡れだぜ。早く帰って夕飯を食いなよ」
だがオレの言うことにケイタは反応しない。なぜならケイタにはオレのいうことが聞こえないからだ。ケイタにはオレの姿が見えていないからだ。オレはケイタの考えていることがちょっぴり分かるのだけど、ケイタからはおれのことを認識できないのだ。
――
そういえばケイタが十七歳の頃にこんなことがあった。その日ケイタは高校の部活動が休みだったので放課後に同じクラスの男友達数人とつれだってファミリーレストランを訪ねた。彼らはケイタにとって気のおけない友人たちであった。時々このように集まってはポテトとかピザとか唐揚げとかをつまみながら、真剣な悩みを打ち明けたり、箸を転ばして笑い合ったりするような、居心地の良い間柄であった。
だがこの日の話題に限ってはケイタにとって良いものではなかった。ケイタの倫理観に沿うものではなかった。愉快な仲間たちはあろうこと、その場にいない同じクラスの女子生徒たちの名前をひとりずつ挙げて、その顔立ちや身体つきに点数をつけ始めたのである。仲間たちの口元は異性への後ろ暗い関心を共有しあう興奮で以て一様にニヤけていた。ニヤけていないのはケイタだけだった。
「そういうのは冗談でも言わないほうがいいよ」と、だから、仲間たちの会話を遮るようにしてケイタは口にした。たとえ本人がその場にいなくても個人の名前を挙げてそうした事を言うべきではないとケイタは訴えた。
だが次の瞬間ケイタは、しまった、と思った。その場の空気はスゥと冷え込んで、仲間たちが自分に向ける視線が、異物に対して向けるものに変わっていたからだ。お前はもう仲間ではないよと言われているように、そのときケイタは感じた。
だからその日の帰り道もケイタは公園に立ち寄り、ベンチに座ってひとりでうなだれた。実際にそれ以降、ケイタが放課後のファミリーレストランの集まりに呼ばれることはなかった。
――
そういえばケイタが十四歳の頃にこんなことがあった。当時ケイタが所属していた中学校のクラスではある特定の男子生徒が数人のクラスメートから成るグループによって日常的に殴られたり蹴られたり侮辱的な渾名で呼ばれたりお金を取りあげられたり万引を強要されたりしていた。それらは当初こそ部室棟の空き部屋など人目につかない場所で行われていたのだけどエスカレートするにつれて人目を憚らなくなり遂には日中の教室でも見られるようになった。
すると黙っていられなかったのがケイタである。加害グループの首魁にあたる男子生徒に対して「こんなことはやらないほうがいいよ」と訴え出たのだった。それはケイタにとっても勇気の要る訴えであった。だが言われた側はそんなケイタを軽く嗤い、それでおしまいだった。
以降も蛮行は止むことがなかった。それどころかケイタ自身にも飛び火したのであった。柔道の有段者で身体の大きいケイタに直接的な暴力をふるう者こそいなかったが、無視したり、根も葉もない噂を立てたりといった嫌がらせが見られるようになった。
一連の嫌がらせは別のクラスメートの通報により警察官が学校にやってきて加害グループの連中を連れていくまでのあいだ数ヶ月続いた。数ヶ月のあいだ、ケイタはしょっちゅう学校帰りにひとりで公園に立ち寄り、ベンチでひとり落ち込む日々を過ごした。
――
そういえばケイタが十一歳の頃にこんなことがあった。それは秋のはじめの夕暮れ時だった。ケイタが当時通っていた小学校からほど近い道で一羽のカラスが人間の悪ガキに襲われていたのだ。ねぐらを目指して飛んでいたところをエアガンで以て撃ち落とされたのだ。突然の衝撃とともに冷たく硬いアスファルトに叩きつけられたときオレは自分の身体に何が起きたのか少しも分からなかった。分からないままさらに何発も撃たれた。撃った悪ガキが興奮してはしゃぐ声が聞こえた。
そんなときに現れたのがケイタだった。「やめろ!」と大きな声で叫びながら走ってやってきた。オレを撃った悪ガキはその声に驚いて一目散に走り去っていった。悪ガキがいなくなったあとケイタはオレの身体を両手で拾い上げた。「なんでこんなひどいことをするんだ」と呟くケイタの目には涙が浮かんでいた。
オレは結局そのまま死んじゃったが、あのときケイタがオレのために泣いてくれて、そのあと土に埋めて弔ってくれたおかげで、いくらか救われた。
後日。オレを撃った悪ガキが父親に連れられてケイタの家に来た。悪ガキはケイタと同じ小学校に通っており学年はケイタよりもひとつ下だった。「うちの子がお宅のケイタくんに大声でおどかされたんだ」と悪ガキの父親はケイタの母親に詰め寄り、ケイタの母親はそれに対して何度も頭を下げた。
父子が帰ったあと、ケイタの母親はケイタのことを少しも責めなかったが、頭を下げる親の姿を見たケイタは、自分が咄嗟にしたことは本当に正しかったのだろうと頭を抱えていた。ケイタはオレを救ってくれたのに。オレはケイタに感謝しているのに。オレは死んじゃったので、それをケイタに伝えるすべはもうないのであった。
――
ケイタはうなだれている。音もたてずに降り、つき刺さるように冷たい、十一月の夜の雨のなかでケイタはうなだれている。おれはもう死んじゃっているからケイタの考えていることがちょっぴりだがわかる。昼間、後輩に注意したことについてケイタは悩んでいるのだ。
もっと上手い注意のしかたがあったのではないか。注意を聞き入れてもらえないのは自分の普段の働きぶりに問題があったせいだろうか。明日も後輩と顔を合わすけれど気まずくならずに関われるだろうか。そういうふうにうじうじ悩んでいるのだ。
実際のところ明日からケイタが後輩とうまくやれるかはオレにも分からない。注意したことでケイタは以前よりも悪い状況に陥るかもしれない。そもそも人間なんて悪いやつのほうが多いものだもの。その場にいない者を侮辱したり、弱いものいじめしたり、カラスをエアガンで撃ったりするような連中なんだもの。そんな連中のなかでケイタがいくら正しいことをしたって、それが良い結果につながることは、そんなに多くないのだ。
だから結局オレに分かるのは、どんなに悪い結果になろうが、嫌な思いをしようが、ケイタはこれからも同じようにするだろうな、っていうことぐらいだ。失敗した、しくじった、もっと良いやり方があったんじゃないかと頭で考えても、結局このケイタという人間は、自分がそのとき正しいと思うことをやってしまう、変な人間なのだ。そしてそういうケイタのことがオレは好きなのだ。
やがてケイタはのそりと立ちあがる。依然として暗い表情のまま歩きはじめ、ゆっくり、ゆっくり、家の方へと向かう。「そうそう。いいかげん腹が減っただろ?」と、聞こえないのが分かっているけどオレはケイタに言う。

あとがき
誰にも感謝されなくても、裏目に出てしまっても、あなたがヒーローだということは、誰かが知っていますよ
2026/01/28/辺川銀


