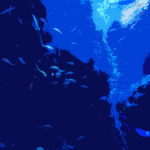ずいぶん早くに目を覚ましてしまった。カーテンを外した窓の向こう側には外灯の灯りだけがぼぅっと浮かんでいる。眠り直そうかとも考えたがすっかり目が冴えてしまったので起きることにした。とはいえ荷造りは概ね済んでいるし引越し業者がやって来るまでは三時間以上ある。本もテレビもパソコンもダンボールの中だ。床の上に置いたペットボトルを手に取り中に残っていたぬるいお茶を飲み干す。お腹の方はそこそこ空いている。コンビニでも行きがてら少し散歩をしてこようかと思う。
外の空気はまだ肌寒く月は出ていなかった。最寄りのコンビニでサンドイッチとチョコレートを買って食べながら人通りのない未明の街を西に向かって歩いた。十五分ほど行くとつい先月まで勤めていた古く小さなオフィスビルに着いた。もしも誰かが残って仕事をしているようであれば最後に軽く挨拶でもしていきたかったが窓に灯りは灯っていなかった。ビルの傍にある公園では桜の蕾が膨らみかかっていた。新卒で入社をしてから三年のあいだ一緒に働いたみんなは今年もここにシートを敷いて花見をするのだろう。どこか遠くで救急車がサイレンを鳴らした。
父は転勤が多いひとだった。だから僕も幼い頃から転校や引っ越しを何度も繰り返した。幸い僕は行く先々で新しい人間関係を築くことに苦労する性格ではなかった。だがそれでも、自分はよそ者だ、という僅かな引け目も常に感じていた。仲間内での話題が一年前とか二年前の思い出話になった時には置いてけぼりだったし、花火大会や雪祭りをみんなで楽しんだ帰りに「また来年も来ようね」なんて言葉を交わしあっても、どうせ自分はその時もう居ない、と心を曇らせた。当時はまだ小学生が携帯電話やインターネットに触れる時代ではなかったから、どんなに親しいクラスメートであっても転校後まで交流が続くケースは非常に稀だった。
彼との出会いは小学四年の秋のことだった。僕が都内の小学校に転入した時だ。彼は僕と同じく親の転勤に伴う転校を多く経験している子どもだった。何度も転校を繰り返してきたとはいえ似た境遇の子どもと知り合えることはそれほど多くなかった。短期間ですぐに環境が変わってしまう寂しさや難しさを共有できる相手はとても貴重だった。僕らはすぐに友だち同士になった。
彼にはひとつの変わった趣味があった。雲を眺めることだ。頭上に浮かぶ雲を指さし、あれはソフトクリームに似ている、あれはクジラのようだ、あの雲はまるでシロクマみたいじゃないかと、その形から連想されるものを挙げて遊ぶのだ。加えて彼は、さながら星座と神話を紐づけて語ったギリシア人のように、雲の形から連想されるものたちを使った即興の物語を僕に聞かせてくれた。「あのクジラは悪さをしたので海を追い出されて雲になったんだ」「あのシロクマは寒がりだから太陽の近くに行きたくて雲になったんだよ」僕はそれまでそんなことを考えながら雲を見ることなどなかったから彼のユーモアや想像力をとても尊敬した。彼の話は一日中聞いていたって飽きることがなかった。
けれどその次の春に彼の転校が決まった。彼は僕よりも先に東京から離れることになった。僕らはお互いに転校が多く、いつか別れが来ることは最初から分かっていた。にもかかわらず実際に離れ離れになることが決まると自分でも驚くほど僕はショックを受けた。それほど彼は僕にとって特別な友だちになってしまっていた。そしてどんなに特別であっても、いちど離れ遠くへ行ってしまえば再会することはとても難しく、ましてや従来と同じような関係を保ち続けることはできないということも分かっていた。
彼が東京を発つ朝。僕は東京駅のホームまで見送りに出向いた。そこでも僕は涙を抑えられず、最後の最後でぐちゃぐちゃの泣き顔を彼に見せてしまった。そんな僕の肩を彼はポンと叩き「距離が離れたって大切なものはなくなったりしないよ」と言ってくれたのだが、あの日の僕にとって、そんな言葉は気休めにもならなかった。
実際あれから十五年が経ち、SNSで古い知人を探しだすことが容易な時代になっても、僕と彼とは未だに再会していないし、相手がどこで何をしているのかもまったく知らないままだ。
どこか遠くで救急車がサイレンを鳴らした。未明の街を西に向かって僕は歩いていく。新卒で就職してからというもの三年暮らした街だ。子どもの頃から引っ越しが多かった僕にとっては大学時代の四年間を過ごした土地に次いで長く住んだ場所だ。思い出だってある。はじめて担当したプロジェクトの打ち上げに使った居酒屋は去年潰れてどこにでもあるハンバーガー屋になった。昼休みのたびに通い詰めた定食屋もこの時間ではもちろん閉まっている。引越し業者がやって来るまであと二時間ほどだ。
そろそろ家に帰っておこうと踵を返して東に向き直ると僕は息を呑んだ。向いた方向には朝日が昇り始めていた。朝と夜との境目には薄紫色の空があって、太陽の傍には大きな雲がひとつ浮かんでいた。その雲をじっと眺めながら、ああシロクマに似ている、と思わず呟いた。大きな鳥の乾いた羽音が頭上を通り過ぎる。次の土地でも上手くやれる気がした。
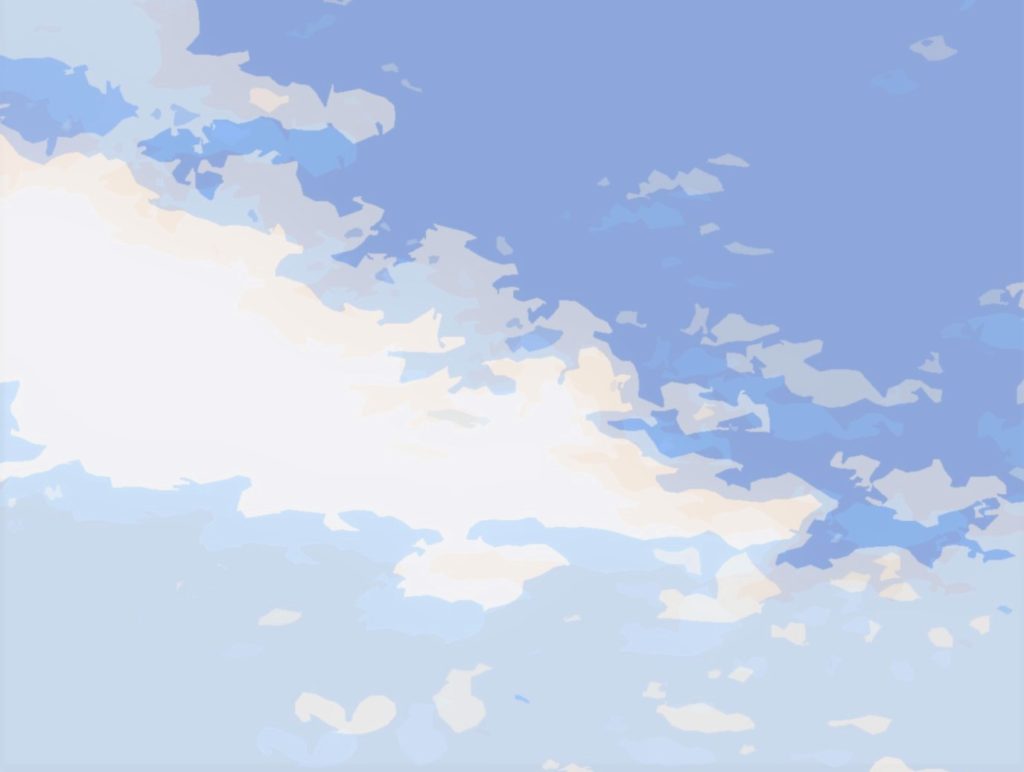
あとがき
このお話のモデルになってくださった方コメントをいただきました。
写真は高校・大学時代にとってもお世話になった、僕の青春の権化といっても差し支えないようなコンサートホールです。残念ながら今はもう閉館して、取り壊し中です。
でも、ホールはなくなっても、ここでの演奏の記憶を通じて、大阪での友人とはいつでも互いに味方になれるような気がしています。同じように、いろんな習慣や記録をたよりに、子ども時代を過ごしたあちらこちらの友達も、味方でいられるはず。
あちこちに散らばった友達と、離れている間の時間を埋めることは難しいけれど、その土地の人たちとの時間が大事な時間だったと思っている限りは、これからの未知の場所でも味方になってくれることだろうと思います。