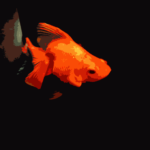さきほど街で出会ったばかりの名前も知らない若い男の子はベッドの上で裸になったわたしの身体をおそるおそる触った。きっと実際におそれているのだろう。母親いがいの生きたおんなに触れた経験が過去にいちどもないと話していたから初めてのことにおそれているのだろう。おそれる気持ちをかき分けながらわたしの身体に触れているのだろう。その腕や指はまるで雪を被った木の枝みたいに細く白く骨ばっているのに触れられた部分には確かな熱を感じて心地が良いと思った。カーテンのないホテルの窓からは夜空に浮かぶふたつの月が見える。どこか遠くで緊急車両のサイレンにも似たケモノの遠吠えが聞こえてきたので、わたしは、男の子の耳の裏側に指を這わせながら今夜このへんでヒトが死ぬんだろうなァとぼんやり考えた。
約二万年前におこなわれた星間大移動では当時地球で暮らしていたヒトのうち半数以上が他の星に移住したといわれている。移住先となったのは事前に選定された十二の星々で今わたしたちが暮らすこの星もそのなかのひとつだ。地球を離れたヒトびとはそれから二万年のあいだに移住した星の環境に応じてその在り方を変えた。ある星に移住したグループは星を渡るほどの科学を一切放棄して深い森での暮らしを営んでいる。別のある星に移住したグループは幾世代を経た進化によって水中での呼吸が可能になり現在は海中に文明を築いている。地球を上回る科学と武力を得て地球に戦争を仕掛けているグループも存在する。そしてこの星で暮らすわたしたちにも他の星のヒトにはない特徴がある。
この星で生まれたヒトはひとりでに死ぬことがない。長く生きればそれだけ老いるし病気になることもあるが原則として不死だ。飢えてもナイフで刺されても爆弾を落とされても自ら首を吊ってもわたしたちは死なない。唯一の例外はケモノに食べられることによる死だ。この星の原生生物であるケモノだけがわたしたちを殺せる。ケモノは夜にだけ現れ夜の色をしており決まった形を持たない。この星に住むわたしたちの死はすべてケモノによってもたらされるのだ。とはいえケモノはそれほど素早く動くことができないので若く健康なヒトであれば食べられることはまずない。老いや病気で逃げることが困難になれば食べられる可能性が高くなる。ケモノから逃れるちからのないものと逃げる意思のないものだけがケモノに食べられる。にもかかわらずわたしの兄は十八歳でケモノに食われて死んだ。
兄は若くて健康だった。ケモノから逃げるちからがないわけがなかった。だから死んだときには誰もが驚いた。兄の死の第一発見者はわたしだった。そのときわたしはまだ十歳だった。十歳だったわたしは兄がケモノに食われるところを見た。「夕飯の支度ができたからお兄ちゃんを呼んできて」と母に命令されたので兄の部屋に赴くとそこでケモノが兄を食っていた。ケモノの身体は埃のように軽く腕を一振りしただけでも飛んでいってしまうから健康な人間ならば眠っていても追い払うことができる。だが兄は目を開けていたのに微動だにせずケモノに食われていた。ケモノは夜が昼を飲み込むときのような遅さで兄の身体を侵した。兄は両腕を広げて抱きしめるような姿勢でケモノを受け入れていた。愛するヒトを抱きしめるみたいに。愛おしそうに。すぐ近くで見ているわたしに気づかぬほど。
さいきん流行りの他所の星の歌手は「どのように死ぬかが重要だ」と歌う。他所の星にはこの星とは異なり様々な死に方があるのだ。死に方には良し悪しもあり病気で長いあいだ苦しんだり誰からも看取られずに孤独に死んだりすることは良くない死に方だという。この星のヒトにとっての死はケモノに食べられる以外にないがケモノにも個体差があるためどういったケモノに食べられて死ぬかを気にするヒトは少なくない。たとえば少食なケモノやグルメなケモノに食べられて死ぬのは中途半端に食べ残されることがあるので悪いとされている。逆に腹ペコのケモノにぺろりと食べられて骨だけが残されるのは良いとされている。わたしもそう思う。どうせだったら残さずぜんぶ美味しく食べられたい。あの日のケモノは兄を丸呑みにした。だから兄は骨さえ残らなかった。まるではじめからこの世に居なかったみたいに。
兄は賢かった。才気に溢れ勤勉で母が自分では叶えられなかった夢を叶える力があった。研究者になり依然として謎が多いケモノの生態を明らかににするという夢。だから母は「あの子の夢を叶えるため」といいながら自分の夢を叶えさせるために財力も労力も持てるすべてを兄に注ぎ込んだ。母は一方で次子のわたしに対してはほとんど関心を抱くことがなかった。だがわたしは特に不平や不満を感じたことはない。兄はわたしから見ても優れた存在だったからだ。母が兄に期待することもわたしに期待しないことも当たり前だと思い疑問を抱かなかった。でも兄は死んだ。ケモノは兄ではなくわたしを食べるべきだったと母は言った。もちろんわたしもその通りだと思った。きっとケモノは優れた兄のことが欲しくてたまらなかったのだろうとも母は言った。きっとそうだとわたしも考えた。すぐ近くにいたのに食べられなかったわたしはきっと食べる価値もなかったのだろうとも酒に溺れながら母は言った母がそういうのであればそれは正しいことなのだろうとわたしは考えた。だからわたしはわたしのことを食べ残された肉片みたいだと思ってずっと生きている。
さきほど街で出会ったばかりの名前も知らない若い男の子はベッドの上で裸になったわたしの身体をむさぼり食う。これまで母親いがいの生きたおんなに触れたことなどなかったのだというやせっぽちの男の子はまるでナイフやフォークの使い方もままならない幼子が初めて目にするビーフステーキにかじりつくときのように息を荒げて口を大きく開けてわたしを味わってゆく。さきほどよりも近い場所からケモノの遠吠えが聞こえたが意に介すことなくわたしは彼に行為の続きを促す。今日のようなことはめずらしいことではない。ケモノ食われて人が死ぬこともたまたまみかけたお腹の空いていそうな男の子にわたしの身体をお食べよと言ってみることもありふれていて少しもめずらしいことではない。この一週間に食べたものを全て思い出せるだろうか。ちょうど一ヶ月前の夕ご飯を思い出せるだろうか。食べる価値もなく食べ残されたわたしは美味しく食べられたい。誰かにとって忘れられないご馳走でありたい。
やがて男の子は力尽きて汗だくのまま寝息をたて始める。わたしは起きあがり衣服を身につけてテーブルのうえにホテル代をおいてからその場を後にする。こういうことをしたあとはいつもお腹が空く。三日経ったら思い出しもしないような粗末なものを貪りたいと思う。

あとがき
とてもお久しぶりです。「年をとるとたくさん食べられなくなるけど、そのぶん粗末ではないものを食べたくなる」という話題から、こういうお話になりました。
2024/01/10/辺川銀