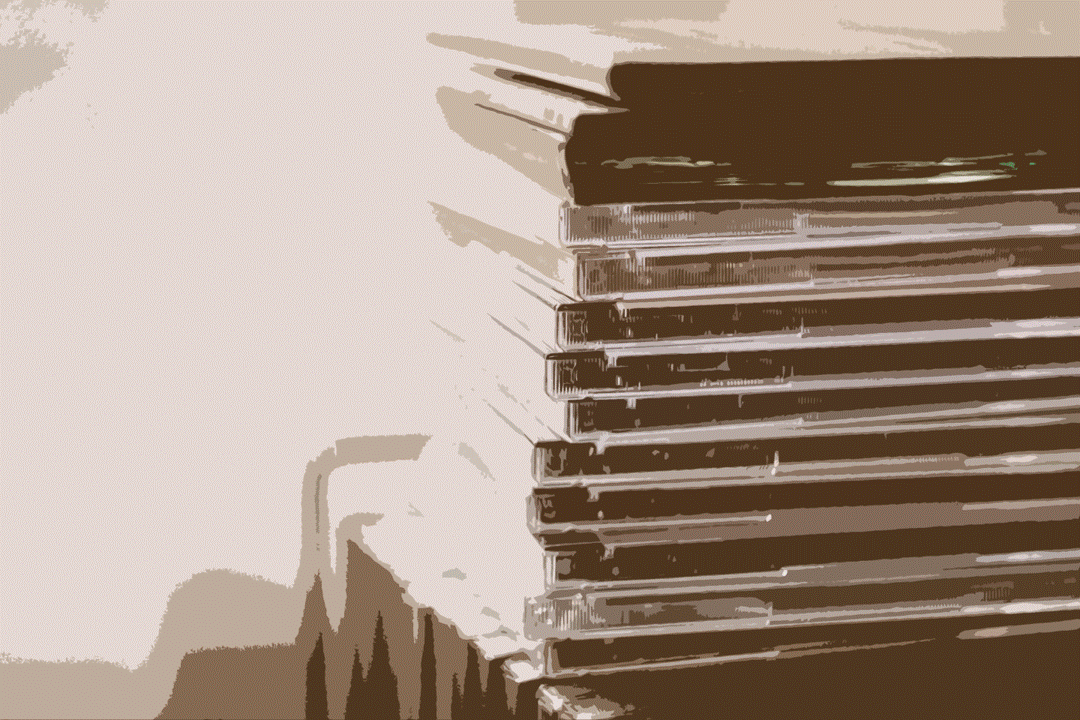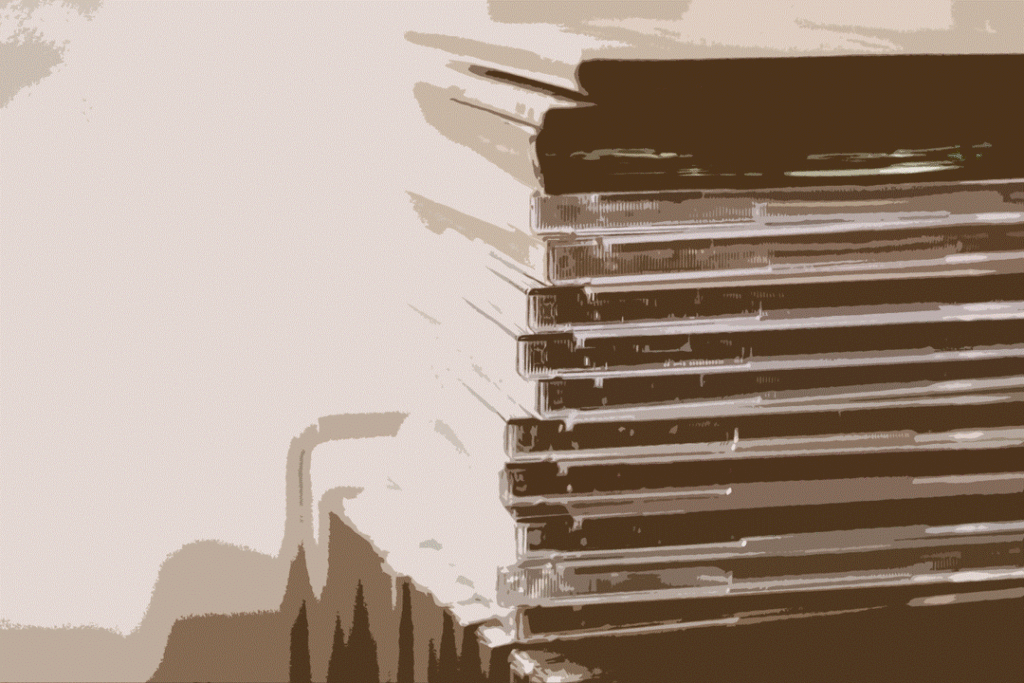
新幹線に乗るのはずいぶん久しぶりだ。大学時代に親しかった仲間たちと旅行をした時以来だ。彼らが今どこで何をしているのか私はほとんど知らない。窓際の席だが既に二十時を少し過ぎているから景色はほとんど見えない。お腹が空いてきたので車内販売のワゴンを呼び止めた。どのお弁当も売り切れており何も買えなかった。
昨年末から寝付きが悪くなった。一過性の不調だと思っていたが年末年始の休暇を挟んでも改善しなかった。それどころか仕事中に動悸や息切れが起こるようになり従来ならば難なくこなせていた業務にも支障が生じ始めた。見かねた上司の勧めで心療内科を受診すると鬱病だという診断され数ヶ月のあいだ休職することが決まった。
休職してからの一ヶ月ほどは自宅で療養していた。だが私にとって自宅療養は出勤するよりもずっと苦痛だった。両親の存在が主な原因だ。地元の国立大学を卒業して県庁に就職した私は両親にとって自慢の娘だった。その私が一時的にとはいえ働けなくなったという事実は彼らにとって非常に大きな失望だったようだ。
母は「鬱の治し方」とか「復職ガイドブック」といった本を毎日のように買ってきては私に手渡した。父はお酒を飲みながら「大人というのは吐いても泣いても仕事に行くものだ」と私を非難した。これでは治る鬱も治らなくなってしまう。そう思った私はしばらくのあいだ地元を離れて東京で過ごすことを決めた。
ミサキと私は同じ日に生まれた。ミサキが姉で私が妹だ。ミサキは他者との競争を好まない子どもだった。小学校の運動会では徒競走の途中で、転んでしまった同級生に手を貸し、励ましながらゴールに連れて行った。結果としては最下位だったがミサキは満足げにニコニコ笑っていた。順位とか点数とか評価というものに対しミサキはほとんど興味を示さなかった。
片や私は優等生だった。テストや数値評の数値を伸ばし親や先生に褒められることが苦手ではなかった。けれどもちろん優等生でいるためには努力が必要で、努力することに疲れる時もあった。疲れた時に私は決まってミサキの部屋を訪ねた。ミサキの部屋には古い洋楽がささやかな音量でいつも流れていた。本棚にはミサキがお小遣いをやり繰りして買ったCDが幾つも並んでいた。その日その日でオススメの曲をかけてもらいながら、彼女と会話する時間が私は好きだった。
小学校の高学年になると私たちは両親の意向で中学受験をするための勉強を始めた。志望校として両親が定めたのは中高一貫の進学校だった。ミサキは私と違い勉強があまり得意ではなかった。だから母は嫌がるミサキに毎晩つきっきりで勉強を教えた。「ミサキのような子ほど無理矢理にでも勉強させて私立に入れなきゃいけない。そうでなければ良い大学に行けない。良い大学に行かなければ良い職業にも就けない。良い職業に就けなかったら不幸になってしまう」と母は話していた。
そんな両親の頑張りが実り私たちはふたりとも志望どおりの進学校に入学できてしまった。だがそれはミサキにとって決して良いことではなかったように思う。定期テストのたびに廊下に張り出される順位や点数が、人間としての価値まで決めてしまうような雰囲気があの学校には合った。競争が苦手なミサキは入学してすぐに劣等生のレッテルを貼られた。
私はといえば進学校でも優等生であり続けた。定期テストでは上から五番以内をキープするよう努めた。いちど不注意で順位を大きく落とした際には「しょせんミサキの妹だな」と侮蔑の言葉を浴びた。私はそれが泣くほど悔しかった。悔しいと感じる自分を嫌悪もした。あんあ思いを二度としないためにいっそう努力を重ねた。そしてこの時期から私はミサキと距離を取り始めた。彼女の部屋で音楽を聴くこともなくなってしまった。
高等部に進学するとミサキはいよいよ問題児としてみなされるようになった。同級生が大学受験に向けて勉強を始めた頃、ミサキは大学どころか卒業することさえ危うい有様だった。私にとって不可解だったのはそれでもミサキが毎日を明るい表情で過ごしていたことだ。アルバイト禁止の校則があるにもかかわらず隣町のレコードショップででレジ打ちをしていた。そのレコードショップで知り合った大人たちとバンドを組んでライブに出たりしていた。
なんとか高校を卒業するとミサキはアルバイトで貯めたお金を頭金にして家を出ていった。それからというものミサキはいちども家に帰って来ない。家族の中でミサキの話題は禁句のようになった。
両親は彼らなりにミサキのことを愛していたと思う。けれど愛することと、愛を伝えることは、必ずしもイコールではないのだろう。愛を正しく伝えるためには、相手をきちんと理解することが必要不可欠なのだ。両親はミサキのことを愛してこそいたけど、彼女がどんな人間なのかを理解することは、ついぞできなかった。
一方の私は少なくとも両親よりミサキのことを理解していたはずだ。けれど中高生の時点で彼女のことを愛せていたかというと、少し自信がない。特に高校時代などは彼女のことを驚異に感じていた。勉強をしなければ不幸になる。偏差値の大きさが将来の幸福度を約束する。そう言われながら努力をしてきたのに、家に変えれば劣等生のミサキが、さも青春を謳歌していますといわんばかりにニコニコ笑っているのだ。彼女が楽しそうであるほど、私は自分の努力が否定されている気がして、恐ろしく思った。いつかミサキが不幸になればいいと思う気持ちさえ心のどこかにあった。だからミサキが家を出ていった時には、正直なところ、胸をなでおろした。
残った私はその後も様々な競争に勝ち続けた。受験競争に勝って地元の国立大学に入学した。就職競争も勝ち抜いて県庁に就職した。就職後の出世競争にしてもそこそこ堅調に戦果をあげ続けてきた。両親はそんな私を褒めそやしていたけど、鬱病を患ったことで私の競争力が大きく損なわれると、かつてミサキを理解しなかったのと同じように、私に対しても理解を示さなかった。
東京駅にたどり着いてから在来線に乗り換えて一時間ほど揺られた。たどり着いたのは私がそれまで思い描いていた東京のイメージとはずいぶん違う小さな駅だった。改札の前にはミサキが立っていた。何年も会っていなかったが、自分によく似た顔をしているので、すぐに彼女だと分かった。「久しぶり」とミサキは私にニコニコ笑いかけた。今はこちらのレコードショップに勤めているのだという。近くに停められていた軽自動車に乗り込んで彼女の家へと向かう。「夕ご飯は食べた?」と運転しながらミサキは私に訪ねた。車内のスピーカーからは聞き覚えのある洋楽がささやかな音量で流れていた。
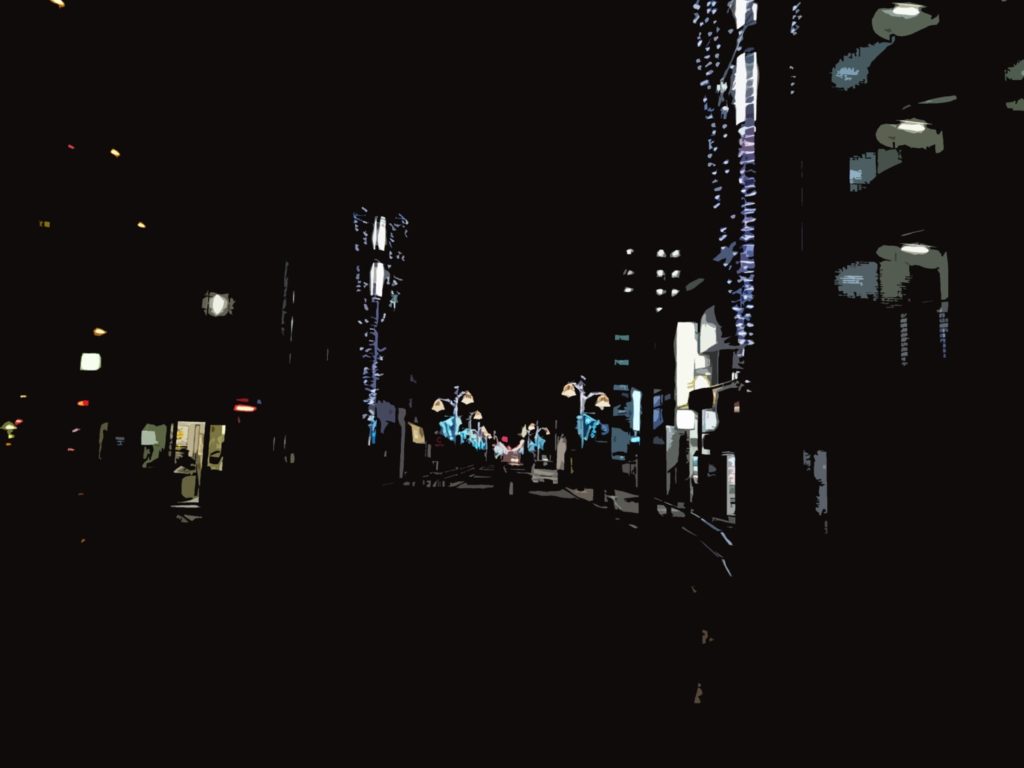
あとがき
「家族から愛された実感がない。だから自分を愛するひとの目線で書いて欲しい」ということでオーダーいただきました。
本文中にも書きましたが、愛を伝えるためには、相手のことを理解しようと努める気持ちが必要不可欠です。完全に理解することはもちろんできないけど、「もっと知りたい」とお互いに思う気持ち互いの距離を近づけ、そこではじめて愛の遣り取りが可能になるのでしょう。
お話をするなかで驚かされたのは、依頼者さんが「愛された実感がない」と言いながらも、ご自身は「愛するための理解」という姿勢を本当にしっかりと持っていたことです。「自分が欲しいものほど他者に与えていく」というのは、これはなかなか凄いことだなぁと。
2019/04/10/辺川銀