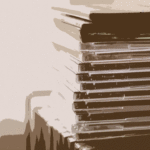アラームの音で目を覚まして部屋のカーテンを開けると皮肉なことにとても天気が良かった。それでも僕は普段と同じように朝食を摂りスーツに身を包んで自宅を出発した。
駅へ向かう途中の遊歩道で泣いている子どもを見つけた。年齢は四歳か五歳ぐらいだろう。幼稚園のものと思しき制服を着ているが周囲に保護者らしい大人の姿はなかった。送迎の途中ではぐれてしまったのだろうか。
普段の僕であれば迷うことなく声を掛けただろう。もしも彼の持ち物に自宅か幼稚園の住所や連絡先が書かれていたならばきちんと連絡した上で送り届けただろう。連絡先が分からないなら近くの交番まで連れて行っただろう。そうすることで仕事に遅刻し、上司から幾らかの文句を言われようとも、目の前で泣いている子どもを助けることの方が正しい行いだと信じて、手を差し伸べただろう。
だけれど今日の僕はそれを躊躇した。子どもに歩み寄る足を止めて立ち尽くしてしまった。後ろから歩いてきた僕よりもひとまわり年上であろうスーツ姿の男やイヤホンをした大学生ふうの女などは泣く子を見ても我関せずと横を通り過ぎて駅へと向かっていった。自分もこのまま見て見ぬ振りをして素通りしてしまおうかという考えが僕の頭の片隅に生まれていた。
「正しいひとでありなさい」と言われて育ってきた。ここでいう正しいひとというのは誰に対しても誠実に振る舞うひとのことだ。嘘や隠し事をしないひとのことだ。ひとには優しく自分には厳しく奉仕の心と不断の努力を両立するひとのことだ。そんなふうに生きれば幸せになれると小さな頃から僕は教えられた。そしてその教えを疑うこともなかった。実際にこれまで出会ったひとの多くはきちんと誠意を示しさえすれば同じような誠実さを僕に返してくれた。先が見えない努力の先には充分な成果が必ず待っていた。
「正しく生きれば報われるなんて。恵まれた世界しか知らないのね」
数日前。アサミは憐れむような笑みを浮かべて僕にそう言った。
アサミと知り合ったのは一年ほど前だ。学生時代の友人が催したホームパーティで出会った。控えめだが常に周りをよく見ていて気遣いのできる女性というのが最初の印象だった。僕はその場で彼女に好意を抱いた。そして彼女も僕の好意にすぐ気付いたのだろう。その場で彼女から声を掛けてくれて連絡先を交換した。後日ふたりで出かける約束を交わした。
実際には、アサミはただ控えめなだけの女性ではなかった。彼女はひとから褒められることが好きなのだといった。可愛いと言われることや好意を向けられることがとても好きだといった。そしてひとから褒められるためにはどうすれば良いのかをアサミは知っていた。好意を効率よく獲得する技術を備え持っていた。その技術を用いてアサミは、彼女自身の言葉を借りるのなら、様々な男たちと「遊んだり遊ばれたり」していた。厄介だったのは、こういった恋愛観をアサミ自身の口から聞かされた時点で僕がすっかり彼女に恋をしていたことだった。
アサミに恋をしてはいたものの、僕は彼女の振る舞いを正しいことだと捉えることができなかった。彼女自身の技術で以て恋をするよう仕向けておきながら、その恋心を遊びの道具と捉えるような態度は、どうにも優しさや誠実さを欠いているように感じられたからだ。だから僕は――いま振り返るとそれ自体が酷く傲慢だが――できることならアサミには正しいひとになって欲しいと願っていた。正しく生きればひとは幸せになれると信じていたからだ。アサミのように正しさの逆をいけば幸せにはなれないと思っていたからだ。僕はアサミに恋をしていたから、彼女には不幸な日々ではなく、幸せな日々を過ごしてもらいたかった。
それにアサミだってなにも最初からなろうとして「遊んだり遊ばれたり」するひとになったわけではなかった。彼女は他者に自分を褒めさせることこそ得意だったけど、自分で自分を褒めることは苦手なようだった。外でどれだけ可愛いと言われたって、部屋や浴室で鏡を覗き込んでいる時はどこか不安げだった。多くの好意を獲得することはできても、自分自身を好いてあげることには抵抗がある様子だった。自身のことを好きになれない分、他者から多く好かれる必要があったのだろうと思う。
だから正しいひとになって、自分の行いに自信を持てるようになれば、「遊んだり遊ばれたり」することがなくても満ち足りることができるに違いないと、僕は考えた。そうなるために手を貸すことが僕の役割なのだと愚かにも思っていた。
僕が自分の愚かさを思い知ったのはつい数日前だ。あの日の僕とアサミはファミリーレストランの机を挟み向かい合って座った。そして彼女の隣には見たことのない細身の男が座っていた。何より僕を驚かせたのはこの時ふたりが怪我をしていたことだ。アサミの右手の中指と薬指には包帯が巻かれていた。男の方は目の周りに生々しい大きな青あざがあり、腕や手の甲には生々しい引っかき傷が幾つも残っていた。細身の男は初対面の僕に挨拶もせず目線もほとんど合わせることがなかく、正しいひとには到底見えなかった。
「正しく生きれば報われるなんて。恵まれた世界しか知らないのね」
アサミは憐れむような笑みを浮かべて僕にそう言った。
「わたしはあなたと違って、間違えないで生きることなんかできない。だからこっちの彼みたいに、一緒に間違えてくれるひとの方が好きだわ」
皮肉のような晴天の下で小さな子どもが泣く。その様子を遠巻きに眺めながら僕は考える。今すぐあの子に優しく声を掛け、手を差し伸べることが、これまで僕が信じて疑わなかった正しい行いだ。けれど僕が信じてきた正しさとは何だったのだろう。僕とアサミはおそらく二度と会いも話しもしない。正しいひとを目指していても手に入らないものはあるのだと分かった。正しくあれば幸せになれるなんて嘘なのかもしれないと初めて疑っている。もしも幸せに繋がらないのであれば、僕が正しさや誠実さを求めて振る舞うことに意味はあるのだろうか?
意味はないかもしれない。
そう心の中で呟き、僕はようやく足を前に進んだ。泣く子の前に膝をついてしゃがみ、出来るかぎり柔らかく見える表情を作って、どうしたの? と訊ねた。生まれて初めて本当に正しく在れたような気がした。

あとがき
「正しいけれど自分には合わない男性」「正しくないけど自分と気が合う男性」いずれかの視点から見た自分を書いてほしいということでオーダーいただきました。お話する中で「高級だけど口に合わないお菓子や、安価だけれど自分の口には合うお菓子ってあるよね」という話題になったのが面白かったです。