 掌編小説
掌編小説 魔法と森と赤い石
なんでお前は魔法を使わないんだ。魔法を使えばもっとたくさん作品を作れる。もっと多くのひとに届けられる。もっともっと金だって稼げるし生活も良くなるんだ。見たところ飯だってまともに食えていないだろうそんなに痩せてしまって。
 掌編小説
掌編小説 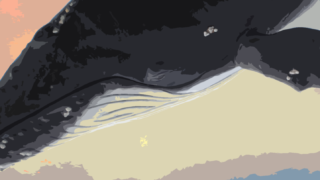 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説 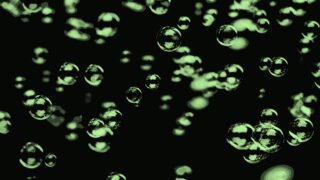 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説 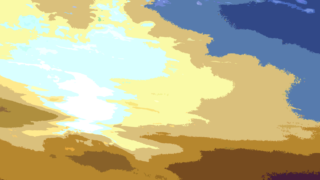 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説 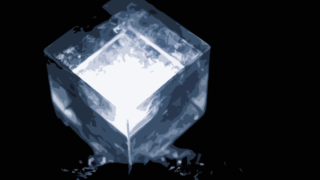 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説