 掌編小説
掌編小説 顔のない世界で
あたしには、ひとの顔が見えない。その他のものは正しく見えるのに、まるで映り込んだ一般人の顔にぼかしをいれるテレビ番組みたいに、ひとの顔だけが見えない。
 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説 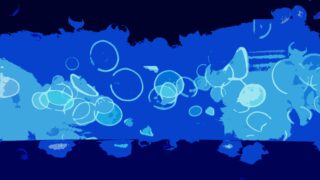 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説 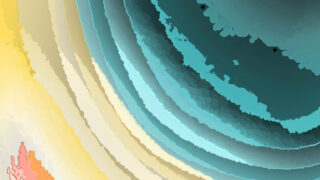 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説 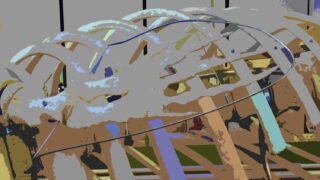 掌編小説
掌編小説  掌編小説
掌編小説